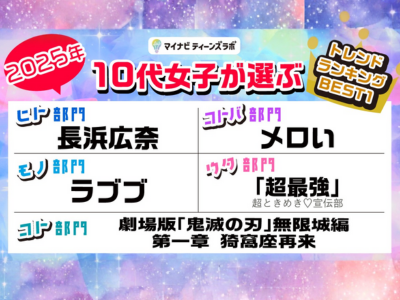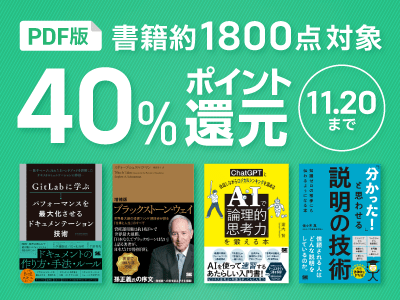数多くトライすること、運用体制を確立することに注力
青葉――MITができて約2年になりますが、現在の課題はどのような点にありますか?
小林:前述のように、デジタルマーケティングは、何をすれば効果が出るのか、という知見を積み重ねていく仕事です。そこに2つの課題があります。
1つ目は、数多くのトライと検証ができるためのサイクルと環境をつくること。そして2つ目は、そこで得られた成功・失敗パターンを組織知化して、運用レベルにのせることです。
1つ目の、トライ&エラーのフェーズでは、打席数を多くするためのフローや、仮説を検証するための測定条件の整備が大事になります。それから、2つ目のフェーズでは、効果のインパクトを大きくするために、一気に大量に進める運用の仕組みと体制を構築することがポイントになります。これらは言葉で表すとシンプルに見えますが、組織としての意思決定プロセスや業務分担を変えていくことは、なかなか一筋縄ではいきません。
リクルートには元々、個人各々が自由に創意工夫することを尊重する文化があります。しかし、デジタル領域で効果を最大化するためには、個人レベルの突破力だけでなく、組織としてのプロセス・体制を、きちんと環境設定していくことも必要だと、この数年で実感しました。
青葉――スピーディに知見を探し、運用体制に一気に持ち込むときにどのような苦労がありましたか?
有効な集客手段が激しく変化していくマーケットのなかで、トライする案件の優先順位をどう付けていくのか、運用体制が自律的に回るための組織力学をどういう仕掛けで作っていくのか、などについては今でも苦労しています。たとえば、サーチの結果に関する営業サイドからのイレギュラーな要望があったり、外部のIT事業者から新しい提案を受けることも多い中、判断のスピードを上げることも大切だと思います。
私自身は、ずっとマーケティング畑にいた人間でもないですし、ましてやITのプロでもありませんが、MITにおいてはスタッフが思い切り能力を発揮できるような環境をつくることが最大の責務だと思っています。