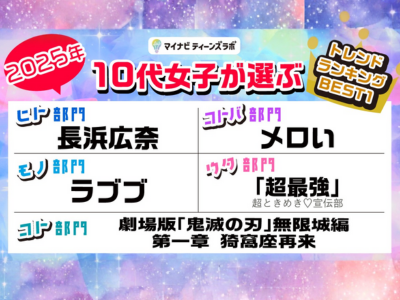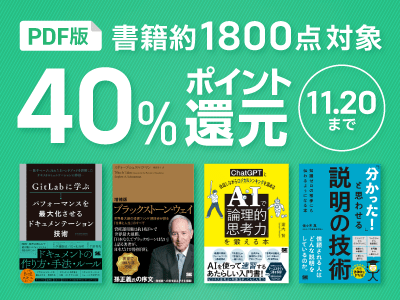企業と読者をつなぐサロンWEB
――企業がサロンWEBのコミュニティを活用して、共創マーケティングに取り組む事例も進行していると伺いました
髙谷氏:花王さんの企画で「新商品発表会」というイベントを行いました。イベントの前後に参加者にはコミュニティ内で、トークとアンケートに参加してもらいました。さらにイベントレポートをコミュニティで報告して、参加されなかったかたにも商品のサンプルを送り、使った感想をコメント投稿してもらう、という流れになっています。

イベントに参加した花王の担当者さんも、参加者のコミュニケーション能力の高さに驚き、生活者の反応を直に聞ける機会を喜ばれていました。また、サンプル応募には460件以上の応募がありました。応募者のコメントは、イベントレポートをよく読んでおられること、新商品に関心を持たれていることが伝わるものばかりでした。他人の体験を読むだけでなく、自分も体験できることへの期待を感じました。
中には「イベントに友だちが参加してすごくよいというので、使ってみたい」というコメントもありました。参加者が他の人に伝えるという流れが自然に生まれていて、PVなどでは測定できない質のよい共感が生まれています。
他にも調味料のモニターの企画も動いています。その企業は、ある調味料のコンセプトを「こだわり」にするか「簡便」にするかで迷っています。ですから、サロンWEB内で会員にアンケート調査をしています。
アンケートは自由回答や、実際に作った料理をアップしてもらうといったハードルの高い調査です。ですが先ほどご説明したとおり、『オレンジページ』の読者が回答者なので、非常に質のよい回答が返ってきています。
――『オレンジページ』読者ならではの属性、回答などが企業モニターの企画とマッチしているのですね
髙谷氏:仰るとおりです。現在一緒に取り組みを進めているのは、いわゆる雑誌広告クライアントである大企業や有名メーカーです。今後は、自社でマーケティングリサーチができない中小メーカーと、一緒に商品開発をするというような施策の可能性も感じています。
また、7月からはマスターカードと提携し、法人カード会員向けにマーケティング支援をする「ビジネス・アシスト」に参加する予定です。出版社のノウハウやスキルを活用し、サロンWEBを含む「くらし予報」のマーケティング支援サービスを、これまで、雑誌への広告出稿とはご縁のなかった企業にも広く活用いただけるようになると考えています。
――雑誌から離れるという点に不安はありませんでしたか?
髙谷氏:出版業界において「雑誌」の販売部数は17年連続で減少しています。このような環境下で、出版事業以外の事業の創出を積極的に展開することが求められています。その一環が、サロンWEBを通じたBtoB( toC)ビジネスの推進だと考えています。不安がないと言えばうそになりますが、読者から離れるわけではなく、より、深くかかわる場を設けることで、自社ブランドの強化にも繋がり、紙の刊行物だけでない広がりにつながることを期待しています。
社内の説得するためには、小さな成功の積み重ねを
――共創マーケティングを開始するにあたって、社内の反応や期待度はいかがでしたか?
髙谷氏:以前、農林水産省のプロジェクトで長期間にわたって、ワークショップ、MROC(マーケティングリサーチのためのクローズドコミュニティのこと)、実食イベント、誌面タイアップを組み合わせた施策を行ったことがあります。その時はサロンWEBがなかったのでMROCを使ったのですが、読者モニターの皆さんは抵抗なくコメントをしてくれました。
このプロジェクトを成功事例にできたので、社内の説得材料にしました。メリットとして、当社のクライアント企業が『オレンジページ』の読者をターゲットにマーケティングができる点も、社内へのアピールになりました。
――コミュニティ開設前にパイロットプロジェクトで成功事例を作っておいたというわけですね、素晴らしい計画だと思います。サロンWEBでの共創企画は誌面ではなく、読者の協力を活かした施策です。コミュニティ構築に向けて、その後、どのようなステップがありましたか?
髙谷氏:コミュニティを立ち上げる前に、読者に対してライフスタイル全般についての意識調査を実施しました。私たちのお客様がどのような方々で、どのような価値観を持っているのかを把握したかったのです。おかげで読者像を確認できて、社内に共有できました。
これまでも「オレンジページの読者はこんな人だよね」という、ぼんやりとした共通イメージはありました。ですが、調査を通して当たり前と思っていることを、数字や形にすることは非常に重要だと改めて感じました。「料理が好き」とはどういうことなのか、読者はどこに価値を置いて生活しているのか、ということが具体的になり、読者像を大きく6つのパターンに分類することができました。
また、自分たちでクラスタ分析を行ったのですが、この分類は不変ではなく可変のものだということも分かりました。高度な分析は調査会社に依頼する必要がありますが、声なり数値なりに最後は自分たちが向き合わないとわからないと実感しましたね。