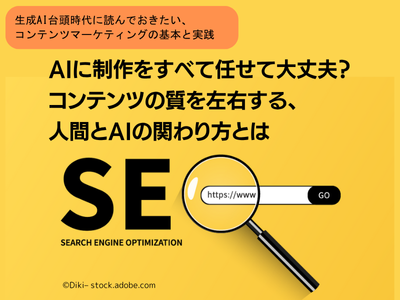ファンが熱狂しない動画は広がらない
「ついつい僕たちは、裾野を拡げるような編集をしてしまう」と語る鈴木氏は、「そもそもファンを熱狂させることができなければ、ファン以外に広がるわけがない」とも指摘する。
「ファン以外の人は、ファンが動画に対して熱狂している姿を見て“何が起きているんだろう?”と興味を持つわけです。いきなりファン以外に拡げていくのは、とてつもなく難しい。まずファンに向けて0.5を1に、1を2にしていくことをする。一方で企業からは全員を1から2に変えてと言われることが往々にしてありますが、それができたら奇跡に近いです」(鈴木氏)

「私も同意見ですね。YouTuberの作品をいくつか見直してみて思うのは、制作するたび作品に変化があって、ファンがその変化を楽しんでいる。つまり、ファンに喜んでもらうにはこれまでの作品の系譜をくみ取った企画にする必要があります。そうすることで、通常のタイアップ動画より再生回数が上がり、結果的にインストール数などのKPI向上につながった実績があります」(桑野氏)
鈴木氏によれば、最近そうしたことを強烈に感じさせられたYouTuberがいるという。それは、UUUMに所属するYouTuberのFischer's(フィッシャーズ)だ。全作品の再生回数が8億回を超えている、大学生や社会人7名によるグループである。
「彼らの動画がなぜ面白いのかを考えることが最近の研究テーマの一つです。ある若手芸人に教えてもらって作品を見たんですが、正直わからないんですよ、面白さが(笑)。ただ、小中学生を中心にとても見られている。
毎週、楽しみにしていたあのお笑い番組、みたいな僕らのノリが、今は“スマートフォンで見る10分の動画”に変わってきている。小中学生の中にある“感覚”に見事に合っていて、かつカジュアルに楽しめる内容になっています。編集もうまいし、ついつい僕も繰り返し見てしまいます」(鈴木氏)
“なんか面白い”で、片付けてはダメ
自分たちにはわからないけれど、“何か”面白いことが起きている……そんな問いかけをしたときだ。鈴木氏は、「何か」と言ってしまう姿勢に苦言を呈する。
「何か、と言ってわかったフリをしてしまう時点で、もう気づけない大人になってしまう。小中学生にとっては、強烈に面白くてファンもいるわけで、そこには明確な理由があるはず。そこは、僕たちは制作と発信する側として、何が面白くて刺さるのか、詳しくリサーチして理解しなければならない。そこを理解した上でYouTuberと仕事をしないと、どうせ俺らを商売で使いたいだけなんだろう、とYouTuberに見透かされます」(鈴木氏)
最後に、これからのWeb動画の向き合い方について、両者に話を向けた。
「今後、もっと競合他社が出てくる。そのときに、僕らの強みはここまで積み重ねたYouTuberとの関係性、仲間みたいな気持ちです。例えば、5倍以上のギャラを出すという相手にも渋谷クリップクリエイトを選んでもらえる、という関係性作りが大事です。
最近、ちらほら見かけるのはテレビCMで予告をして、ネットでロングバージョンという組み合わせ。好きな人をより好きにさせていく方法、きちんとメイン扱いをしたWeb動画がどんどん出てきそう。僕らもその一翼を担いたいですしね」(鈴木氏)
「業界でも認知されるようになり、設立からの制作実績も1,000本以上になりました。今後は、弊社発の動画サービスやメディア作り、エンドユーザーが直接見たり使ったりするサービス開発に挑みたいです」(桑野氏)