非日常ではなく「こんな日常だったら」を提供する
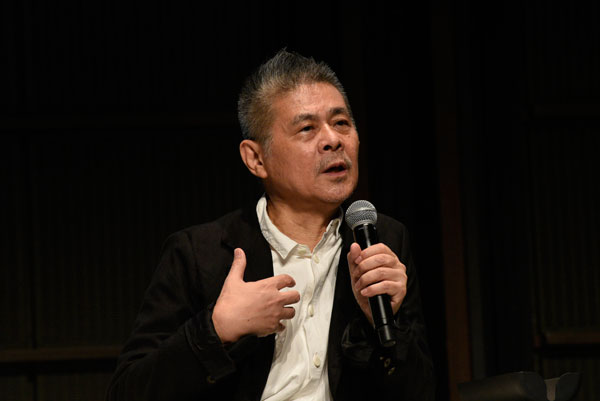
糸井:気といっても、それを測るメーターがあるわけじゃないので、人間と人間との間で何か……子供が一人泣くと皆がつられて泣くような?
唐池:いいとこ突いてますが、違いますね。
糸井:出直してきます。
唐池:人からの共感じゃなく、一人でも泣いてしまうんです。それは、「気」としか考えられないなと。中国思想に基づく考え方で、気の力で病を治す気功術、あるいは相手を投げ倒す合気道にも通じる、見えないけれど人間を動かしているのは気だという考えですね。欧米の方には伝わりにくいんですが、エナジーというとわかるようです。
で、エネルギーというのは中学のときに理科で習いましたね、熱エネルギーが運動エネルギーになったり、電気エネルギーや光エネルギーに変わったりと、どんどん変化していく。ななつ星に込められた気は、エネルギーですから、見たり乗られたりした方の中で感動というエネルギーに変化するんです。これしか、皆さんが号泣するのを説明できない。
糸井:その場に居合わせただけで、じわりとこみ上げてくるものがあるということですよね。実は唐池さんはじめスタッフたちが、ものすごく細かくやってきたいろいろなことが、目には見えない物語としてそこで華開いている。
唐池:そこに気が詰まっていて、ご覧になった方が感動のエネルギーに変えていく。それこそ糸井さんのおっしゃる、ななつ星こそ感動という情報を発信するメディアだということが、私は分かったんです。
糸井:地元の人に取ってみれば、たとえばディズニーランドみたいな施設ができたら、一目で全部が把握できる気がするのでわかりやすいじゃないですか。イベントも、メディアですし。でも、ななつ星は昔からあるローカル線の線路を列車が走って回ってきて、で、博多に帰ってくる。どこへ行くのかと思ったら元のところへ帰ってくるんですよね。
その、行程を味わうということを、鉄道ができたばかりで「列車は人をどこかへ運ぶものだ」と思っているころはわからなかったんじゃないかな。
唐池:あの、糸井さんが好きな言葉で。
糸井:僕が好きな言葉ですか、どうして知ってるんですか。
唐池:や、うすうす。「生活」ですよね。「おいしい生活」から始まって、なんとか展覧会ですか。
糸井:「生活のたのしみ展」です、覚えてくださいね。
唐池:その「生活」なんですけど、先日、由布院温泉の老舗旅館のひとつである亀の井別荘の中谷健太郎さんとお話しする機会がありました。由布院というのは我々今まで、非日常を客に提供していると思っていたんですが、違うんです。由布院は、「こんな日常生活があったらいいな」というものを提供しているのだと。
だから、ディズニーランドには非日常がありますけど、由布院には「こんな日常があったらな」がある。それで、ななつ星もよく考えたら、同じなのかなと思いまして。ななつ星には7両の車両に14の客室がありまして、よく「走るホテル」だと紹介されたりしますが、最近私は「走る街」であり「走る生活」だと言っているんです。部屋こそ別々ですけど、食事のときには皆でひとつのダイニングカーに集まっていただいてね。まるで江戸時代の長屋みたいに。
究極の楽しみや喜びは「生活」にある
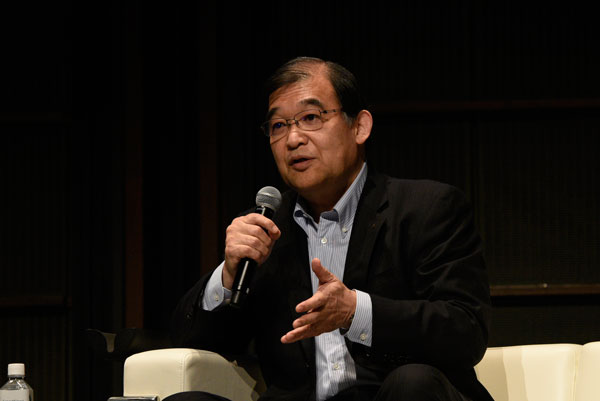
糸井:あっ、そうですね、長屋の井戸ですね。
唐池:通路を挟んで部屋があってね。ななつ星も、旅の間にお客様同士が仲良くなるんです。ホテルだとそういうのはないので、だからこれは14組の「走る街」なんだと。デザイナーの水戸岡さんに聞いても、やはり街づくりという観点でつくられているとおっしゃいます。
糸井:動いている生活、動いている街。
唐池:動いている「おいしい生活」。
糸井:どうしても縁をつくろうとしてくださって、ありがとうございます。今の「おいしい生活」にもかかわりますが、日々の「ハレ」と「ケ」でいうと、「ケ」の部分がいちばん嬉しいものでありますように、というのが「生活」という言葉が行きたい場所ですよね。その「おいしい生活」というコピーを考えて世の中に出たのが1982年でしたが、そのひな形みたいなのを僕は見たことがあるんです。
これは西武百貨店の広告ですから、当時の打ち合わせに、亡くなった堤清二さんがいつも来てくださっていました。それでいつもごはんをごちそうしてくださるんです、本社にそういう場所があって。それが、普通においしく炊いたお米と、みそ汁と干物、ポテトサラダかなんか、ちょっと焼き海苔かな。気の利いた旅館の朝ごはんみたいなものなんです。
望んでいるのって結局、これがピークだというようなごちそうじゃなく、毎日食べ続けてもおいしいもの、「これがやっぱり大好きなんだよね」といわれるようなものじゃないかなと思って。自分も、そっちの方向に行きたいんだろうなと思ったんです。
唐池:そうでしょうね。究極の楽しみや喜びは、生活にあるんじゃないかなと思いますね。
糸井:もちろんそれぞれ仕事もしていますけど、やっぱりいちばん長く過ごしているのは「人間」として生活している時間なので。今までは、仕事の現場がどれくらい興奮をつくってくれるかとか、何の仕事をしたかとか、そういうところに過重に重心がかかってきたと思います。でも、ただの人としてどれだけ素敵だったかということに、もっと目を向けてもいいんじゃないかなと。
唐池:それは糸井さん、1982年に「おいしい生活」を書いたときに既に気づかれていたんですね。生活こそいちばんの、究極の人間が求めるものだと。
糸井:いちばん短く人間をいうと、ただ生まれて生きて死んだ、というだけですが、それが「よかったなぁ」と思えるかどうか。あるいは亡くなったときに、肩書き云々じゃなく「あいつのお葬式だから行きたい」と思ってもらえる人でありたい、という。
唐池:そうですね。会社を離れても、何人の人がお葬式に来てくれるかですよね。



































