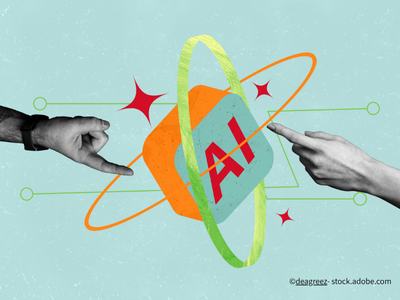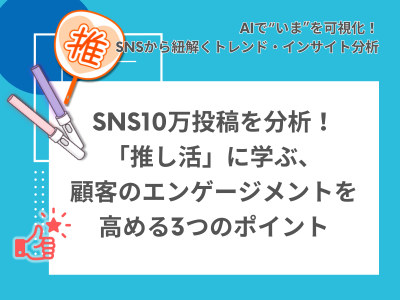相手の求める情報の伝え方ができているか
中川:「相手の気持ちで考える」というのは、多くの人が幼い頃からずっと周りから言われていることのはずですし、「自分はできている」と思っている人も多いと思います。ですが、本来は誰にでもできるはずのことが、できていないという現状があるのも事実です。「相手の気持ちで考える」ということをできなくしているのは、一体何なのでしょうか?
阿部:ひとつは単純で、ほとんどの場合「相手」は知らない人、つまり「他人」だからではないでしょうか。サービスや観光を生業にしていない普通の人は、自分とは関係のない他人に対して親切にする必要は必ずしもないですよね。
でも、こと観光に関しては、初めていらした方や、初めてお会いした方を含め、「よく知らない相手」に楽しんでいただく、という仕事ですから、そこには他人という存在が不可欠で、その人たちがいてくださらないとビジネスとして成立させることができません。当たり前のことですが、そういうことが認識されていないために、サービス業や観光業に携わる人の多くが「相手の気持ちで考える」ことを実践できていないのではないでしょうか。
それともうひとつ、日本では、「慮ること」とか「以心伝心」、あるいは「察すること」、そういうことは「よいこと」だと認識されていますが、それを表現するとき、「控えめ」で「慎ましい」のが美しいということも、私たち日本人には刷り込まれています。その刷り込まれた価値観によって、日本人は表現の仕方がはっきりしない、わかりにくい傾向にあると思うのです。いつでも控えめになってしまうと伝わりにくいこともありますよね。多くの人が思い当たると思います。
でも、世の中が急速にグローバル化するなかで、私たちが接する相手は日本人だけではなくなりました。どうすれば伝わるか、という部分は、目の前の相手によって変えていかなければいけない時代になったのです。つまり、表現の仕方をそれぞれの相手に伝わりやすいように使い分けられるようにならないといけないのですね。
別の言い方をすれば、相手にとっての“親切”は、相手によって違う時代になってきているということです。そのことを理解しないまま、やり方・伝え方を変えない状況がいまの日本です。それでは、相手の気持ちにはいつまでもなれません。
最近、あるアメリカ人女性から「同僚から突然ランチに誘われて、気味が悪い」と言われたことがありました。よくよく話を聞くと、彼女は先日その同僚の翻訳を手伝ってあげたのだそうです。「その翻訳のお礼だと思う」と伝えるも、「それなら『昨日はありがとう、お礼に僕がランチをおごるよ』と言ってくれないとわからない!」とのこと。
わざわざ口にせず、さらっと、粋にご馳走したい、そこは察してくれるよね……という感覚は、日本人同士でしたらわかるかもしれませんが、彼女は「気味が悪い」と感じた。それくらい、異なる文化やバックグラウンドを持つがために、人によって伝わり方は異なるということです。
地域についても同じことが言えます。誰にどう感じてほしいのか、そのためにどう伝えるかについて、きちんと考え行動することが必要です。誰かが旗を振らないと、強いリーダーがいないと、変わっていかないことなのかもしれません。
その意味で、先ほどは「地域活性は地域の中から」と言いましたが、一方で「よそ者」の目が必要であることも事実です。他者の知恵がないと、自分たちだけでは考えきれないかもしれないし、ユニーク性があっても気づけないかもしれません。他者も交えながら、自分たちのユニークネスを整理することが必要になってくると思います。
村山:発信する内容の面白さ・ユニークさと同じくらいに、それを伝わるように相手の気持ちで考え、工夫して発信する努力も重要ですよね。全く知らないもの、あるいは興味がないものは、どんなに歴史的価値があって素晴らしいものでも「ふ~ん」で終わってしまいます。このような非常にもったいない事態を、相手目線で伝わる情報として事前に提供することによって変えていけると考えていて、個人的に「ツーリズム・ラーニング」と呼んでいます。
例えば、中国人の方に「山口県」と言っても、知らない人が大半です。仮に知っていたとしても、他のエリアとの違いまではわかっていない。ただ、「長州」と言うと、幕末から明治維新の歴史のなかで知っていたり、強い興味を持っていたりする人も多々いて、全く反応が変わってくるんです。このことをきちんとわかっていて、中国人に伝わるように「長州」というかたちにして情報を発信していたら、山口県に対して、より興味を持ってもらえるようになるはずなのです。

中川:表現の仕方についての話が出ましたが、慎ましく・控えめであることをよしとする文化が日本には確かにあって、「そうじゃなくてもよいんだ、自分の個性を出してよいんだ」という風土は、組織づくりの側から働きかけ、つくっていく必要があると思っています。
川崎のホステルの元支配人は、20代の女性なのですが、初対面の人に対して「ゆるく接する」ことをしていると言っていました。例えば、北海道から訪れたお客様に「鼻水って本当に凍るんですか!?」と話しかけてみる。あまりにくだらなくて、肩の力がふっと抜けちゃいますよね。そうやって、相手をよい意味で「くずす」ことをしていくことで、親しみやすさを感じてもらい、リピートを獲得しています。会社としてそのようにすべきだとは、一度も言っていません。彼女自身が、「ゆるい接し方があってもよいんじゃないか?」と考え、行動した結果です。
彼女は前職のシティホテル時代を振り返って、フロントに入っているときは、たとえ目の前で子どもが転んで泣いていても、駆け寄って助けてあげることができなかった、と言います。少々極端ではありますが、「ただひたすらチェックインをさばくことしか考えていなかった」そうです。今は、目の前のゲストに対して、こうしたら喜ぶかな?こうしてあげたらどうだろう?と考え行動できることにやりがいを感じています。
「人の気持ちって、こうやって動くんだ」と実感できることは、つぎにまた「相手の気持で考える」ことの原動力になる気がしますね。「こう表現したら相手が喜ぶはず」と考えて行動する、それが実現できる土台として、会社がつくる風土が重要ということでしょうか(図3)。

自分の外側で起きていることを知る
村山:なぜ相手の気持ちで考えることができないのかと考えたとき、海外経験・異文化経験が少ないからというのも、やはり一つの原因だと思います。講演などで、年間50回以上は地方に足を運んでいるのですが、そのなかで、参加者の方々に海外経験について聞くこともよくあるんです。結果、プライベートはもちろん、仕事でも海外へ行ったことがない人、あるいは数回だけの人というのが多いです。
私は、インバウンド対応を考える方たちに対して、「自分が海外旅行へ行った時に受けたサービスや対応で、よかったこと、悪かったことを整理して、よかったことを日本に来る外国人観光客にもしてください」とお伝えすることがよくあるのですが、海外に行ったことがないと、その気持ちもなかなかわからないなと感じています。海外経験や異文化経験がないと、相手の気持ちで考えようと思ってもギャップが大きすぎてしまいます。言葉や宗教、生活習慣なども大きく異なるので、なかなか想像力が働かないんですよね。
改めて周囲を見渡してみると、子どもの頃や若い頃から海外・異文化体験をした方が、特にインバウンド分野で活躍している方にはとても多いと感じます。今後、長い目で見ると、若い世代への異文化教育が日本のインバウンドの発展の鍵を握るのではないかと思えてなりません。
阿部:島国だからなのか、日本では常識の幅が狭いというのもあると思います。違うものがあるということや、人によって異なる常識があるということ自体、感じていない人が多いのではないでしょうか。そしてまた、世界から見たとき、私たちがいかに“異文化”であるか、ということにも気づいていないと思うのです。
井庭:海外に出て、日本や自分のことを知るということは、確実にありますね。僕自身の経験でも、他の国に住んでみて初めてわかったことはたくさんあります。短期間でも住んで生活してみる、というのは、違う次元の気づきが得られるものです。自分のこれまで馴染んできたものとは異なる世界を体験することで、その国・地域の文化・感覚を知るとともに、日本人としての自分や、日本という国・文化のこともよく理解できるようになります。
これまで「当たり前」だと思って来たことが、日本の外では必ずしも当たり前ではなく、それは特殊な一つのケースだったのだ、ということを痛感します。そういうわけで、そんなふうに住んでみるのでもよいですし、旅行・出張でもよいですし、何はともあれ、海外に出てみるというのは、とても大切なことだと思います。

でも、実際には、様々な理由で海外に行けない人もいるでしょう。そういう場合には、これまでの人生のなかでの「他者」との経験が大切になります。海外でなくても、日本の違う地域・町に住むとか、来訪者との触れ合いなど出会った人との視点や感覚の違いを感じて、思いを馳せる想像力を育んでいくことができるでしょう。
村山:そうですね。多様性を受容し、そのなかでどこまで経験できるかが鍵のような気がします。よい面、悪い面を知って、いかにバランスを取れるかどうか。
中川:私自身は英語も話せませんし、それこそ海外経験もありません。それでもなぜこの本をつくっているか、本をつくってまで届けたいことは何なのか……それは「このままでは生きていけない」という危機感を感じるからにほかなりません。このままでは経営は立ち行かなくなると肌で感じます。それは自分の会社はもちろんそうですし、日本全体についても同じことを思っています。
とある高校でキャリアに関する授業を担当したとき、20名の高校生に対して「インバウンドという言葉を知っているか」と聞いたことがあります。なんと、知っていると答えたのはたった2名でした。そしてその2名が「インバウンド」という言葉に抱くイメージは「爆買い」。多くの高校生はまだビジネスの現場もリアルも知りませんから、当然といえば当然なのですが、私自身が日々の経営のなかで感じている現実とのギャップがものすごく大きいのです。
そこで今度は、高校生たちに、日本の主要産業に関するデータを見せます(図4)。「自動車」「半導体」「鉄鋼」「自動車部品」「インバウンド消費」の上位5つのうち、インバウンド消費以外は今後低迷していくことがほぼ確実です。「自動車も、半導体も、鉄鋼業も、今後は厳しい。そうなると残るはインバウンド消費のみ。インバウンド消費、すなわち観光業は、これからの日本の主力産業になるんじゃないの?」と伝えるも、いまいちピンときていないような反応です。10年、15年後には自分たちが必ず乗り越えていかなければならない課題であるにもかかわらず、です。

このような認識は学生に限ったことではなく、大人にさえ「インバウンドは自分には関係ない」と思っている人が多いように感じます。危機感教育という言い方が正しいかはわかりませんが、学校の授業など、小さな頃からもっと現実・事実を見せていくことをしたほうがよいのではと思っています。
阿部:危機感については、私も機会があるごとに話すようにしています。日本はこれからどんな産業で生きていくんだろう?日本にある資源のなかで、これから売れるものってなんだろう?と。たいてい多くの人はみんな初耳顔でぽかんとしています。ただ、話す順序は重要だと思っていて、危機感からはじまるよりも、地域活性や観光の活性ということに興味を持ってくれた人たちに対して、「あなたが選んだこれって、実はすごく重要で……」と話すように気をつけています。
井庭:危機感を煽ると、人は硬直して固まってしまうんですよね。あるいは、そのことについて考えなくなったり、思考停止してしまったりします。僕は、学生時代、環境・エネルギー問題に取り組むグループで活動していたのですが、そのとき痛感しました。危機感だけを伝えても人は動けないのです。
しかしながら、希望につながる方法・道具がセットになっていれば、話は違ってきます。思考停止に陥らずに、考え出し、動き出すことができるようになります。だからこそ、本書の「おもてなしデザイン・パターン」のような未来への希望につながる道具立てが重要になるのです。危機感を伝えるとともに、そこから自分たちで改善していくためのきっかけとなる方法・道具も一緒に手渡すわけです。
そういう希望の方法・道具だけがあっても、人は動きません。それをわざわざやろうという根本的な動機がないからです。そこで、現状についての認識をしっかり持ち、生き抜くためには、何かを変え、自分たちも変わっていかないといけないんだ、ということを実感することはが不可欠です。変わらなければという危機感と、希望の方法・道具は、いつもセットでなければならないのです。
中川:どう危機感に気づかせるか、というのは難しいところですね。現在、ある地方都市で商店街活性化の仕事をしているのですが、一番難しいと感じるのは、そこそこ豊かで、現状では特に困っていない人がいることです。彼らに商店街活性化の必要性をわかってもらったり、将来を見据えるとインバウンド施策が不可欠と理解してもらうことのハードルはかなり高いと感じています。
阿部:危機感がない人っていますよね。特に、経済的に豊かな地域に多いですね。「困っているから来てほしい」と言われてその地域に行ってみると、本人たちは「まぁ、そこそこ人は来るだろう」と内心実は思っていて、本気で困っていなかったという地域も多いです。そこは変えていかないといけないところですね。
中川:危機感を正しく持てる人、意識が高い人は永遠に一握りになってしまいますよね。
村山:「5年・10年先の将来を考えたら、今のままでは食べていけない」という危機感を持ち、打ち手を打っている経営者は、残念ながら一握りです。目先のビジネスにつながることしかやっていない経営者の方が多いと感じています。
私自身は2007年からインバウンドビジネスに関わっていますが、そういう危機感を持てていない人たちの背中を押すためには、直接危機感を伝えるよりも、ライバルの成功を見せる方が効果的だと思っています。先日、とあるキャンピングカー会社からインバウンド対策についての問い合わせがありました。平日の稼働が少ないなど経営的な課題を認識されていたというのもありますが、問い合わせの決め手は、近くの同業者がインバウンド需要で潤っているから、ということでした。彼らにできているなら、自分もやりたい、何かできないか、と。
もしかしたら根底では危機感にも通じる部分はあるかもしれませんが、ライバルの成功は経営者にとって面白くないものです。ちなみにここで重要なのは、等身大の事例であるということです。自分とは全く規模感が違う地域や会社の成功事例をどれだけ聞いてもなかなか響きません。そうではなくて、等身大の事例、「自分にもできそう」というレベル感の事例こそが、背中を押してくれるのではないでしょうか。
続きは本書で
本書『おもてなしデザイン・パターン』ではトークセッションのあと、「創造的おもてなし」を実践するための28個のパターン(フレームワーク)を解説。顧客とよい関係を作りたい、地域や分野の魅力を引き出したいなど、観光業以外の方でも役立つノウハウが紹介されています。