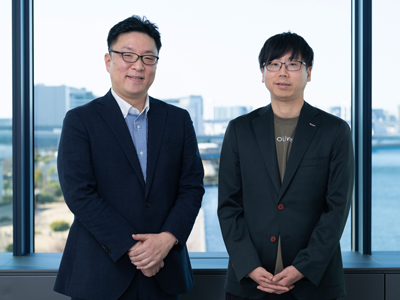会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
新規会員登録無料のご案内
- ・全ての過去記事が閲覧できます
※プレミアム記事(有料)は除く - ・会員限定メルマガを受信できます
- ・翔泳社の本が買える!500円分のポイントをプレゼント
-
- Page 1
-
- Page 2
この記事は参考になりましたか?
- 米国最新事情レポート『BICP MAD MAN Report』連載記事一覧
- この記事の著者
-

榮枝 洋文(サカエダ ヒロフミ)
株式会社ベストインクラスプロデューサーズ(BICP)/ニューヨークオフィス代表
英WPPグループ傘下にて日本の広告会社の中国・香港、そして米国法人CFO兼副社長の後、株式会社デジタルインテリジェンス取締役を経て現職。海外経営マネジメントをベースにしたコンサルテーションを行う。日本広告業協会(JAAA)会報誌コラムニスト。著書に『広告ビジネス次の10年』(翔泳社)。ニューヨーク最新動向を解説する『MAD MAN Report』を発刊。米国コロンビア大学経営大学院(MBA)修了。※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア