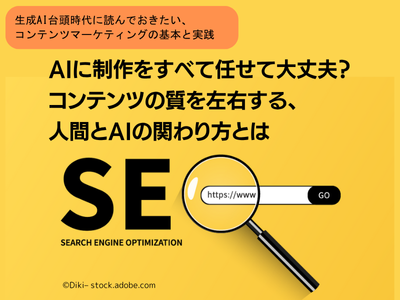音楽業界で指標を定める難しさ
高野:音楽側のマーケティングで言うと、企業の施策に比べるとKGI・KPIが流動的である点が面白くも難しいですね。
以前、あるアーティストのマーケティングを担当したんです。タイミング的にライブも新曲もないからデジタルでの発信を中心に戦略を組みました。つまりKGIはアーティストの好意度や推奨意向の向上などですね。そして、KPIはYouTubeやTwitter、ブログなどそれぞれの媒体の使い分けを決めて、各コンテンツのエンゲージメントの向上をメインにやっていきましょうね、と。ただ、途中から「今、この動画の再生数を増やしたい」といった部分最適のオーダーが増えてしまって……。
確かに再生回数が増えるにこしたことはありませんが、本来の目的を考えた時に注力するところはそこですか?という話になってしまう。もちろん、先方の言っていることも間違いではありません。
ほかにも、デジタル上で存在感が薄くなってきたことに課題を感じるアーティストに対して、クチコミの増加をKPIにさまざまな施策を組んで実行した際も、途中で「ツアーをやるからチケットが売りたい」といった話に変わったこともあります。
こういった流動性のあるKGI・KPIの設定はあり得ると思いますし、理解もできます。結果も出しましたが、やりとりをするなかで、スタッフの方からするとうまく噛み合わないと感じた点があるかもしれません。
山口:音楽に限らないことかもしれないけれど、確かに、今見せたい映像の再生数・ともかく伸ばしたいチケット販売など近視眼になりがちかかもしれない。
高野:ただ、音楽とかアーティストって、曲をやっぱり出さないとか、Aに決めていたけどBにしただとか、可変であることも一つの特長だと思うんですね。だから、マーケティング側にも臨機応変さが求められると考えています。一番良いのはアーティストのチームにマーケティングとして入らせてもらって、一緒に状況を見ながらやっていくことですね。そして、登る先と登り方、登るルートの中で可変させるものと可変させないものの共通認識を持つということでしょうか。
山口:海外ではそういう事例も増えていますね。高野さんのチームでは現在、どうされているんですか?
高野:変化があることは理解しつつ、施策を提案する際には何に寄与して何に寄与しないか、どこにコミットしてどこへのコミットは約束できないか。先ほどの話と重複しますが、登る先と登り方、そして、登るルートと可変させるものと可変させないものの共通認識を持つようにしています。
以前手掛けた、感覚ピエロというバンドと立命館大学のコラボレーションの場合は、立命館にとっては「Beyond Borders」というブランドメッセージを体現するための施策であり、感覚ピエロはTwitterのプロモトレンドでいきなり新曲を発表するというプロモーション施策でした。

大学側にもバンド側にも、この施策で効果を出せるKGIやKPIは●●で、加えてSNS上でポジティブな声があがる反面、●●のような意見も発露される可能性がありますよと説明して、了承を得て実施しました。
KGIとKPIを握っておかないと、何のためにやったんだろうとお互いに思ってしまいます。それでは実績を作ろうとしても、良い体験にはなりませんので。
着火点が変わった今、何をするか
山口:音楽サイドでも高野さんと同じ視点で考えられる人が必要ですが、いないんですよね。だから僕なりにニューミドルマンというコミュニティ活動をしたり、セミナーやったりもしています。
今、ロールモデルの変化がさまざまなところで起きているじゃないですか。レコード会社の中に、デジタルメインの宣伝のことを教えられる管理職はいません。CDを持ってラジオ局に行って、1回流してもらうまで帰らない。ディレクターと仲良くなって、信頼関係を築いて一緒にラジオ局からアーティストを育てていくといったことが彼らの成功体験です。
そのやり方はもう通用しません。成功体験を抽象化して、「今の時代に置き換えたら」と考えられればよいのですが、そういう思考転換ができていないように感じます。
悩ましいのは、アーティスト自身にも同じ側面があることです。自分が憧れているアーティストはビジネスのことがわからなくても、SNSとかやらなくても成功している。だから自分がそうなれないのは、曲が悪いからだと思ってしまう。
曲の良し悪しもありますが、時代が違うんです。観客5人のライブハウスで最高のステージをするところからのし上がるという成功を夢見るのではなく、UGMやSNSを上手に使えるアーティストが人気者になっていく時代認識を持つことが大切ですね。
マネジメントやレーベル、アーティスト、全体が変わっていく必要を感じています。
高野:個人的には着火点が変わっただけな気がしますね。私たちの時代は話題化のきっかけが雑誌やテレビでしたが、今はSNSやSpotifyから話題化したり、THE FIRST TAKEに出ることが一種の登竜門になったり。
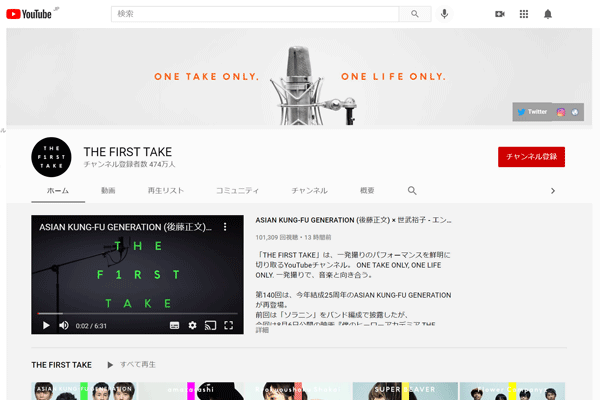
おっしゃる通り、SNSがわかっていないと着火しようがないことは確かです。ただ、デジタルネイティブな人たちにとってはそれが当たり前なので、意識せずにできていると思います。
音楽の広がり方も俯瞰すると構造自体は変わっていないと思います。どんなにSNSやストリーミングで良い音楽を見つけても、伝播の範囲は自分ごと化から仲間ごと化まで。世の中ごと化するには、やっぱりマスメディアの力が欠かせません。