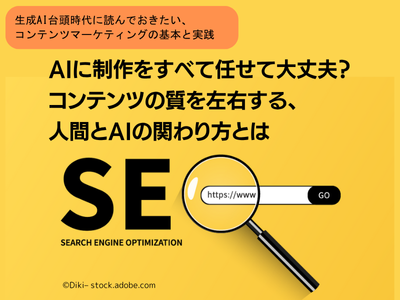各事業の状況・課題に即したデジタル人材を育成
──デジタル本部では、デジタル人材の育成もミッションの1つとして掲げられています。ここでいう「デジタル人材」とは、どういった人材を指していますか?
デジタル人材の育成は、「デジタルマーケティング」「IT」「データ」の3つの守備範囲に分けて考えています。個々人でスキルやノウハウに濃淡はあり、たとえば「デジタルマーケティング」の領域では、現場でPDCAを回す人もいれば、プロデューサーのような立ち位置でデジタルを活用したマーケティング戦略を描く、企画を考えるといった仕事をする人もいます。社内で求められているデジタル人材は部門ごとで様々ですので、先述したデジタル本部内のDX戦略部が全社のDX戦略から必要な人材の全体像を描き、それぞれの事業・部門と協議を始めています。
──デジタル本部が横串となって、全社でデジタル人材の育成を進めているのですね。どのような体制が敷かれているのか、詳しく教えてください。
これまでは、マーケティング部門や営業部門など各事業部門内でピンポイントに必要な人材を考えることが多かったのですが、昨年からやり方を大きく変えました。現在は、各事業部門および人事部門と連携し、中長期的に採用・配置・育成の戦略を立てています。どのような人材を採用するか、採用した人材と既存の人材をどこに配置するか、そしてデジタル未経験者も含めて、いかにデジタル人材を育成・強化していくか? これを各事業部門の戦略と現状から逆算して考えていく形です。すでに、具体的な人材育成プランが動き出している事業部門も出てきています。
育成の1つのパターンとしては、まずはデジタル本部での研修とOJTから始まり、デジタル本部でいろいろな事業部門のデジタル活用のサポートをしながらスキルや経験を積んで、育った人材を各事業部門へ送り出すという流れです。現状、多くの事業部門ではデジタル人材をゼロから育てるのは難しい状況なので、デジタル本部内で育成する方法を取ることが多いです。
そして、私が本格的に人材育成に取り組み始めたのは、遡ると2012年頃からです。いろいろな試行錯誤があり、必ずしもすべてうまくいったわけではありません。成功したパターンと成功しなかったパターンをレビューしながら、今の形にたどり着きました。
──その枠組みでは、各事業部門と密な連携を取ることが求められると思います。どのように協業体制を構築していますか?
仕組みとしては、各事業部門にキーパーソンを置き、それぞれの課題を吸い上げる場を設けています。このキーパーソンは、必ずしもデジタル人材である必要はありません。彼らと我々でコミッティを形成し、そこで各事業部門の現状と、それに対する打ち手を協議する。また、時には各事業部門内で強力な旗振り役となってもらう。そのようなキーパーソンを事業部門ごとに設定してもらっています。
──これまでのご経験から、組織的に人材育成を進める際のポイントを教えてください。
人材育成は、恐らくどこの会社でもそうだと思うのですが、「総論大賛成! 各論は、……」になりがちです。人を育てることが大事だとわかっていても、やはりみんな現業で精いっぱいで、人を育てるお金と、特に時間がない。よって、事業部門内で現業にプラスして人を育てるとなると、なかなかうまく進みません。実は、自分の部署内ですら、「今こんなに忙しいのにさらに研修をやるんですか?」というような意見が上がる時代もありました。
それを乗り越えるために私がやってきたのは、自分の部署で人材が育っていることを可視化するということです。人材育成に取り組むとき、ファーストステップはここにあると思っています。次にやるべきは、人事部門からの信頼を得ることです。先に可視化した内容を人事にわかりやすく説明し、「たしかにこの部署では社員がしっかり育っていますね」と、信頼を得ていく。そうして人事を巻き込むことで、人材育成を全社共通の課題として取り組むための土台ができます。各事業部門を巻き込むことも大事ですが、人材の採用と配置に関わることなので、まずはやはり人事部門を巻き込むことのほうが重要だと私は思っています。
──人が育っていることを可視化するとは?どのように可視化するのでしょうか。
たとえば、デジタルマーケティング部門のリーダーを務めていたときは、デジタル人材に必要な項目をまず作りました。次にそれぞれの項目について、「1.知識があるが、まだ実行できない」「2.実行できる」「3.人に教えられる」といった3段階くらいのシンプルな指標を作り、一人ひとりの状況を可視化するというアプローチを取っていました。これを半期ごと、1年ごとに振り返ると、それぞれの成長を追うことができます。それまでは目分量で育成や評価をする部分もあったと思いますが、こうして可視化することで、マネージャー陣も誰に何をすればいいのかが明確になり、またやりがいも高まったようです。