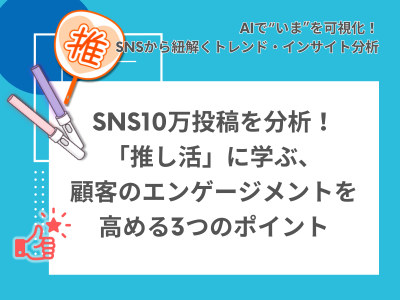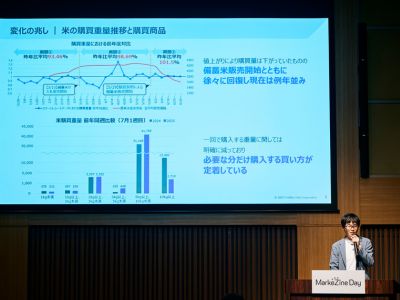売上最小化×利益最大化が、広告運用の大前提
続いて、テクニカルマーケティングの基本概要だが、木下氏はここで重要なポイントとして「売上最大化と利益最大化は違う」と話す。販促費を増やせば獲得件数は増え、売上も増える。しかし、売上が最大の時に、利益が最大であるとは限らない。北の達人の広告運用では「利益最大化」の前提が第一にあり、そのための重要な指標としてCPO(CostPerOrder)がある。
投資の量に比例して収穫量が増加しても、ある限度を超えると次第に収穫量は減っていくという収穫逓減の法則があるが、木下氏によるとCPOはこの法則に当てはまる。「最初の顧客は比較的意欲が高い人を獲得できますが、拡大するとなると徐々に意欲の低い人を取り込むのでCPOが悪化する傾向にあります。これは広告運用の大前提として重要です」と木下氏。つまり、CPOが上限を超えると利益最大化は実現しないため、「利益最大化のためにはCPOの上限をつかんでおくことが大切です。これにより採算が悪化する手前で、投資(=広告出稿)を寸止めすることができます」と説明する。
広告が複数走っている場合、上限CPOを超えた広告を止めることで、売上が減っても、利益(利益率)を上げることができる。木下氏は「実際、これこそが北の達人の強みの源泉になっている」と言い切る。同社は常時約5,000本の広告を運用しているが、自社システムで毎日CPOを管理しており、上限CPOを超えた広告にはフラグを立てて、出稿を止めるようにしているそうだ。なお、出稿をストップしたものはCPOが合うまで何度もチューニングを続けるのだという。
広告運用担当者の評価方法
セミナーでは、広告運用チームの評価方法も明かされた。北の達人の広告運用メンバーは、商品ではなく、媒体を受け持つ。目標は、先述のディレクターの評価方法と同様に、担当媒体の過去半年平均の月間獲得件数の1.2倍で設定。獲得件数と評価ポイントは、以下のように算出している。
広告運用担当者の評価方法
獲得件数のカウント方法 = 上限CPO以内で生まれた獲得件数―上限CPOを超えた獲得件数
評価方法 = 目標達成率×獲得件数
たとえば、上限CPOが1万円の場合、5万円のコストで4件新規を獲得するとCPOは1万2,500円で上限をオーバーする。よって、評価につながる獲得件数はマイナス4件となる。この状態で出稿をストップすればマイナス4件のままだが1万円足してもう2件獲得できたらどうか? CPOは上限の1万円となり、獲得件数はプラス6件でカウントされることになる。マイナス4件からプラス6件へ、運用次第で10件の差が出る可能性があるということだ。この仕組みにより「出稿を止めるべきか、このまま追加するべきかの判断基準が研ぎ澄まされていき、運用センスが磨かれていきます」と木下氏。
それだけでなく、成果を上げたい運用担当者が、自分の担当媒体での成功事例をディレクターやADに共有するなど、クリエイティブチームと密に協力する流れも生まれる。ディレクターやADにおいても、「自分が作成したこのクリエイティブが媒体Aで高い数値を出したから、媒体Bでも運用を強化するといいと思う」などと伝えるようになる。社内の協力体制の強化に、評価制度が一役買っていることがよくわかるだろう。
実際に同社で高い成果を上げているのは、コミュニケーションをしっかりしているメンバーなのだそうだ。木下氏は、「成果が上がっていなければ、コミュニケーションを積極的にとって情報交換をしながら、メンバーと協力し合う。みんなこれが一番自分の成果につながるとわかっています」と話した。