空気という知覚できない要素を、いかに妄想させるか?
田中:前編も含めここまでの話で、よくわかったことがあります。空気は実感をもって知覚しにくいということです。つまり、エアコン製品をブランド間で比較しても、消費者がその違いを明確に知覚することは難しい。だからこそ、ブランド戦略に力を入れなければならないわけですね。
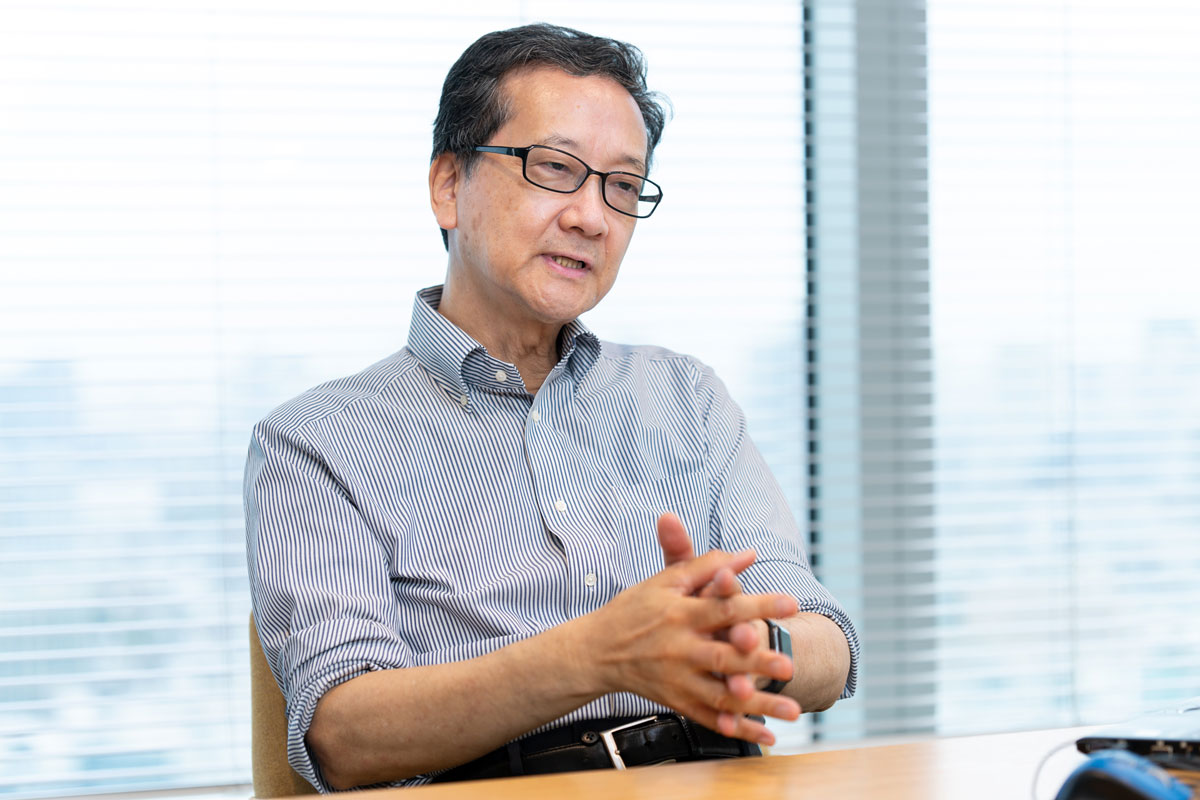
片山:そうですね。実際に製品では、ダイキンの技術開発とモノ作りへのこだわりで、とても良いエアコンをつくり続けているのです。ブランドをカッコよくイメージ表現してブランディング活動をしても、商品の機能が伴っていなければ、本質的ではないですし、売れたとしても長続きしないでしょう。
ただ、他社もすごく頑張っておられて、商品や技術はコモディティ化している部分も多く、ものすごく極端な言い方をすると、日本の皆さんがご存知のメーカーエアコンは基本的にはどれを買っても間違いはありません。ですから、製品の機能の違いを細かく説明するだけでは限界があり、それに加えて「あの白い箱から出てくる空気がダイキンのものは何となく良さそうだ……」と妄想していただく必要があります。ですから、技術開発者が懸命に製品の設計をしているように、我々も必至にブランド作りをするのです。
ブランドイメージは顧客の“妄想”である
田中:片山さんはご著書の中で「ブランドとは、お客様が頭の中で作った妄想」というようにブランドを定義されていました。その定義には私も納得しています。「ブランドというのは、その隣の部屋で人々があなたについて話していることだ」と同じようなことをAmazonの創業者であるジョフ・ベゾスも言っていました。
私がブランドで大事な要素だと思うのは、イマジネーションのほうの“想像”です。想像というのは、「今、ここにはないことを思い浮かべる」という意味です。想像はまさに“妄想”ではないですか(笑)。そういう意味でとても片山さんの主張に共感がありました。

片山:“ブランド”という言葉には、“いいもの”というイメージがありますよね。ブランドの代表と言えばAppleやスターバックスなどの想起が先立ちますし、「ブランドイメージ=ポジティブなブランドイメージ」と変換されます。ややもすると「ブランドは広告で作れるもの」といった誤解すらあります。
ですが、必ずしも良いイメージだけが、ブランドイメージではないですよね。ブランドイメージは顧客が抱くものですから、ポジティブだけでなくネガティブだったり、ニュートラルだったりと、最終的には顧客が勝手に決めるものです。そういったことを伝えたくて「ブランドは、イメージではなく“妄想”」と表現しました。“妄想”とすると、顧客が勝手に決めるものという意味合いをつけることができるからです。このように説明するようになってからは、社内でもブランドに対する理解が少しずつ得られるようになりました。



































