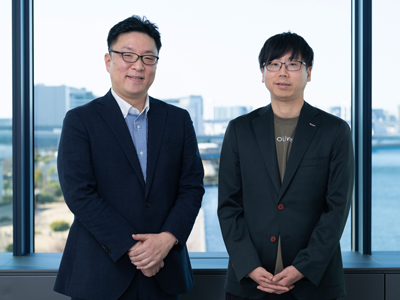若年層へのアプローチを目的に「企業MV」という考え方で制作
――本日はYouTube Works Awards Japan 2023でグランプリおよび、YouTube広告において蓄積された実績がない中で優れたビジネス目標を達成した企業に贈られる「Breakthrough Advertiser部門」の受賞作品でもある「『電気よ、動詞になれ。』ピクセルアート篇」について、読売広告社の高橋さんにお話をうかがいます。

――まずは、高橋さんが今回のプロジェクトの中でどのような役割を担ったのか教えてください。
読売広告社とクライアントである明電舎さまとは、2017年12月に新聞広告で携わらせていただいて以来、お付き合いがあります。今回の「電気よ、動詞になれ。」というフレーズはこれまでテレビCMや新聞広告でも繰り返し使用してきたものですが、このフレーズを使って若年層に対してもコミュニケーションしていこうとトライしたのが今回の施策です。私の役割としては、クリエイティブディレクター、コピーライター、映像プランナーに加え、今回の動画では監督も務めさせていただきました。
――若年層との接点強化を狙った背景について詳しくうかがえますか。
明電舎さまは、これまでテレビCMと新聞広告を中心にコミュニケーションを展開してきました。特に90年代にテレビCMの出稿を強化していた時期の蓄積もあり、ミドル層やシニア層には比較的認知度や企業イメージが保たれています。一方で、若年層においてはこれらのスコアが比較的低い状況にありました。
若年層は将来の取引先でもありますし、採用の文脈でも重要なステークホルダーです。そこで彼らとの将来に向けた関係基盤づくりの第一歩として踏み出したのが今回の施策でした。具体的には、YouTubeをタッチポイントとして活用し、「企業MV」という考え方のもと、まずは明電舎の存在に気づいてもらうことを狙いました。
――企業MVとは聞いたことがないジャンルですが、なぜ企業MVという発想に至ったのでしょうか?
発想の背景には、ブランドというものに対するある“捉え方”がありました。それは、「ブランドとはアーティストのような存在である」というものです。たとえば音楽アーティストが自身の思いや哲学を音楽で表現しているように、ブランドというものも根底にある思いや哲学を商品やサービスというかたちで表現していると捉えられないでしょうか。
そう考えたときに、ブランドが自分自身の感情をコンテンツとして表現していくようなコミュニケーションができないか、それによってアーティストとファンのような“共鳴関係”を生み出すことができないか。そんなふうに考えていました。
MVフォーマットの広告は数多くありますが、MVを見ているときの没入感そのものを企画の中心に据えた広告にはあまり触れたことがありませんでした。もしそれをやりきれたら、コミュニケーションの“感触”として、少し新しいものになるのではないかと考え制作にトライしました。
「知らせる広告」ではなく「知ろうとしてもらえる広告」を
――「企業MV」という提案をしたとき、議論になったポイントはどんなところでしたか?
通常の広告であれば自社の優位点をアピールする内容になると思いますが、優位点を押し出すのではなく、企業としての思いだけでやりきることが重要だという点はしっかり議論しました。
この企画のそもそもの目的は、若年層との接点をつくり、将来にわたる関係を築いていくこと。そう考えたときに「知らせる広告」ではなく、「知ろうとしてもらう広告」であることが重要であるというお話をしました。「認知」は伝えてしまえばそれで終わりですが、「動機づけ」は今後のコミュニケーションにも継続的に作用する効果だからです。こうした効果を生み出すために、当初のコンセプトをぶらさずやりきることになりました。
――企業MVを展開する先として、YouTubeだけでなく各種SNSも検討・利用されたとうかがいました。どのようなメディアプランを組まれたのでしょうか。
オリエンをいただいた当初は、メディアについてはゼロベースで検討しました。動画広告という手法も決まってはおらず、当初はInstagramアカウントの運用なども検討していました。
ただ、企業MVというアイデアが出てきてからは、自ずとメディアプランも決まっていきました。X(当時のTwitter)は拡散性が魅力ですが、ミュートにして視聴されているケースも多く想定されるので、音楽を主としたコンテンツ展開の主軸に置くことは少し難しいと感じました。一方で、YouTubeはこの媒体自体が「MVを見るプラットフォーム」であるため、企画との親和性が高いことが大きなポイントでした。
具体的なメニューとしてはスキップ可能なTrueViewインストリーム広告を選択。「スキップできるのにしない」という状況をつくりだすことで、受け手の主体的な視聴態度を引き出し、強制視聴よりも強く印象に残していくことができるのではと考えました。
また、ピクセルアートというビジュアルとの親和性を考え、Instagramの動画広告もトライアルとして併用しました。こちらはショート版を配信し、LPへ誘引する設計でした。実施してみると、YouTubeのほうが広告効率としては良かったので、途中から予算をそちらに集約させていきました。