サステナビリティをトレードオフの議論にしない
木村:最後は、「サステナビリティ」に関する活動についてです。このテーマに関する答えは一つに限られるものではなく、様々な考えを踏まえて、各社で最適解を探っていくべきものだと考えています。ユニリーバもカンパニーとしてサステナビリティを掲げていましたが、スターバックスもこの領域のリーディングカンパニーです。ちなみに、ユニリーバは、「パーパスブランディングは、利益を上げるための経営手法である」と明言していました。スターバックスにおけるサステナビリティは、どういったものですか?

ユニリーバ・ジャパンに2009年に入社。約14年間、ラックスやダヴなどのブランドマーケティングを経験。国内を中心とした360度のプロモーションからグローバルのブランド戦略や製品開発まで、幅広く従事。ロンドン本社にて、ダヴヘアのグローバル全体のブランド戦略をリード。その後、ユニリーバ・ジャパンでのスキンケアカテゴリー統括とグループ子会社のラフラ・ジャパンの代表取締役を兼任し、PMI後のV字回復を達成。2021年より株式会社Brandismを創業し現職。BtoBからBtoCまで、国内外の多様なクライアントのブランド戦略立案や経営戦略を支援。著書『ブランド・パワー ブランド力を数値化する「マーケティングの新指標」』が2023年12月に刊行
森井:考え方はユニリーバもスターバックスも大きくは違わないように思います。前提として、スターバックスは「パートナー、お客様、コミュニティ(地域)、ビジネスの全てにおいてメイクセンスできるか」を常に考えてあらゆる企画をしています。サステナビリティは、これらすべてと同列に、絶対に欠かせないものです。
いくらお客様やパートナーが喜んでくれても、ビジネスが順調でも、環境にマイナスだったら、社会にとって良いものにならないでしょう。スターバックスにおけるサステナビリティは、それ以上でもそれ以下でもありません。
木村:経営戦略における位置づけはいかがでしょうか?
森井:サステナビリティは事業の真ん中に置くべきだと考えています。つまり、経営において何かとトレードオフにすることなく、スターバックスとして果たすべき責任を純粋に果たすということです。
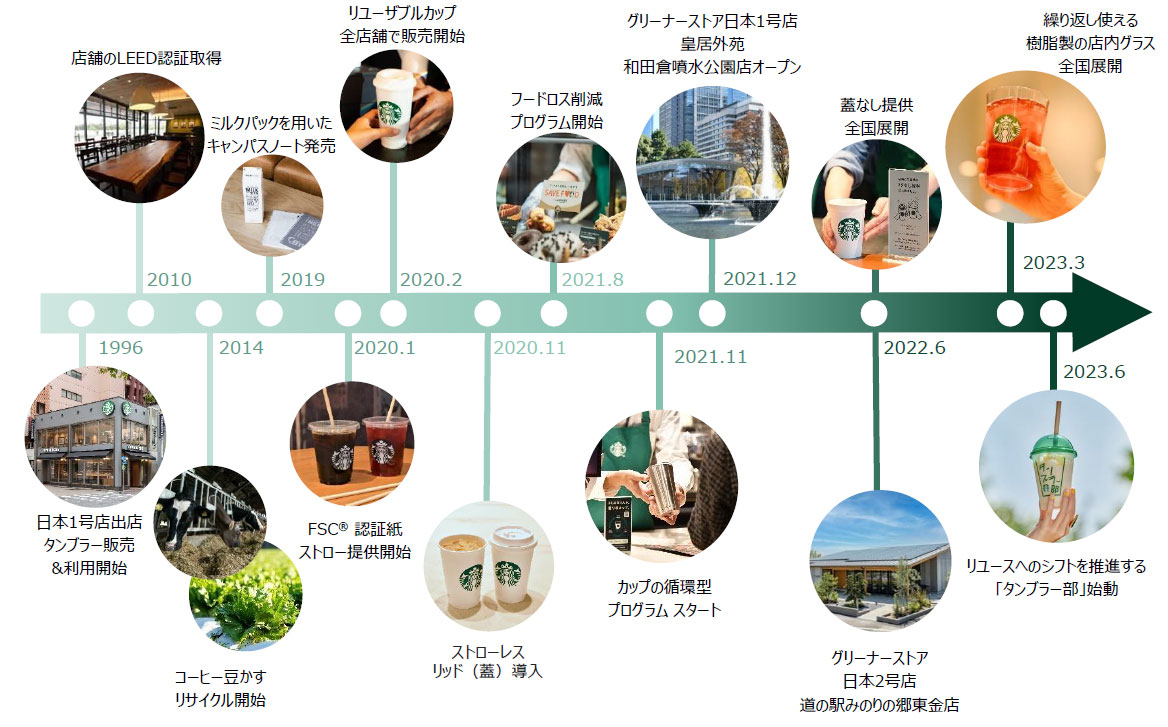
木村:それは金言ですね。サステナビリティをトレードオフの議論にしない。
森井:サステナビリティを事業活動の真ん中に据えた上で、良い商品を企画し、価格に見合う価値を提供して、ビジネスとして成立させることで循環をしっかり回す。それができて初めて、人にも環境にも投資ができるわけで、この循環を回すことは経営の責務であると考えます。
当然、サステナビリティ活動にはコストがかかります。サステナビリティを単体で見て、売上や利益とのトレードオフの議論にしてしまうと、事業活動の端っこに置かれることになってしまい、取り組みが終わってしまうことが多くなります。
木村:サステナビリティに関する活動は、ブランディングにも繋がってきますか?
森井:現時点では、購買行動のデシジョンにサステナビリティの観点が入ることは少ないと思います。だからこそ、その間口をいかに広げられるか? というのは、マーケティングに委ねられるところです。
特に我々のような小売の場合、最終的にはお客様にも共感していただき一緒に取り組んでいただけないと、環境へのアクションは前進しません。やはり、エネルギー負荷が一番大きくなるのは、お客様との接点(店舗)だからです。ただ、店舗でお客様に対して「環境のためにこうして下さい」と言っても広く共感を得るのは難しいので、「おいしい! 楽しい! 気づいたら環境にも良い!」というように楽しく働きかけることを意識しています。
木村:先にうかがった「タンブラー部」の話も、「おいしい、楽しい、気づいたら環境にもよい」が揃っていますね。
今日はスターバックスのブランドマーケティングはもちろん、森井さん視点のブランディングやマーケティングに対する考え方についてお聞きし、久しぶりに背筋が伸びました。お忙しいところ本当にありがとうございました!



































