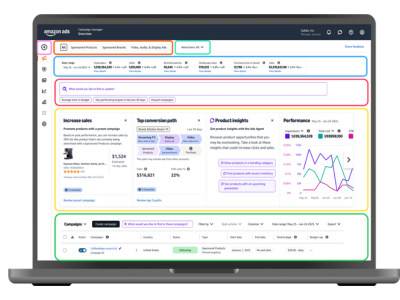会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
新規会員登録無料のご案内
- ・全ての過去記事が閲覧できます
※プレミアム記事(有料)は除く - ・会員限定メルマガを受信できます
- ・翔泳社の本が買える!500円分のポイントをプレゼント
この記事は参考になりましたか?
- 広告/マーケティングにおける7つの転換点~『2030年の広告ビジネス』番外編連載記事一覧
- この記事の著者
-

横山 隆治(ヨコヤマ リュウジ)
横山隆治事務所 代表取締役
ベストインクラスプロデューサーズ 取締役 ファウンダー
トレンダーズ 社外取締役1982年青山学院大学文学部英米文学科卒業。同年、旭通信社(現・アサツー ディ・ケイ/略称:ADK)に入社。インターネット広告がまだ体系化されていなかった1996年に、日本国内でメディアレップ事業を行う専門...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア