初心者が押さえるべき、マーケティング活動の全体像
MarkeZine編集部 吉永(以下、MZ):第20回では、マーケティングにおける「地図」として、ストラテジーマップを解説していただきました。この1枚に、初心者が知るべきマーケティング活動が収まっているのですね。

西口:はい。(1)の「WHOとWHATの組み合わせ」が、この地図を手に進んでいくための「コンパス」になります。この定義から始まって、ストラテジーマップに示す(6)までのプロセスを継続的に行っていくのが、基本的なマーケティング活動です。
(1)価値を定義 WHOとWHAT(顧客戦略)
(2)WHO(潜在顧客)へ接触し、WHAT(便益と独自性)を提案
(3)新規(初回購入)
(4)価値の再評価(実際の使用体験)から継続購入(頻度・単価の向上)もしくは離反
(5)離反の復帰
(6)ブランディング(価値を記号化・強い記憶に)
MZ:ストラテジーマップの(1)に複数の顧客が描かれているのは、ここまでの回で解説いただいたように、それぞれ違う価値が成立しているということですね。
西口:その通りです。ファミレスならお子様連れや学生グループ、高齢の方々、お一人様のビジネス利用など、色々な顧客層が異なる価値を感じて利用している、といった話をしましたね。1種類のWHOとWHATの組み合わせしか成り立たないプロダクトはほぼありません。

西口:逆に、ストラテジーマップでは便宜上、(1)で示した3種類の顧客層を(2)では同時並行で見つけているように描いていますが、実際にはWHOとWHATの組み合わせは段階的に増えていくことが多いです。最初に成立するWHOとWHATが見つかって、その方の初回購入が実現し、同じWHOとWHATの組み合わせが増えていく過程で、新しいWHOとWHATの組み合わせが生まれるのです。
ストラテジーマップを元に顧客の「数・単価・頻度」を上げる
MZ:(3)の新規獲得まではシンプルでわかりやすいのですが、(4)からは分岐が多くなっています。最初の体験に満足して継続購入に進む人もいれば、いいなと思いながら忘れてしまって買わなくなる「忘却離反」をする人、プロダクトに不満があって離反する人もいますね。

西口:(4)は複雑に見えますが、どんなビジネスにとっても非常に重要な分岐点です。初回購入を経て、最初にプロダクトを体験して満足した顧客は、その後も継続的に購入いただけます。しかし満足しなければ離反しますし、満足していてもなんとなく忘れてしまい離反する方も出てくるのです。この分岐で離反せず、継続購入につながって、購入単価や購入頻度も上がるのが理想です。
(6)のブランディングは全体に有効ですが、特にこの「忘れないように強く記憶してもらう」部分に効果的なのは、連載のブランディングパートで解説した通りです。
MZ:それでも離反してしまった方々には、(5)の離反から復帰していただけるアプローチをするわけですね。

西口:プロダクトに不満があって離反した顧客に対しては、どんな便益や独自性を提案すれば復帰していただけそうなのかN1インタビューなどを通して突き止め、それを解消して再度アプローチすることが必要になります。
一方で、離反の理由として、そもそも提案している便益や独自性に顧客が気づいていない場合もあります。なんとなく購入して、なんとなく使用体験して、大きな不満はないけれどなんとなく再購入していない、といったパターンです。このような顧客には便益と独自性をしっかりお伝えすることで、あっさり復帰いただけることもあります。







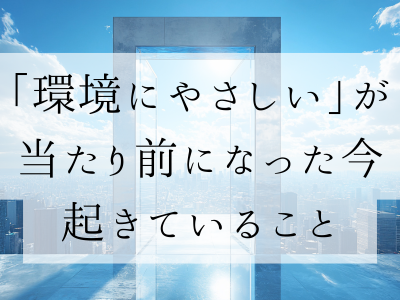




























.jpg)
