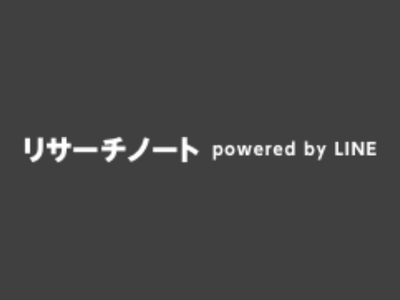BtoBマーケティングとは
BtoBマーケティングは「Business to Business」の略で、企業間の取引におけるマーケティング活動を意味します。クライアントとなる企業が抱える業務上の課題解決や業務効率化を支援するための商品・サービスの提供です。
クライアントが企業になるため、契約に至るまで多くの人が関わります。商品・サービスの機能のほかに提供する企業の信頼性や取引上のリスクなどを検討するため、提案から契約までに時間が必要です。
BtoBマーケティングにおける営業手法には「営業単独型」と「分業型」の2つがあります。
- 営業単独型:従来の営業手法。営業担当者がテレアポでクライアントとの接点を作り、関係を構築して商談につなげる。
- 分業型:営業だけでなくマーケティング担当者と協力する営業手法。マーケティング担当者がリード(見込み顧客)を獲得・育成し、受注確度が高いクライアントに対して営業がアプローチを行う。
またデジタル化に伴い、クライアントが契約に至るまでの行動データの取得が可能になりました。データを基にしたマーケティング戦略の立案や受注確度の高いクライアントへの営業活動に集中でき、効率化を図れます。

BtoCマーケティングとの違い
BtoCマーケティングとBtoBマーケティングでは、いくつか違いがあります。特に理解しておくべき違いは「購買目的」「意思決定者の数」「購買するまでの期間」の3つです。

プレゼンテーションをとおして商品・サービスの特徴や優位性、他社での導入実績を基にした信頼性や商品・サービス導入後の費用対効果をアピールして有用性を示さなければなりません。提案の際には、商品・サービスを購入することで得られるベネフィットをロジカルに伝え、納得してもらうように意識しましょう。
BtoBマーケティングのプロセス
BtoBマーケティングのプロセスは、大きく以下の5つに分けられます。
- リード獲得(リードジェネレーション)
- リード育成(リードナーチャリング)
- リード発掘(リードクオリフィケーション)
- 商談・受注
- 継続利用
それぞれについて、詳しく説明します。
リード獲得(リードジェネレーション)
1つ目に「リード獲得(リードジェネレーション)」です。リード獲得は、自社の商品・サービスに興味関心を持ちクライアントとなる可能性がある「見込み客」を作り出すことです。クライアントとの接点を持つきっかけになります。
リードを獲得するための手法はさまざまです。オンラインでは、Web広告やメルマガ、コンテンツマーケティング、ウェビナーなどがあります。オフラインでは、テレビCMや交通広告、展示会、セミナーなどの手法が用いられます。
リード育成(リードナーチャリング)
2つ目に「リード育成(リードナーチャリング)」です。獲得したリードの中には、自社の商品・サービスをすぐに購入してくれそうな「今すぐ客(ホットリード)」と「そのうち客(コールドリード)」が混在します。リード育成とは「そのうち客(コールドリード)」を「今すぐ客(ホットリード)」に育成することです。
獲得したリードの中に混在する「今すぐ客」の比率は16%と言われています。「そのうち客」のフォローアップを行い関係性を構築しながら「今すぐ客」へ転換させて商品・サービスに対する購買意欲を引き上げることが重要です。
たとえば、Web広告やウェビナーの実施により自社の商品・サービスの認知を拡大したもののフォローアップしなければ「そのうち客」は「今すぐ客」へ転換せず、他社の類似商材を購入する可能性もあります。これでは事業投資に見合った費用対効果が得られません。
クライアントのニーズや課題を把握し、定期的に接点を持てるようにコミュニケーション戦略を練りましょう。

リード発掘(リードクオリフィケーション)
3つ目は「リード発掘(リードクオリフィケーション)」で、商談や受注の前に行う最後のプロセスです。獲得・育成したリードの中から、商談や受注確度の高い「今すぐ客」を絞り込み抽出してリスト化します。
リード発掘で育成した「今すぐ客」に対して、属性や興味関心・購買行動に応じてスコアをつけてリードの購買意欲を可視化する「スコアリング」という手法を用います。
商談・受注確度の高い「今すぐ客」のリストを営業部門に提供することで、営業担当者は確度の高いリードへの営業活動を効率的に行えるでしょう。
商談・受注
4つ目に「商談・受注」です。リード発掘で抽出した商談・受注の確度が高い「今すぐ客」に対して、営業部門がアプローチを行い、商談から受注につなげます。
商談の際にはリードの獲得から育成までに、リードが起こした行動を把握しておきましょう。過去にセミナーへの参加や資料請求をしたことがあるのか、商品・サービスに興味を持ったのはいつごろからかなどを把握し、営業トークに活かすことで受注率の引き上げが期待できます。
継続利用
5つ目に「継続利用」です。サブスクリプションやSaaSのような商品・サービスを提供している場合には、新規の獲得に加えて既存クライアントに商品・サービスの利用を継続してもらうことが重要です。
たとえば、商品・サービスの「解約率」を低く維持することをKPIとします。「解約率」を低く保つためにカスタマーサクセス部門を設けるのが一般的です。カスタマーサクセス部門は、クライアントの悩みや不明点に回答するといった支援を行います。また、商品・サービスを最大限に活用して、収益増加や業務効率改善などのビジネス成功を実現できるように支援する役割を持ちます。

BtoBマーケティングの3ステップ
BtoBマーケティングに取り組むためのステップは大きく3つあります。
- 市場環境の調査・分析
- マーケティング戦略の立案
- マーケティング戦略の実行
それぞれのステップで、どのようなことを行うか詳しく紹介します。
1.市場環境の調査・分析
ステップ1は「市場環境の調査・分析」です。このステップでは、市場・顧客の理解はもちろん、自社の状況把握や競合他社の取り組みも調査します。
市場・顧客を理解する
マーケティング活動を進めるうえで、自社の商品・サービスが参入する市場の規模や特徴を把握しましょう。
また競合他社の商品・サービスもある市場の中で、自社の商品・サービスを購入する顧客はどのような課題を抱えているのか、課題に対してどのような情報を集めているか、商品・サービスの購入までの意思決定のフローなどを理解することで、マーケティング戦略を練りやすくなるでしょう。
自社を理解する
BtoBマーケティングに取り組むためには、自社の状況を理解することも必要です。既存の商品・サービスの顧客データや過去に実施したマーケティング施策の分析、短期で取り組める改善点の洗い出し、商品・サービスの営業方針と体制を把握しましょう。
競合を理解する
競合他社の状況を把握することも重要です。マーケティング戦略を実施する中で、クライアントは自社を含めた複数の商品・サービスを比較検討することもあります。
競合他社の商品・サービスの特徴や、訴求内容、利用している顧客はどのような企業か調査し把握しましょう。
2.マーケティング戦略の立案
ステップ2は「マーケティング戦略の立案」です。このステップでは、商品・サービスを「誰に」「どんな価値を」「どんな方法で」届けるのかを明確にしてマーケティング戦略を立案します。
「誰に」「どんな価値を」「どんな方法で」の整理を間違えると、ターゲットにマーケティングメッセージが届きません。しっかりと整理して適切なマーケティング戦略を練りましょう。
Who(誰に)
まずは誰に向けて商品・サービスをアプローチするのか整理します。「市場」には、さまざまな課題やニーズを抱えたクライアントが存在します。マーケティング活動を進めるうえで、注力するクライアントはどのような課題やニーズを抱えているのかを整理して、ユーザー像を明確にしましょう。
ユーザー像を明確にせずマーケティング活動に取り組むと、受注確度の低いターゲットにもアプローチを行うことになり、費用対効果が悪化する可能性があります。しっかりとターゲットとなるクライアントが抱えている課題やニーズを整理しましょう。
What(どんな価値を)
次に、商品・サービスを通じて提供する価値は何か、強みや特徴はどのようなものがあるのかを整理して言語化します。
自社の商品・サービスの価値や強み、特徴を言語化するためには「ポジショニングマップ」と「バリュープロポジション」を活用します。
- ポジショニングマップ:市場における自社の商品・サービスと競合他社の商品・サービスを比較した際の優位性や差別化ポイントを可視化した図
- バリュープロポジション:自社の商品・サービスが提供でき、競合他社の商品・サービスでは提供できない、独自の価値
ポジショニングマップを活用するとマーケティング戦略を練りやすくなります。バリュープロポジションが明確になると、訴求ポイントの整理やマーケティングメッセージが作りやすくなります。
営業担当者が商品・サービスについて説明する際にも役立つでしょう。
How(どんな方法で)
最後にどんな方法で情報を提供するか決定しましょう。クライアントへのアプローチに活用するチャネルを整理して、コミュニケーション設計を行います。
クライアントが商品・サービスを認知してから購入・申込に至るまでの購買動線を可視化するためには、カスタマージャーニーマップを用いることです。商品・サービスの認知から購入・申込までの各フェーズにおけるクライアントの行動や態度変容を捉えてマッピングを行うことで、クライアント視点に立った施策立案やコンテンツ設計ができます。
各フェーズごとに、クライアントの検討度合いは異なります。クライアントとの関係性を構築するうえでも最適なコミュニケーションを取れるように設計を行いましょう。手間がかかる工程ですが、上手く機能すると関係性を構築した状態で営業担当者が商談に望めるので、効率よく商談・受注の件数を延ばせるでしょう。
3.マーケティング戦略の実行
ステップ3は「マーケティング戦略の実行」です。ステップ1・2で整理して設計したマーケティング戦略を実行します。マーケティング戦略に応じて実施する施策の優先順位は変わりますが、一般的には以下のとおりです。
- LP(ランディングページ)の改善
- 商品・サービスの認知拡大
- フィールドセールスの効率改善
- 営業の受注率引き上げ
- クライアントの満足度向上
受注確度の高いクライアントを商談につなげるためには、CV(コンバージョン)ポイントになるLPの内容がわかりやすいか、申込動線や操作性に問題がないかを確認しましょう。LPに何らかの問題がある場合、広告でアプローチを行ってLPへ誘導しても、すぐに離脱してしまい機会損失を引き起こします。
まずはLPに問題がないかを確認して、CVR(コンバージョン率)を上げてリードの獲得を図りましょう。
BtoBマーケティングで成果を出すために必要な知識
BtoBマーケティングで成果を出すためには、クライアントとのコミュニケーションのほかにも重要なポイントがあります。BtoBマーケティングに取り組む際は、以下の3つのポイントを覚えておくとよいでしょう。
- 顧客ニーズの理解を深める
- 営業やマーケティングなど部門間の連携をする
- ツール導入や施策実行の目的を明確にする
それぞれについて、詳しく紹介します。
1. 顧客ニーズの理解を深める
まずは「顧客ニーズの理解を深める」ことです。クライアントがどのような悩みを解決したいのか、課題を解決したあとはどのような状態になっていたいのかなど、ニーズを深く理解する必要があります。
また獲得したリードの中には、さまざまな業種や職種・役職の属性が含まれています。一般社員と役職者では、日々対応している業務や立場、抱えている課題も異なるでしょう。業種や職種・役職により抱えている課題やニーズが異なることを意識せずにコミュニケーション設計を行うと、適切なコミュニケーションが図れず、機会損失を招いてしまう恐れがあるので、注意してください。
2. 営業やマーケティングなど部門間の連携をする
BtoBマーケティングでは、リードの獲得から商談や受注・継続利用に至るまでのクライアントとの関係性構築が重要です。リードの獲得から商談や受注・継続利用までのフローは、一般的な企業では営業・マーケティング・カスタマーサクセスなど、部門をまたいでしまうため情報共有や連携が十分に行われていないことがあります。
情報共有や連携が不足していると、無駄な工数が掛かってしまっている可能性があります。たとえば、獲得したリードが受注につながったのかを営業部門からマーケティング部門へ共有していない場合、マーケティング担当者は「受注確度の高いリード」と「受注確度の低いリード」の特徴を捉えられないため、効率的な営業活動につなげられません。またカスタマーサクセス部門から商品・サービスの継続率が低いクライアントの特徴が営業部門に共有されなければ、LTV(顧客生涯価値)の低いクライアントへの営業活動が多くなってしまう可能性もあります。
部門間で情報共有や連携をしっかりと行い、効率的にマーケティング活動を進めましょう。
3. ツール導入や施策実行の目的を明確にする
BtoBマーケティングを取り組むうえで注意すべき点が大きく2つあります。
- ツール導入の目的を明確にする
- 施策実行の目的を明確にする
まずツール導入です。MAツールは大量のリードの管理やクライアントのスコアリング、メルマガ配信などを自動化できる便利なツールです。しかし、BtoBマーケティングにおいて必ずしもMAツールが必要ということはありません。BtoBマーケティングは、BtoCマーケティングに比べてリード数が少ない傾向があります。たとえば月間の平均獲得リード数が10件の場合、MAツールの導入費やランニングコストを考えると費用対効果が合わないことが考えられます。
次に施策実行について、BtoBマーケティングではクライアントとの関係性構築が重要になるため、インサイドセールスに力を入れる企業も多いです。インサイドセールスにはクライアントとコミュニケーションを図り、抱えている課題やニーズのヒアリング、受注確度を高めるための育成を行う役割があります。しかし獲得しているリードの質がよく、受注確度が高ければフィールドセールスに渡すことでインサイドセールスの工数を掛けずに商談につなげることができます。
ツールの導入や、施策の実行を進める際には、自社の状況や課題を見直して実施する目的を明確にして取り組みましょう。

BtoBマーケティングの手法14選
BtoBマーケティングで実施される代表的な手法を紹介します。オンラインとオフラインあわせて14個あります。

それぞれについて、詳しく紹介します。
オンライン施策9選
まずはオンライン施策を紹介します。デジタル化が推進される中で、BtoBマーケティングにおいてもオンラインでの接点を設ける企業が増えてきました。ここでは代表的な施策9つを紹介します。自社の商品・サービスのマーケティング戦略に取り入れやすそうなものがあれば、実施してみましょう。
1.Webサイト/ランディングページの政策・改善
オンライン施策を行ううえで重要な役割を果たす、Webサイトやランディングページの制作・改善を図りましょう。
Webサイトやランディングページは、集客したユーザーに対して、自社の商品・サービスの特徴や導入することで得られるメリットを示し、資料請求や問い合わせなどの行動へ誘導するためのページです。上手くユーザーを集客できてもWebサイトやランディングページの内容がわかりづらかったり、導線設計が上手くできていない場合には成果につながらず離脱してしまうでしょう。
ユーザー視点に立ってWebサイトやランディングページの内容、導線設計を見直し、商品・サービスの魅力が伝わりやすくなるように改善しCVR(コンバージョン率)を向上させることで効率的なリード獲得につながります。
2.Web広告
Web広告とは、Web上のメディアやSNS・アプリ内に掲載される広告の総称です。Web広告の種類は多岐にわたり、そのなかでも代表的なのは以下になります。
- リスティング広告:GoogleやYahoo!などの検索エンジンで、検索したキーワードに対して関連する広告が掲載される
- ディスプレイ広告:バナーや動画を活用した広告。潜在層~顕在層まで視覚的にアプローチができる
- SNS広告:X(旧Twitter)やFacebook・InstagramなどのSNS上に掲載される広告。プラットフォームによっては、リポスト機能があるので拡散性に優れている
- アフィリエイト広告:商品購入や申込など、広告主が定めた成果条件を満たしたときに広告費が発生する。顕在層へのアプローチに向いている
Web広告はターゲットとなるユーザーの興味関心や年齢層・居住エリアなど、さまざまなターゲティング設定ができるため、無駄なコストを抑えられます。
広告配信のターゲティング設定を絞り込み過ぎると、配信対象となるユーザーの母数が少なくなり十分なアプローチができなくなるので注意しましょう。
3.SEO対策
SEOとは「Search Engine Optimization」の略称で「検索エンジン最適化」を意味します。自社が運営するWebサイトやランディングページに訪問するユーザーを増やすための施策です。
検索エンジンでユーザーが検索行動を起こした際に、自社のWebサイトやランディングページが検索結果の上位に表示されるためには「このWebサイト(ランディングページ)は、ユーザーが求める情報や役立つ情報を掲載している」と検索エンジンに評価してもらわなくてはなりません。
検索エンジンからの評価を上げるために、検索したキーワードに合ったコンテンツを掲載し自社の商品・サービスに関連するキーワードを検索したユーザーに有益な情報を届けられるようにしましょう。

4.SNSマーケティング
日常的に使用するSNSも、マーケティング施策として活用できます。主にX(旧Twitter)やFacebook・Instagramなどのプラットフォームの利用です。各SNSで企業のアカウントを作成してユーザーに向けて自社の商品・サービスの情報を発信します。
各サービスの特徴は下記のとおりです。

SNSマーケティングは、ユーザーとコミュニケーションを取り関係性の構築を図ることもできます。自社の商品・サービスのターゲット層が頻繁に利用しているであろうプラットフォームは積極的に活用してみましょう。
5.プレスリリース
プレスリリースとは、自社の取り組みを報道機関に情報提供し、新聞や雑誌・Webメディアに記事を掲載して告知や発表を行うマーケティング施策です。
メディアの担当者は「先進的な取り組みについての情報」や「公共性のある情報」に関心を持つ傾向があります。その特徴を理解して、自社で独自調査したデータの発表や新商品・サービスのリリースの際に活用しましょう。プレスリリースは多くのメディアが取り上げるので、認知の拡大が期待できるでしょう。
6.メールマーケティング
メールマーケティングは、獲得したリードや既存クライアントに対して自社商品・サービスに関する役立つ情報や最新情報を配信してコミュニケーションを図る施策です。メールマーケティングは「メルマガ」「ステップメール」「営業メール」の3つに分けられます。それぞれの特徴は以下のとおりです。

「メルマガ」「ステップメール」「営業メール」それぞれの特徴を理解して、効果的に活用しましょう。
7.マーケティングオートメーション(MA)
マーケティングオートメーション(MA)ツールを導入することで、獲得したリードの管理工数が削減されます。またリードの商談化率や受注見込みなどをスコアリングして可視化できます。
商談化率や受注見込みを可視化できることで、最適なマーケティング戦略を練ることが可能です。また、受注確度の高いクライアントの情報を営業担当者に共有でき、効率的なアプローチを行えるようになるでしょう。
8.ホワイトペーパー
ホワイトペーパーとは、自社の商品・サービスについて役立つ情報や独自に調査したデータ、専門的な知識などをまとめた資料や冊子などのコンテンツを指します。しくみとしてはWebサイトやランディングページ上に資料請求フォームを設置し、ユーザーに企業名や電話番・メールアドレスなど必要な情報を入力してもらい資料を提供するものです。
ホワイトペーパーを求めるユーザーは、自社の商品・サービスが携わる分野に対して何かしらの課題や興味関心を持って情報収集をしている可能性があり、商談・受注確度の高いリードと言えます。そのため、ホワイトペーパーから獲得したリードは関係性構築がしやすい傾向があります。
9.ウェビナー
ウェビナーは、Web上で行うセミナーのことで、「Web」と「セミナー」を組み合わせた用語です。自社の商品・サービスの役立つ情報やノウハウをセミナーを通してユーザーに提供できる施策で、セミナーに参加するユーザーはすでに商品・サービスに興味関心を持っており、より理解を深められます。
ウェビナーへ参加するためにユーザーは、企業名や電話番号・メールアドレス・参加者の役職などの個人情報を入力する必要があるので、リードの獲得にも適しています。
ウェビナーのメリットは、ユーザーと直接コミュニケーションを図れることです。ユーザーが自社の商品・サービスに対する不明点や質問に回答でき、関係性の構築につながります。ウェビナーは、コストを抑えてリードを獲得できる施策なので、ぜひ実施してみましょう。

オフラインの施策5選
オフライン施策は5つあります。オフライン施策は、リード獲得やリード育成を目的に実施されるケースが多いです。
実施する施策によってはオンライン施策に比べると、アプローチできるユーザーの母数が限られてしまいますが、オンライン施策では体感できない価値の提供ができるメリットがあります。
1.展示会の出展
展示会の出展は、新規のリード獲得に向いている施策です。ただし、展示会で獲得できる新規のリードは潜在層のクライアントが多いため、商談化率は低い傾向があります。
展示会のメリットは、多数のクライアントと直接コミュニケーションが取れることや、短い期間で数百~数千件の新規のリードを獲得できることにあります。しかし、出展にはコストが掛かります。多いときには1,000万円程度かかることもあるでしょう。コストをかけたが商談につながらなかった、ということがないようアフターフォローを忘れないように注意してください。
2.マス広告
マス広告はテレビCMやラジオ、新聞・雑誌に自社の商品・サービスの広告を掲載して、認知の拡大を図るマーケティング施策です。Web広告とあわせて実施することで、より効果を高める見込みがあるので、Web広告を実施する際にはマス広告の掲載も検討しましょう。
認知の拡大に向いているマス広告ですが、アプローチできるターゲット層が広い分、実施するためにかかるコストも高額になることが多い傾向にあります。市場における自社の商品・サービスのシェアを確立させたいときに実施するとよいでしょう。

3.交通広告
交通広告は、電車やタクシーの中で掲載される広告です。日常的に電車やタクシー・バスを利用する人は多いため、広告との接触機会が多く認知拡大に有効な施策です。
交通広告は、公共交通機関に掲載されるため信頼性が強いという特徴があります。またタクシー広告は利用者層や走行エリアが限定的なため、ターゲットにあった広告を掲載できると費用対効果も高くなるでしょう。
4.ダイレクトメール
ダイレクトメールは、新規クライアントや既存クライアントの育成を目的として実施される施策です。自社の商品・サービスの紹介やセミナーの案内を送付するものです。
BtoBマーケティングの商材は高額なものが多く、クライアントも購入や申込を躊躇してしまったり、社内の意思決定者が多くなかなか承認が取れなかったりするということがあります。そういったときに、トライアルや割引き価格を提示したダイレクトメールを送ることで、取り組みへの検討が進み商談化しやすくなるでしょう。
5.テレマーケティング
テレマーケティングは非効率と言われることありますが、それは課題が顕在化していない潜在層に向けて営業活動を行っており商談化率が低いためと言えます。
抱えている課題やニーズは顕在化しているが、積極的に情報収集を行っていない企業もあります。テレマーケティングでは、架電によりユーザーと直接コミュニケーションが取れるので、一方的な商品・サービスの紹介ではなく課題やニーズをヒアリングし、相手の反応にあわせて提案を行いましょう。

BtoBマーケティングで覚えておくべき用語5つ
BtoBマーケティングに取り組むうえで、覚えておくべき用語が5つあります。それぞれにどのような意味があるのか覚えておくようにしましょう。
- ペルソナ
- カスタマージャーニー
- CV(コンバージョン)
- CVR(コンバージョン率)
- LTV(ライフタイムバリュー)
各用語について、紹介します。
1.ペルソナ
ペルソナとは、自社の商品・サービスを使用するユーザー像を具体的に言語化することです。似ている用語に「ターゲット」もありますが、より具体的なユーザー像を表すのが「ペルソナ」になります。
ペルソナ像を解像度高く明確に言語化できると、マーケティング戦略やコミュニケーション設計を図る際に「誰」に「どんな広告」で「どんなメッセージ」を「どの媒体」で「何を見ているとき」に届けるのか整理できます。
- ペルソナ:性別や年齢、職業、趣味嗜好のほかに家族構成やよく使用する媒体、どのような業務に従事していてどのような課題を抱えているか明確に言語化する
- ターゲット:性別、年齢、職業や趣味嗜好を洗い出す
マーケティング戦略を練る前に、まずは自社の商品・サービスを使用する企業がどのような課題を抱えているのか仮説を立てましょう。
2.カスタマージャーニー
カスタマージャーニーとは、クライアントが自社の商品・サービスを認知してから購入や申込に至るまでの道筋を可視化したものです。フェーズごとにクライアントの行動を整理して、自社の商品・サービスのアプローチ方法を検討できます。
一例になりますが、カスタマージャーニーは以下の5つのフェーズに分けられます。
- 認知:課題の解決方法を探している
- 理解:課題の解決事例を知る
- 検討:課題解決に役立つ商品・サービスの導入を検討する
- 商談:問い合わせをする/企業からの営業メールを受けて商談する
- 購入:実際に商品・サービスを導入する
カスタマージャーニーがあることでフェーズごとにクライアントの行動や自社の目的が明確になり、どのようなタッチポイントでどのようなコンテンツを提供するかの戦略立案が可能です。
3.CV(コンバージョン)
CV(コンバージョン)は、クライアントが自社の商品・サービスの購入や申込などをして成果につながったことを指します。
商品・サービスにより何をCVにするかは変わります。以下の行動は、いずれもCVです。
- 商品の購入
- サービスへの申込
- 商品・サービスの資料請求
- セミナーやウェビナーへの参加申込
- Webサイトからの問い合わせ
CVはマーケティング活動を行ううえで非常に重要な指標になります。どのような行動をCVとするかしっかりと検討して決めましょう。
4.CVR(コンバージョン率)
CVR(コンバージョン率)は「Conversion Rate」の略語で、Webサイトやランディングページへ来訪したユーザーがどのくらいの割合でCVに至ったかを計測する指標です。
たとえば、セミナーやウェビナーへの参加申込をCVと設定してマーケティング施策を実行した場合、以下の式で算出できます。
CVR(%)=セミナー/ウェビナー申込数(CV) ÷ セッション数(サイト訪問数) × 100
Webサイトやランディングページへの訪問は多いがCVRが低い場合、ユーザーが求める情報が掲載されていないことや、さらに商品・サービスについて知りたいと思わせることができていないと言えます。CVRが低いときには、Webサイトやランディングページの改善を図りましょう。
5.LTV(ライフタイムバリュー)
LTV(ライフタイムバリュー)は、「Life Time Value」の略語で「顧客生涯価値」を表します。クライアントとの取引が始まってから終わるまでに生み出す利益を表す指標です。
スポット型ビジネスと、サブスクリプション型ビジネスで算出方法は異なります。それぞれ以下の式で算出できます。
- スポット型:LTV=取引1回あたりの利益×リピート購買回数
- サブスクリプション型:LTV=クライアント1件あたりの月次利益×継続月数
LTVが低い場合は自社の商品・サービスの継続的な利用を促進できておらず、クライアントとの関係性構築が急務となるでしょう。
まとめ
BtoBマーケティングについて紹介しました。BtoBマーケティングはBtoCマーケティングと異なり、意思決定者が多く商談から受注に至るまで時間を要します。
リードを獲得したら、しっかりと関係性を構築して商談率を高めましょう。営業部門だけでなく、マーケティング部門・カスタマーサクセス部門など各部門間での情報共有を行い、契約・継続利用につながるように効率的にアプローチをすることです。
マーケティング戦略を練る際にはペルソナやカスタマージャーニーの整理を行い、クライアントの課題と自社の目的にあわせて施策を実行しましょう。