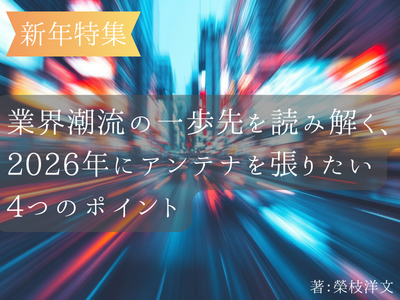若年層の視聴者が約半数を占める
2018年7月に発足し、今年で7季目を迎えるMリーグ。クラブチームと契約を結んだMリーガー(プロ麻雀選手)によるチーム戦の様子は、ABEMAの麻雀チャンネルで配信されている。

「立ち上げ当初は1チーム3名制でスタートし、試合数も定まっていなかった」と語るのは、Mリーグの発足から携わるサイバーエージェントの塚本泰隆氏だ。ユーザーの視聴習慣を作るにあたり、最適な開始時間と試合数を模索し、ルールやレギュレーションの調整にも試行錯誤したという。

試行錯誤の結果、チームの編成を現在の「男女混成4名」に変更。加えて、年間チャンピオンを決めるシーズン形式に変わったほか「プロ野球のナイター中継を家庭で観る文化」に倣い、レギュラーシーズンを9月から、セミファイナルを3月からスタートするスケジュールとした。
これらの工夫が功を奏し、シーズン平均視聴数は毎年右肩上がりに推移。2024年度の視聴数は、初年度(2018年度)の3倍に上るというから驚きだ。
34歳以下の若年層が視聴者の約半数を占めるMリーグ。そのうち19歳以下が約20%を占めるが、視聴者数が特に増加している層は20~34歳の層だ。視聴者の比率を見ると、麻雀が幅広い世代に浸透していることが読み取れる。
発足時に打ち出した「ゼロギャンブル宣言」
なぜMリーグはこれほど盛り上がりを見せているのだろうか。塚本氏は成長要因を四つに分けて解説する。第一の成長要因は「パーセプションチェンジ」だ。
Mリーグを盛り上げるためには、麻雀に対する世間の認識を変える必要があった。塚本氏が学生時代に麻雀プロとして活動していた時代、麻雀はネガティブな言葉とともに語られていた。
一方で、麻雀の奥深いゲーム性に魅了される人も少なくない。近年では「集中力の向上」や「論理的思考の鍛錬」など、麻雀に期待できる効果の研究が進み、高齢者の脳の活性化に麻雀が役立つとするデータも出始めているという。
そこで塚本氏は、熱のこもった実況解説でMリーグの試合を演出し「麻雀は高度なプロ頭脳スポーツである」というイメージの醸成を図った。加えて、リーグ発足時には「ゼロギャンブル宣言」を打ち出し、違法賭博との決別をアピール。小学生を対象とした麻雀大会を主催するなど、健全な麻雀環境の構築を進めている。
「子供の習い事として麻雀が選ばれたり、歴史のあるスポーツ雑誌でMリーグの特集が組まれたり、麻雀に対する認識や麻雀を取り巻く環境は大いに変化しています。パーセプションを変えない限り、新しいプレイヤーや企業の参入は期待できませんでした」(塚本氏)