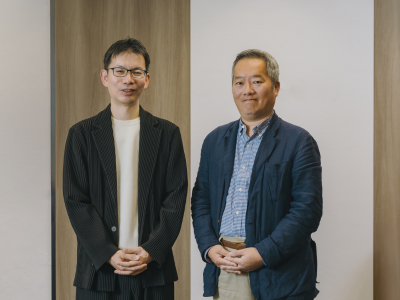営業とマーケティングの分断・サイロ化に、RevOpsという解決策
川上氏はまず、BtoBマーケティングを取り巻く現状について「営業とマーケティングの分断は、日本のみならず世界共通の課題」と問題提起。分断された目標設定によって組織がサイロ化し、顧客体験の質が低下することで、ブランド毀損や売上成長の鈍化につながると指摘する。

この課題を解決するためのアプローチとして注目されているのが、GTM(Go-To-Market)戦略とオペレーションモデルを統合する「レベニューオペレーション(RevOps)」だ。RevOpsとは、持続的な収益成長を実現するために、組織の協業プロセスを強化し、戦略・戦術面で生産性を向上させるための方法論や組織を指す。川上氏は自著『レベニューオペレーションの教科書』に基づいて、次のように解説する。
「営業、マーケティング、カスタマーサクセスを統合的に捉え、戦略とオペレーションを連携させるRevOpsは、顧客への提供価値と業績向上を最大化するように設計されています。『測定』『実行』『再現』を実現するための戦略的アプローチです」(川上氏)

このオペレーションモデルの導入はつまり、「単なる業務効率化ではなく、組織変革の取り組みである」というのが川上氏の見解だ。
「伸びしろ」の多さからクラレの組織変革に着手
中東氏は、消費財メーカー、外資系IT企業、大手通信会社やスタートアップSaaSを経て、2021年8月よりクラレの経営企画室で全社の変革プロジェクトに携わっている。中東氏は、クラレにおける組織変革のきっかけを「伸びしろ」という言葉で表現する。

BtoBマーケティングの経験からデータ分析の重要性を認識していた中東氏は、手始めとしてERP(Enterprise Resource Planning:企業資源計画)から年間売上データをCSV形式で入手し分析。その結果、既存顧客への売上依存度が高いこと、企業コードがないため大手企業グループの親子関係が不明瞭であることなど、様々な「伸びしろ」が明らかになったと言う。さらに、Webサイトの乱立、ツールやプラットフォームの分散、リード管理プロセスの未整備、GDPRや個人情報保護法への対応不足といった問題点も山積していた。
「各国のマーケティング担当者との情報交換を通じて、リード管理プロセスやデータ活用に関する認識のズレも痛感しました。これらの“伸びしろ”を改善すれば大きな成果を上げられるはずだと、ある種の“興味本位”で改革に着手していきました」(中東氏)
では、組織変革推進における最大の課題とは何か? 中東氏は「共通認識の欠如」だと述べる。

「たとえば、現場のマーケティング担当者はSNSやSEOといった施策やツール活用レベルの話題に終始し、その上司は『うちはテレビCMとか派手なマーケティングはいらないんだよ』と費用対効果への懸念を示す。事業責任者は『マーケティングって現場が言っているけど、正直よくわからん』とマーケティング活動の全体像を理解していない。こうした状況で、本社マーケティング部門が『The Modelの分業型が……』『Revenue Processが……』『Demand Centerの必要性が……』と最新のマーケティング理論を語っても、まったく論点が噛み合っておらず組織として動けるはずがありません。組織内での共通認識がなければ、当然コミュニケーションは成立しないのです」(中東氏)
このような状況を打破するために、中東氏が重視したのが「Burning Pain」の定義と生成だ。