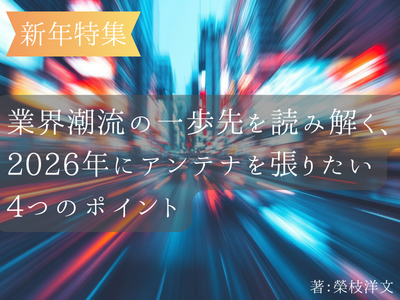会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
新規会員登録無料のご案内
- ・全ての過去記事が閲覧できます
※プレミアム記事(有料)は除く - ・会員限定メルマガを受信できます
- ・翔泳社の本が買える!500円分のポイントをプレゼント
この記事は参考になりましたか?
- ビジヲタ必見!「すべらない事業」の作り方連載記事一覧
- この記事の著者
-

矢作 嘉男(株式会社ハチワン)(ヤハギ ヨシオ(カブシキガイシャ ハチワン))
株式会社ハチワン代表取締役。New Jersey City University卒。
中国人観光客向けクーポンサイトなどインバウンド媒体を運営。
2011年、中国のインターネットプロモーション事業を行う北京博洛密網絡科技有限公司と提携し、中国向けプロモーション事業を開始。本当に成果の出る中国市場向けインターネットマーケティングのみをを提供し、インバウンド向けから中国現地進出向けまで数多くの実績を持つ。
プロモーションのご相談:info@813.co.jp※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア