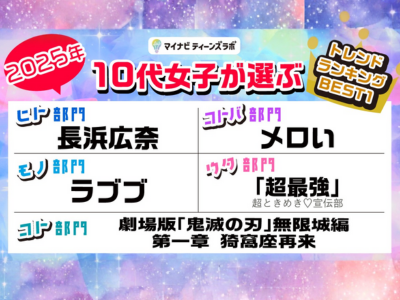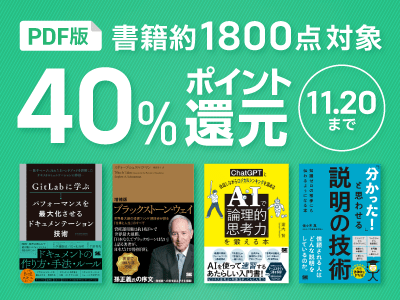施策立案の視点から考えてみると…
施策から考えた例だと例えば…
懸念事項:その2つ以外を買い忘れ、売上が下がる可能性
懸念事項:その2つ“以外”目的のお客様には不便
懸念事項:おむつ+ビールのお客様に不便さを与えないか
懸念事項:非常にテンポラルな施策
懸念事項:人件費、設営費などのまとまった投資が必要など
- ソリューション1…買い忘れないように、近くに陳列
- ソリューション2…入り口近くに両方を陳列する事で、より利便性を上げる
- ソリューション3…おむつとビールをわざと遠いところに陳列。その導線上に他に買ってもらえそうな商品を配置する事でバスケット単価をあげることを狙う
- ソリューション4…おむつとビールと何かもう1点買ったお客様に割引などバスケット単価アップ狙い
- ソリューション5…かさばるものと重いものなので、いっそ駐車場で販売して車に店員さんが運んでくれるサービスなど
それぞれに必要な要件について、再検討・追加調査・分析を行い、
- ターゲットやニーズは存在するか?
- ボリュームインパクトはあるか?
- 懸念点、リスクの課題は?
などから、優先度がつけられるでしょう。調査範囲が比較的限られるので、無駄が少なくて良いかもしれません
ただし、一緒に買っているお客様が多いならば、特別なことをしなくても買っていただけそうですし、ビールもおむつも結構陳列スペースを取る商材なので、気軽に近くにおけないのでは、という実施に当たってのそもそも論も考えられます。
どちらにせよ、これまで見えなかった“事実”をあぶり出す事も重要ですが、そのネタを膨らまし具体的にどう活かすかはそれ以上に重要ですね。
マーケティング分析に関して、今後も記事を書いて行く予定です。マーケティングメトリックス研究所にも、ぜひ遊びに来て下さい。