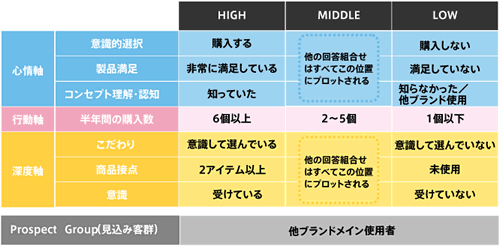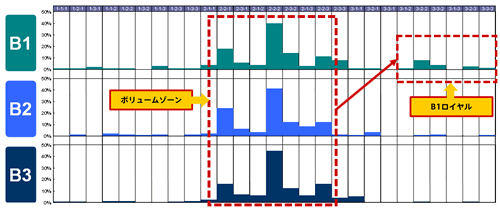事例:ブランドバリュー比較からのDrive
次は、企業内の複数のブランドと他社の製品ブランドを比較しつつ、それぞれのバリューを計測していった例です。ある商品に関する3つのブランドライン(高級ラインのB1、普及ラインのB2、社外ブランド中心のB3)それぞれを従来の3軸の概念で検証しました。アンケートは、このメーカーが運営する情報提供Webサイトを介して行いました。さらに特殊な事前調査を行い、対象商品を「意志を持って選択した層」のみを抽出し、分析母体としました。
3つの軸の判定項目とルールの決定
心情軸、深度軸、行動軸それぞれに2~3問の質問を設定し、その回答パターンをルール化、3つのスケールに落とし込みました。下図は一般的な設問例ですが、ここではさらに意識内部まで深く切れ込んでいます。
- 心情軸:ブランドイメージ、製品クォリティの満足度、価格重視度、存在感など
- 深度軸:製品選択基準、同ジャンル製品使用度、基本的知識・情報の理解度
- 行動軸:最近半年間における対象商品/競合商品の購入頻度
アドレス初期配置結果の分布(ヒストグラム)
配置可能な5000以上のサンプルをベースとし、ブランドごとのアドレスに配置しました。意外なことに、各ブランドのボリュームゾーンはほぼ同じでしたが、高価なブランドラインであるB1には、わずかに高ロイヤリティ層が出現しました。
アドレス特性
特定商品ジャンルの調査ではよくある傾向ですが、9つのアドレスの中心である2-2-2がどのブランドでも半数近くを占め、最大ボリュームゾーンになっています。また、元々商品への意識の高いユーザーを調査母体にしていることもあり、ブランドに対する固執度はかなり高い傾向にありました。B1にロイヤリティ層が出現したのはこのためと思われます。 しかも、この層は行動軸の基準である「該当商品の購入頻度」も高く、自分の意志で自分に合った商品を購入する積極性が傾向として現れていました。
ロイヤル顧客へのDrive施策
この調査結果では、同じブランド内でのロイヤル顧客へのDriveと、ブランド間のスイッチングの2つがポイントとして挙げられます。すべてのブランドで中庸な2-2-2がボリュームゾーンのコアとなりましたが、このアドレスであれば、ブランドごとの性格付けを行う施策を与え、より高いロイヤリティ層にDriveさせることができますし、よりマッチした別ブランドにスイッチングさせることも可能です。例えば、Eメールなどを通して、B1に高度な活用ノウハウ、B2に目的別の成功事例などの情報を与えて上位へのDriveを促進させる、などが具体的施策となります。
価格重視の傾向があるB3には、使用目的を明確にする啓蒙的な情報を与え続ければ、自社ブランドへスイッチさせることも可能と結論付けられたのです。