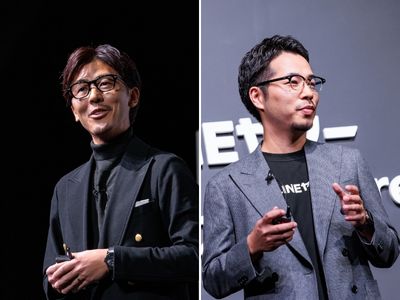サントリーのデジタルコミュニケーションの未来に責任を持つという使命がある
青葉 ――バックオフィス側の支援体制を進める一方で、現場である事業部門がより効果的にITを活用するためには何が必要なのか。皆さんが前に出てやるのではなく、現場である事業部門に活躍してもらうというのは簡単そうで、非常に難しいと思うのですが。
まさにそうですね。私は周囲をぐいぐい引っ張って行くタイプではないので、今のような徹底して支援する役回りが合っているとは感じます。人を動かすというよりも、各部署のベクトルをそろえることが大事なのだと思います。
そうした働きかけが重要だと痛感した出来事がありました。ちょっと前の話になりますが、システム部時代の95年頃に一人1台PCが導入され、私は営業部門のウィンドウズの利用推進を担当していました。PCは導入したものの、人によってはなかなか上手に使えない人もいました。そこで、社内報で「PCの活用法」を連載することを思いつき、担当部署に頼みこんでコーナー化させてもらったところ、社内報を読んでくれた他部署の人から大きな反響があり、ウィンドウズPCの利用が広がる一助になったと感じました。
こちらが伝えたいことも「他人はわかってくれない」ことを前提に進めないといけないのだなと痛感しましたし、この出来事がコミュニケーションというものを仕事として捉える契機になったと思います。
それから、これも20代のときでしたが、やや大きなプロジェクトのプランをまとめていて、上役に許可をもらいに行ったことがあります。しかし、その人と相談して進めていたわけではなかったので、突然プランをぶつけて「YES or NO」を突きつけるような形になってしまい、YESを取るリスクが大きすぎて結局NOとなってしまった。
そこで初めて、もっと現場にも経営層にもきっちりヒアリングして、その上でプランを練って実現可能なラインに落とし込んでいかないと、ゴールから遠ざかってしまうんだなと実感したんです。その経験から、自分より数段上のレイヤーの視点だとどう感じるか、想像しながら判断していくようになりました。

青葉 ――ご自身としては、今後どのような展望を描かれていますか。
ありがたいことに30代のうちからデジタルコミュニケーションを任されてきて、社内では私が一番その領域に詳しくなければいけないという意識を持つようになったので、サントリーグループのデジタルコミュニケーションの未来に責任があるとは肝に銘じています。とはいえ自分ひとりでは何もできない。だからこそ周りを巻き込んで、会社にとってきっと正しいであろう方向に少しでも近づけるよう努力をし続けなければならない、と今もあらためて感じています。
例えばFacebookを新聞で見かけるようになったら、世の中に浸透しつつある証ですから、その段階で経営陣に「当社の対応はどうなっているんだ」と聞かれて口ごもるようではダメだと思うんです。だから日々の勉強・情報収集が大事ですし、自分が気づけない点は、まわりの同僚や外部の有識者に助けてもらいながらアンテナを張り巡らせる意識を持つことが大切です。勉強しながら常に先を見て、このデジタルコミュニケーションの分野で会社に貢献していきたいと思っています。
青葉 ――最後に、坂井さんにとってマーケティングプロフェッショナルとは?
いや、そんな「マーケティングプロフェショナル」なんていえる立場ではないんですけどね。とはいえ、あえて言うならば、「社内外を巻き込む力」が大事だと思います。これは、若手のスタッフにも身につけてもらいたい力です。今は情報環境の変革期で、既存の組織の枠に捉われているといくら戦っても解決できないことが増えています。
そうすると、部署を超えて協力関係を築かなければいけないことも増え、ソーシャルメディアを介すればお客様と一緒に何かを進めて行くことも出てきます。また、取引先との連携も大事です。その時には、相手に動いてもらう力を発揮できるかどうかがカギになりますね。社内調整が大変、なんて発言はしないで、社内調整こそが大事、という発想がよいと思います。
それから、マーケティングに携わる人ならば、「人の行動がどう変わっているかを日ごろから注視する」という習慣も重要ではないでしょうか。例えば、電車の中でも、私は新聞派ですが、今は本当にスマートフォンで青い画面(Facebook)を見ている人が多いですよね。
マーケティング専門誌ではなく、一般の新聞記事にFacebookの話題が出てくる頃にそれに気づいていたのでは遅い。日常的に新しいデバイスやメディアが登場したらまず真っ先に自分が使ってみて、それを仕事に置き換えたときに、どうやって活用できるかまで考えて提案するくらいであってほしいですね。
誤解を恐れずに言うと、厳密に公私の区別はいらないのではないでしょうか。例えば映画制作の仕事をしている人だったら、公私関係なく映画を見まくるでしょう。そのくらいでないと、人より抜きん出ることは難しいですよね。そうやって仕事へのモチベーションが高い人、問題意識の高い人は仕事が楽しくなって、どんどん成長していくのだと思います。会社にとっても本人にとっても、成長していくというのは素晴らしいことだと私は思っています。私もまだまだその域には達していませんが、そういったことを意識してさらに成長していきたいと思っています(文・高島知子)。
創業以来1世紀を超えてもなお、何ごとにも失敗を恐れず、妥協せず、“やってみなはれ”という創業者の精神を脈々と受け継ぐサントリー。
日本初の国産ウイスキーづくりや、新規参入は不可能とまで言われたビール事業へ進出し、苦悩を乗り越えてプレミアムビールの大ヒット。清涼飲料水、健康食品への事業拡大、グローバル化など「やってみなはれ」の精神に基づく挑戦の歴史と、その活躍ぶりは小売業や同業他社からも一目置かれています。
坂井さんとの対談の際に伺った、「サントリーのデジタルの未来に責任を持つ」という言葉には、新しい部署を率い、新たな挑戦をしているリーダーとしての力強さを感じました。使命感をもって業務に当たれる理由についてお訊ねすると、「なんでしょうね、愛社精神かも(笑)」と微笑みながら話をされる坂井さんの姿がとても印象的でした。