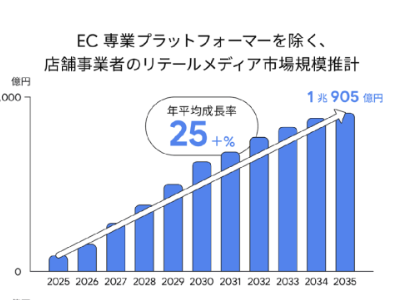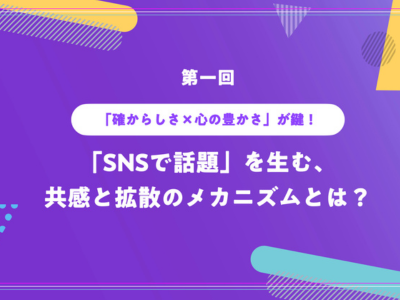会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
新規会員登録無料のご案内
- ・全ての過去記事が閲覧できます
※プレミアム記事(有料)は除く - ・会員限定メルマガを受信できます
- ・翔泳社の本が買える!500円分のポイントをプレゼント
この記事は参考になりましたか?
- マーケティング・プロフェッショナルズ連載記事一覧
-
- 「テレビCM好感度ナンバー1。でも実際はネットを活用した戦略が6割を占める」 ─ エステー...
- 「これからの流通・小売のマーケティングは、お客様との関係性マネジメントが主軸になる」 ─...
- 「新しいことにチャレンジし、新たなカテゴリーを創造できる人になれ」 ─ 日産自動車 貴田晃...
- この記事の著者
-

青葉 哲郎(アオバ テツオ)
サイコス株式会社 代表取締役
東京都出身。明治大学政治経済学部卒業。1994年4月 ジャスコ (現イオン)入社。1995年マイクロソフト入社。トップセールスを経て、最年少ブランドマネージャに就任。MSN事業開発など担当。2001年インテリジェンス入社。マーケティング部を設立し『はたらくを楽しもう。』で同社を転職ブランド1位に。2008年リクルートエージェント入社。『転職に人間力を。』で新ブランドを立ち上げ、コスト減と広告効果の最適化...※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア