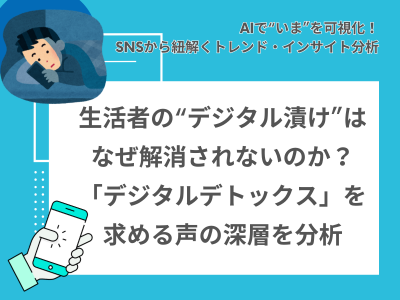1958年の入場者数は、11億人を突破した。しかし1960年代になると、テレビの普及によって入場者数は減少し、72年1.9億人に落ち込んだ。1950年代は、邦画配給収入に占める割合が7割程度であったが、1966年以降は邦画が洋画を超えることはなく、2005年に至っている。
1990年代まで市場が縮小する中で、邦画はさらにシェアを低下させた。その結果、安定的な顧客層が存在し、興行収入規模も安定的なアニメや「寅さん」を軸とする作品ラインナップしか供給できなくなってしまったのではないだろうか。
そのため、ハリウッドの洋画が大ヒットを記録している脇で、邦画といえば、「ドラえもん」などのアニメと「寅さん」など、子供と高齢者向けのものが中心だった。
産業構造の転換
しかし、日本の興行収入は1996年の1,489億円を底にして回復に転じ、2004年には過去最高の2,109億円に達した。その背景には、産業構造が大きく変化したことが挙げられる。映画産業は、製作・配給・興行の3つの事業に分けられる。
製作は、調達した製作資金で、監督や俳優を集め、実際に映画を制作する。配給は、映画を公開するスクリーンを確保し、映画の広告宣伝等のプロモーションを行う。興行は映画館で映画を上映する。
以前はこれらの三つの事業が垂直的に統合されていた。映画会社が自己資金で映画を製作し、それを自社の映画館に配給して、自社の映画館で公開していた。産業自体が成長過程にあるならば、垂直統合の方が映画にかかわる利益を自社に取り込む手段としては有効だったが、逆に、衰退局面においてはリスクやコストの方が大きくなる。つまり、ハイリスク・ハイリターンのビジネス形態だった。
1996年以降に、こうした垂直統合型の産業構造が水平分業型にシフトしていった。興行では、自社のチェーンに縛られないシネコンが登場し、自己資金で調達していた製作資金を製作委員会方式によって各関係者から調達し始めた。映画会社のみで完結していたビジネスから様々な関係者が関わるビジネス形態へと変化したのである。
シネコンの台頭
1993年に神奈川県海老名市の「ワーナー・マイカル・シネマズ海老名」をはじめとするシネコンが開業され、郊外型やショッピングセンター併設型などのシネコンが登場し、その数は07年1月現在では262サイト2,230スクリーンにまで拡大している。
続きを翔泳社Webサイト、MoneyZine(マネージン)で読む