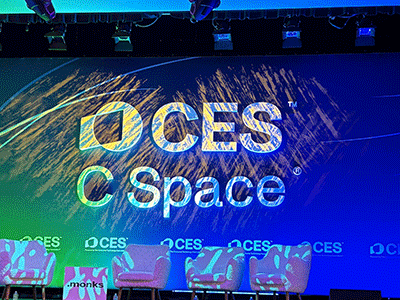SNSマーケティングの行き詰まりの原因とは?
今や、情報収集手段の1つとして当たり前となったSNS。生活者は複数のSNSを使い分けて、趣味嗜好に合った情報を得られるようになりました。こうした状況下で、企業がSNS運用に力を入れる必要があるのは言うまでもありません。しかし、SNSの運用に課題を感じる企業が多いのも現実です。
──「SNSマーケティング観」をアップデートできていますか?
そう指摘するのは、『SNSマーケティング ケースで学ぶ 成果を最大化する技法とロジック』の著者、後藤真理恵氏です。後藤氏はSNSマーケティング支援会社コムニコのマネージャーであり、SNSエキスパート協会の代表理事を務めています。

後藤氏によると、SNSマーケティングに行き詰まりを感じている公式アカウントの運用担当者には、「SNSマーケティング観」がアップデートされていないという共通点があるそう。
SNSマーケティング観がアップデートされていないアカウントの特徴
- 一方的な情報発信ばかりになっている
- 運用の目的が不明瞭
- ターゲットが不明確
- 他社と差別化できていない
- SNSの使い分けができていない
- 宣伝色の強い投稿が多い
- プレゼントキャンペーンの連続実施でフォロワーを増やしている
特に「一方的な情報発信」に陥っているアカウントは多く、ニュースリリースやメールマガジンと同様にSNSが発信ツールとして扱われがちだと述べます。
また、SNSマーケティング黎明期には「フォロワー数獲得」や「いいね数」といった短期的な成果が重視されていましたが、今は違います。「顧客や社会との価値共創の場」として、ステークホルダーとの関係性を深め、ブランドの信頼性を育むツールとして活用することで成果につながるのです。価値共創に向けた取り組みとしては、次の3つが紹介されています。
- SNSごとに異なるユーザー層を理解し、それに応じたコンテンツ作成やキャンペーンを実施し、関係性を醸成している
- オンライン(またはオンライン&オフライン)でユーザー参加型キャンペーンを実施し、価値共創型の投稿コンテンツが増えるよう促している
-
SNS(およびオフライン)を通じて、持続可能な社会の実現に取り組んでいることをユーザーに伝え、興味関心を持たせている
(P.35)
4つのケーススタディーから学べる
「価値共創」と聞くと大層な印象を受けるかもしれませんが、要するにユーザーが発信する情報の扱い方が重要ということでしょう。では実務でどう進めていけばいいのでしょうか。本書では、4つの業種におけるケースを例に、3C分析をはじめとした戦略策定から実行までのノウハウを紹介しています。
飲食業(カフェ):地元住民しか来なかった喫茶店からの脱却を目指し、Instagramの運用とインフルエンサー活用施策を実行した例
小売業(エコレザー専門店):エコレザー製の革小物やバッグを扱うECサイトの売上向上をテーマに、Instagram広告やポップアップストア活用を試みた例
BtoBの製造業(老舗の町工場):若手採用に課題を抱える町工場が、XとTikTokを活用した情報発信と運用体制作りに取り組んだ例
大企業:乱立するSNSアカウントを整理し、社内ルールの整備や属人的運用からの脱却、炎上リスク対策までを行った例
コミュニケーション方針の具体的なルール作りも解説
4つ目の「大企業」のパートでは、コミュニケーション方針の具体的なルール作りにも踏み込み、コミュニケーション施策を2分類した上で業務フロー例やリスク対策とともに解説しています。
-
パッシブ(受動的)コミュニケーション
自社投稿への返信やDMに対して、平日1日1回は「いいね」や返信で対応。内容によって静観対応か返信対応を取る -
アクティブ(能動的)コミュニケーション
UGC(ユーザー生成コンテンツ)を検索して発見し、「いいね」や引用ポストなどで企業から積極的に関与する。たとえば週2回UGC検索を行い、内容やプロフィールの精査によって静観対応か、想定問答集を用いた対応をするか判断する
本書のように、零細企業から大企業までのケーススタディーが1冊にまとまっているのは珍しいと言えるでしょう。特に、手探り状態でSNS運用に関わってきた人なら“あるある”と感じる課題が並んでおり、実務に役立つヒントが見つかるはずです。