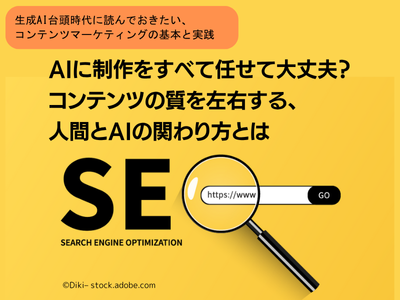田端氏の考えるLINE広告の今と未来
――LAPが急成長を続けている要因とは?
田端:他ではなかなか届かないスマホユーザーにアプローチできているところが大きいでしょう。インフィード広告はTwitterとFacebookの2つがベースになっていましたが、そこにいない層をカバーできているという点ですね。また、スマホの検索連動型広告の市場規模は大きくなっているとは言え、スマホでは検索というよりもフィードの中で見せるほうがより自然な導線です。LAPなら運用型として小額予算から柔軟に、スマホユーザーに向けて効果的な広告配信ができる点をご支持いただいています。

――今回、新たに大阪にオフィスを新設されることも発表されましたが、その意味と狙いは?
田端:小額予算から出稿していただけるということは、地方に本社機能や拠点を持つEC事業主なども積極的にご活用いただけるということです。そういったところに、我々が直接会いにいけるということは非常に大きな意味があります。他社をベンチマークにして、大阪圏あるいは西日本に帰属する広告主の売上比率を推測してみるとまだまだ伸び代があるということもわかりました。
また、全国でご利用いただいているLINE@とのシナジーも期待できます。LINE@は、リピート化には有効でしたが、新規の獲得には向かないプロダクト構造でした。その点をLAPの「コストパーフレンド」型のモデルで、ターゲティングしつつ補うことができるのではと考えています。
――広告枠としてのLINEが目指すものとは?
田端:今日はLAP中心の話でしたが、LINEの広告、マーケティングビジネス全体から見ると、いわゆる狭い意味での「広告枠」というところでの必然性はどんどん下がっているのかなと思っています。たとえば、LINEで宅急便の再配達依頼ができたり、保険の相談ができたり。あるいは、出前もLINEでとれるようになっています。そうなってくると、販促・プロモーションだけではなく、サービスそのものとLINEが渾然一体になっていきます。
とは言え、LAPは、非常に幅広いリーチを取れるものですし、データが集まってくる場という意味では、一連のプロセスの中で重要なパーツとなります。ですので、広告ブロックなどの話はとても残念で、不快にさせたり不健全にならない広告の掲載基準の策定を、業界をリードするつもりでやらせていただければと考えています。正直なところ、代理店の方からは「LINEの基準は厳しすぎ。少し緩めてくれればもっと売りやすいのに」という声をいただくこともあります。それでも、相対的には厳し目の基準でやらせていただければと思っています。