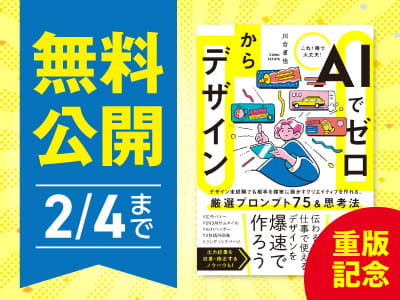会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
新規会員登録無料のご案内
- ・全ての過去記事が閲覧できます
※プレミアム記事(有料)は除く - ・会員限定メルマガを受信できます
- ・翔泳社の本が買える!500円分のポイントをプレゼント
この記事は参考になりましたか?
- 関連リンク
- 「人」「モノ」「メディア」の3つの視点から捉える生活者のリアル連載記事一覧
-
- TikTokなど動画メディア群雄割拠時代、若者はどんな風に動画を消費してる?13の生活シー...
- 動画広告はどんな風に見られている?生活者視点で支持される動画広告のあり方を考察
- 通勤時間が長い人はパッと目を引く広告を好む?プラットフォーム利用実態のリアル
- この記事の著者
-

渡辺 庸人(ワタナベ カネヒト)
株式会社ビデオリサーチ ひと研究所 主任研究員
2009年ビデオリサーチ入社。広告会社やメーカーをクライアントとした調査企画・分析に従事する傍ら、若者研究や幸福研究などに携わり、2017年より現職。メディアと生活行動の関係について若者を中心に研究を進めている。専門社会調査士。※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア