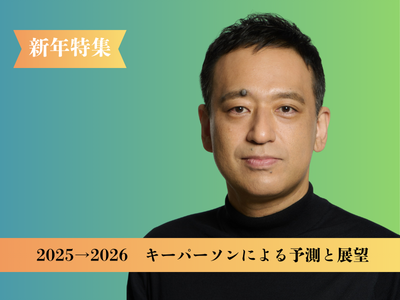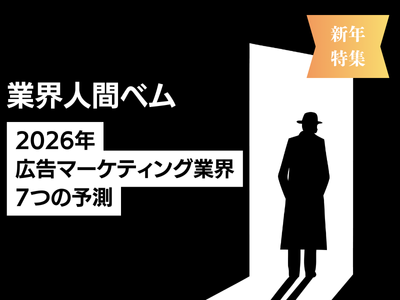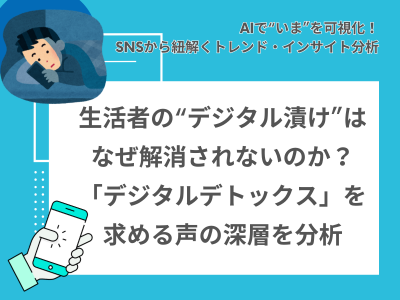業務プロセスを根底から見直すことが本質
では、リテール企業はDXをどのように捉えるべきなのか。田代氏はDXの定義として、経済産業省が2018年9月に発表した「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン Ver. 1.0 (以下、DXガイドライン)」の内容を紹介した。

それによると、DXは「経営・業務・IT すべてを変革し、競争優位に立つこと」を指す。つまり、これまでの業務をITで効率化するレベルではなく、企業組織や既存の業務プロセスを根底から見直すことがDXの本質であるというのが、経済産業省の見解だ。
これまでの「デジタル化」の目的は、その多くが既存の業務プロセスを維持したまま、処理スピードを向上させることだった。しかし既存業務の効率化だけでは、先に挙げた急激な変化に対応できない。特にリテールは顧客密着型のビジネスだ。田代氏は「顧客の消費行動が変化している以上、顧客を理解し、柔軟に対応できる組織体制にする必要がある」と語った。
逸見氏は、DXの推進にあたってリテール業界が抱えている課題として「マーケティング部門が商品部や営業部、販売部と並列に扱われていないこと」挙げる。
「リテール業界では商品部と販売店舗営業部の発言力が大きく、マーケティング部は“彼らの下組織”という立ち位置でした。そのため組織的にも、DXを推進するという体制になっていません。しかし本来はマーケターこそが、DX推進のフロントラインに立つ存在であるべきなのです」(逸見氏)
データの点在・定義のズレがDXを阻む
次に両氏は、リテール企業がDXを進めていく際の道筋と障壁について議論した。逸見氏は「現在は顧客の購買行動データがある程度取得できるのだから、データを分析して商売を考え直さなければいけません」と強調した。
たとえば、これまでのPOSデータからは、「いつ」「どの店で」「何が売れた」しかわからなかった。しかし、デジタルでPOSデータに顧客IDを紐付けることができれば、「どういった属性の顧客が」「どのようなカスタマージャーニーを経て」「何を購入したか」までがわかる。さらに、その顧客が新規顧客なのか、既存顧客なのか、既存顧客であればどのような購買活動をしているのか(毎年継続/新規継続/休眠復活)まで判明する。
また田代氏は、データの点在を問題点として指摘した。
「BI(Business Intelligence)などを活用して売上や在庫、発注、仕入れといったデータを分析し、次にとるべきアクションを決める。マーケティング戦略が確立している企業では、ごく自然に行われているプロセスですが、こうしたデータがバラバラに点在していると、お互いを連携して分析することができないのです」(田代氏)
データの点在がもたらす罠は他にも存在する。同じデータであっても部署ごとにデータの定義が異なる事態が発生し、議論の食い違いが起きてしまうこともあるのだ。
さらにリテール企業は、データを活用して業務効率化しないと、販売の現場は人手不足で立ちゆかなくなる可能性もある。過去に逸見氏が執行役員EC事業部長として働いていたカメラのキタムラでは、店舗販売員の業務効率向上を目的に、手元のタブレットで在庫が見られる仕組みを構築した。その結果、店舗販売員は顧客からの在庫問い合わせなどを接客しながら確認できるようになった。これにより、人手不足による販売機会損失が削減できたという。