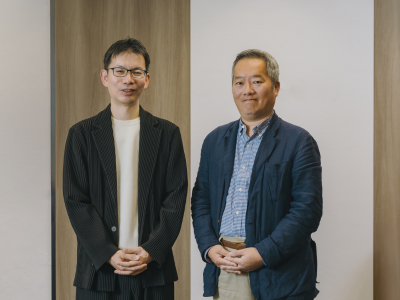会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
新規会員登録無料のご案内
- ・全ての過去記事が閲覧できます
※プレミアム記事(有料)は除く - ・会員限定メルマガを受信できます
- ・翔泳社の本が買える!500円分のポイントをプレゼント
-
- Page 1
-
- Page 3
この記事は参考になりましたか?
- 「プロジェクト譜」で見出す、マーケティングの勝ち筋連載記事一覧
-
- 見込み客はなぜ逃げてしまうのか?ウェビナーでは「学習プロセス」が失われていた
- 開封率が上昇傾向、今改めて注力したいメールマーケティング 「勝つ」ために必要な3要素とは?
- プロジェクトの見直しを迫られた今、取るべき行動は?管理ではなく「編集」の視点でコロナ危機を...
- この記事の著者
-

前田 考歩(マエダ タカホ)
「問いかけ・対話」と「構造化」でプロジェクト進行を支援する、平日早朝のみ開業の『プロジェクト・クリニック』を運営。プロジェクトを「管理」ではなく「編集」して進める方法として「プ譜」を考案。プ譜を使ったプロジェクトのコンサルティングや、企業及び小学生から大学生を対象に、プロジェクトを進めながら学んでいくPBL(Pro...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア