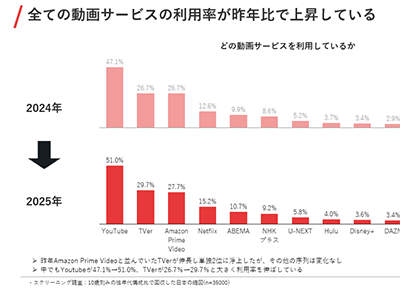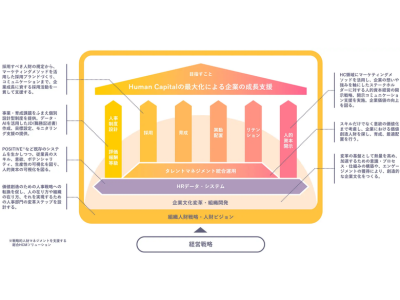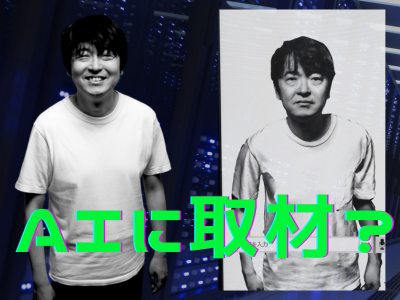コロナ禍でも契約数を伸ばすオープンハウス
1997年に創業したオープンハウスは、東京・大阪・名古屋・福岡といった都市部の商圏を中心に展開する、総合不動産企業だ。現在の売上高は、5,403億円(2019年9月末)と、業界全体では7位に位置する。2013年には東証一部に上場し、毎年15%〜20%のペースで成長を続けている。目指すは売上1兆円と、各メディアからも注目が集まる話題の企業だ。その勢いはコロナ禍の今も顕在で、今年4月の仲介契約件数は前年比マイナス39.3%となったものの、5月は43.0%へ増加。直近の8月も62%増と、順調に前年度を上回る契約数の伸びを見せている。

博報堂出身で、2018年よりオープンハウスのマーケティングと広報を担当するスピーカーの加藤勤之氏は、同社の強みを「勢いのある営業力と、顧客へ徹底的に寄りそったスピーディーな商品開発」と分析する。
オープンハウスは、一棟買い/一棟売りの収益不動産や分譲マンション、海外不動産など幅広く扱うが、戸建て住宅がメイン商材だ。土地の仕入れから企画設計、建設、仲介と、同社グループ内でワンストップに進め、中間マージンを節約。ステイクホルダーが複雑に関わる、一般的な不動産商流と異なるため、市場価格よりも1,000万円ほど下げた販売価格で、土地付き戸建てを提供する。「該当のエリアで現実的な価格感をメンバー同士で共有しあい、市場感を把握している」と加藤氏。
ライフスタイルの変化に合わせた「住みたい家」を開発
しかし、オープンハウスが支持される理由は、決して価格だけではない。「顧客がどのような住まいを求めているか?」の視点で開発する、マーケットインの商品が、同社の特長であり強みだ。仲介業からスタートしたオープンハウスは、顧客のニーズとマーケットのミスマッチを痛感し、住宅の自社開発へシフト。その姿勢が、今日のライフスタイルの変化に合わせた住宅提供に繋がっている。
総務省の調査によると、言わずもがな少子化は進んでおり、また1990年代後半からは、共働き世帯と専業主婦世帯が逆転。今では、7割近くが共働き世帯と言われている。さらに、ダブルインカムとはいえ、年々世帯所得も低下し続けている状況だ。顧客が求める住宅は、親世代のそれとは異なってくるだろう。
「まず、大きな家よりも暮らしやすいコンパクトな家をご希望されます。そして、保育園の送迎を考えると、駅に近く、通勤圏内1時間までが現実的です。また、リーズナブルな価格帯に越したことはありません。このようなお客様の目線から開発したのが、オープンハウスの戸建てやマンションなのです」(加藤氏)

郊外?駅近?住宅のニーズは本当に変わったのか?
放送するテレビCMでは、「時代が変わっても価値が変わらないものは?」という問いに、ユーモアも交えて「愛より駅近の土地」のメッセージを発信している、オープンハウス。
しかしコロナ禍で、生活は急激に変わった。加藤氏は、「家族分の個室や、近隣への騒音を気にせずに子どもが暮らせる環境があったら……と、悩まれた方もいると思います」と、自身の体験も含めてここ数ヵ月の変化を振り返る。
学校が一斉休校し、保護者もテレワークとなり、家族が一つ屋根の下24時間過ごすことが増えた。緊急事態宣言が解除されたあとも、オフィスを縮小し、テレワークを推奨する企業も出てきている。
こういった状況を受け、「大きい住宅を求め、郊外が注目されるかもしれない」「駅近の土地の価値が、変わるかもしれない」などが囁かれていた。顧客視点を重視するオープンハウスは、商品開発を見直したのだろうか?
結論からいうと、同社は駅近・土地付き戸建ての基本方針を変えていない。顧客調査を行い、噂や曖昧な情報ではなく顧客の声をしっかりと聞いたのだ。