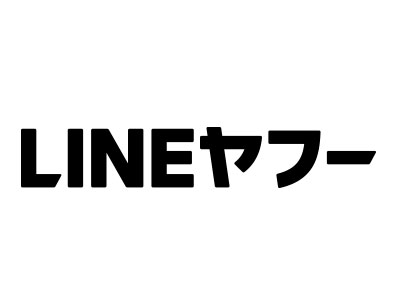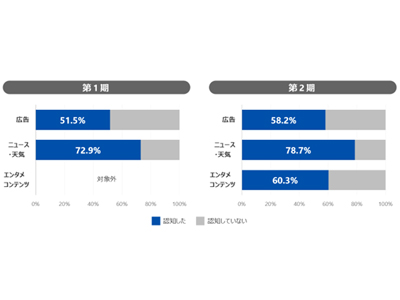コロナが「HaaS」への動きを急速化させた
江端:コロナ禍で事業に変化は起こりましたか? 感染拡大にともなう外出自粛やおうち時間増の影響で、楽器の需要が上がっていると聞いていますが。
石附:確かに、この機会に新しい趣味をはじめよう、音楽を再開しようという人が増えたこともあり、楽器事業は好調に売上を伸ばしています。
一方で大きな変化を迎えたのは、教育事業です。売上構成の多くを、関数電卓や電子辞書をはじめとしたハードで形成していましたが、コロナでオンライン授業が導入されるようになり、ソフトウェアの必要性も高まっている。
なので現在は、関数電卓で培ってきたノウハウをオンラインの中でどう提供できるか考えながら新しいサービス開発にも取り組んでいます。
何年も前から教育のオンライン化が始まっていながら、これまでハードの需要が高いが故に、それを守ることばかりに意識が向かっていた。ある意味で、コロナがドラスティックに事業全体を動かすきっかけを作ったと言えるかもしれません。
江端:「SaaS」ならぬ「HaaS(Hardware as a Service)」みたいな動きがこれから加速化していきそうですね。
石附:目指しているのはそこに近いですね。ハードをどうサービスに変換するかは、ハードを持っている企業にとって取り組まざるを得ない問題でしょう。そのときに自社の強みをどう生かすかが勝負になってくると思います。
江端:具体的に何か実施されている取り組みはありますか。たとえば、『マーケティング視点のDX』で取り上げていますが、老舗のギターメーカー「Fender(フェンダー)」は顧客視点のDXを実践して事業を立て直しています。上達しないことを理由に弾くのをやめてしまう人が多いことを知り、オンラインで24時間ギターレッスンを受けられる場を提供したことで、大幅に売上を伸ばしたそうです。
石附:音楽事業については、具体的なサービスはまだ検討中ではあるものの、今後はハードと共に日々楽器を楽しんでもらうためのサービスを提供していく姿になっていくとみています。
やり方は様々あると思いますが、大事なのはカシオがどんな価値を、どういう人に届けるかを明確にしておくこと。今見えているのは、おうち時間を充実させるような需要ですが、それ以外にもかなり幅広い人に楽しんでもらえるはず。先ほどお話したように、顧客の購入や利用状況をデータとして収集できるようにすることで、また違ったサービスが提供できるようになると考えています。
既にあるものでいうと、関数電卓で培ってきた計算エンジンをソフトに応用し、オンライン学習ツール「ClassPad.net」として提供しています。eラーニングの進んでいる海外向けに提供していたものを、ポストコロナなどを見据えて国内でも利用できるようにしたものです。パソコンやタブレットで関数計算やグラフ描画ができたり、授業で投影資料としたり、オンライン授業をサポートするツールになっています。