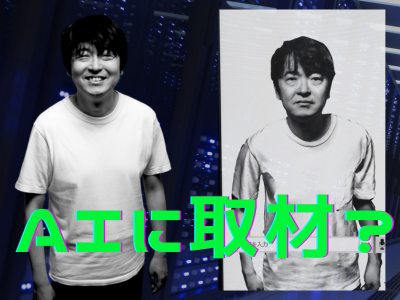成功例が増える一方、“過度な期待と幻滅”も
――本連載では、小島さんが早稲田大学の社会人教育事業「WASEDA NEO」にて実施する連続講座の様子をレポートしていきます。本日はその理解をさらに深めるため、事前インタビューの時間をいただきました。早速ですが、コミュニティマーケティングの現状について教えてください。
小島:コミュニティマーケティングはうまく活用すればスケーラブルな効果を生み出せる施策であり、多くの事例がそれを証明しています。そのため取り入れたいと考える企業はもともと存在していたわけですが、新型コロナ感染拡大で従来型の訪問営業や対面セミナーが大幅に制限される中、コミュニティを通じて新規顧客を獲得し、顧客生涯価値(LTV)を向上したいと考える企業が一気に増えてきました。LinkedInなどを見ても、コミュニティマネージャーの求人が増えていることがわかります。

小島 英揮氏
株式会社PFU、アドビシステムズ株式会社等を経て、2009年に日本での採用第一号としてアマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社(AWS)に入社。 AWSのユーザーコミュニティ「JAWS-UG」の立ち上げに携わり、AWS Summit Tokyo を、世界最大規模にまで成長させ、日本市場での売上を米国に次ぐ世界2位の規模に押し上げた。JAWS-UGは日本最大規模クラウドコミュニティとなり、コミュニティ・マーケティングの伝道師として知られる。AWS退社後は、複数企業のマーケティングを支援するパラレルマーケターとして活躍。コミュニティマーケターのコミュニティ「CMC(Community Marketing Community)_Meetup」も主催する。
しかしコミュニティは比較的新しい施策であり、知見や経験をもった人材はまだまだ不足しています。そのため“なぜやるのか”の理解や合意があいまいで、過度な期待を持ち続けたままコミュニティを運営しているケースも多く、これが「想定していた成果が得られなかった」という失望を生む要因になっています。
とはいえ、ガートナーのハイプ・サイクルが表すように、過度な期待が幻滅につながっていくという流れは、新しい取り組みが普及する際に必ず起こるものです。私は現在の状況を一種の「コミュニティバブル」と捉えていますが、幻滅期に差し掛かるタイミングで「なぜやるのか」が明確化されたり、ノウハウが蓄積されたりすることで、正しい知識や実践方法が少しずつ広まっていくのだと思います。

うまくいかない原因は3つに集約される
――コミュニティマーケティングが“幻滅期”に入りつつある背景には、なんらかの原因で施策がうまくいっていないこともあるのかもしれません。なにが障壁になっているのでしょうか。
小島:大半の問題は次の3つに集約されます。1つは他部門の協力が得にくいというものです。せっかく口コミで興味を持ってくれた見込み顧客がいても、営業のフォローがなければ売上にはつながりませんよね。そのためコミュニティはどこからどこまでを担い、他の部門には何をしてもらいたいのか説明し、実際に動いてもらう必要がありますが、担当者自身がマーケティングの全体像とコミュニティの効果を深く理解していないと、説得が難しいのです。
2つ目は集客が目的化してしまうこと。コミュニティは関心を軸とした集まりで、参加者に「あのイベントは良かったよ」と発信してもらい、それを見た人が新たに参加する「再生産型」の施策です。目先の参加者数やコンバージョン数だけを追い続けるのは適切ではありません。
もちろん数値目標そのものは必要です。成功している企業は必ず目標を設定しています。ただし、コミュニティがどのように成果に結びつくか理解した上で、定量・定性の指標を組み合わせて設定することが重要です。

小島:3つ目は、コミュニティ形成そのものの難しさです。担当者は場当たり的に人を招き入れるのではなく、参加者とのコミュニケーションから、彼らの“人となり”やコミュニティに求めていることを察して、どんな役割でその場に参加してもらうと良いかを考えて立ち回る必要があります。
たとえばコミュニティの立ち上げ段階では、参加者からアウトプットが生まれることが肝心です。そのためには、製品のファンで情報を自主的に発信してくれる「リーダー」と、リーダーが発信した知見を実践する「フォロワー」を核とした、熱量の高い初期コミュニティを作らなければなりません。この段階で、「一方的に情報を受け取りたい」という人ばかりを集めてしまうと、熱量の高いコミュニティを作るのが難しくなります。このような“目利き”ができるかどうかが、成否を分けるのです。
――マーケティングとコミュニケーションの両面で、高度な知識やスキルが必要になりますね。
小島:はい。コミュニティマーケティングは本来、経験豊富な人材がフィットするポジションなのですが、そのことがあまり理解されていないと感じます。そうでなければ必要なスキルセットが身につくよう、会社が教育の機会を提供する必要があるでしょう。