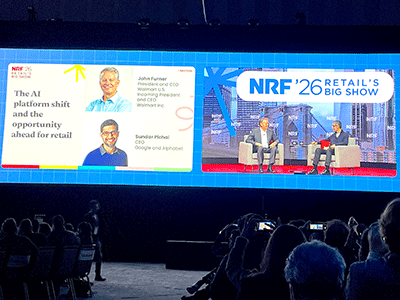※本記事は、2021年5月25日刊行の定期誌『MarkeZine』65号に掲載したものです。
「テレビvs.デジタル」から「テレビ×デジタル」へ
インターネット広告の伸長とともに、長年テレビとデジタルは対立構造で語られ、「テレビは衰退する」と言われてきました。しかしここ数年テレビコンテンツが様々なプラットフォームで同時配信、見逃し配信される一方、テレビデバイスを使って、放送局以外のデジタルプラットフォームの視聴もされるようになり、かつてのようなテレビとデジタルの対立構造は薄れ、「テレビ×デジタル」の様相を呈しています。多くの方は「テレビでYouTubeを見る」「YouTubeでテレビを見る」の両方を体験したことがあるでしょうし、デジタルの雄Netflixの放送セッションの70%がテレビで見られていることも、このテレビとデジタルの融合を物語ります。だからこそ、改めて「テレビ」の定義を捉え直すことが必要です。その文脈の中で、テレビが「デバイス」「プラットフォーム」「コンテンツ」の3つを指すと考えると、いろいろ整理がつくかもしれません。テレビという筐体は視聴「デバイス」の一つですし、放送局は放送という「プラットフォーム」を提供しています。そしてテレビ番組は「コンテンツ」です。ひと言で「テレビ」といっても、デバイスを指すのか、放送局のことなのか、それとも番組のことなのか切り分けて考えると、様々なことが見えてきます。
まず「デバイス」としてのテレビを見ていきましょう。テレビの前での一日平均の視聴時間は、2013年の151.5分から2020年の144.2分と、「テレビ離れ」という印象からは程遠いほぼ横ばいの状態が続いています。同時期に視聴時間が50.6分から121.2分へ伸びたスマホと比較すると見劣りますが、メディア総接触時間が伸びていることもあり、スマホ増の影響をほぼ受けていない、ということが数字から見受けられます。そのヒントは、テレビのデバイスとしての特徴にあるのかもしれません。パーソナル・デバイスが台頭してきた今、テレビが唯一のマルチ・パーソン・デバイスとして、複数人が同時に見るのに適したデバイスになっています。スマホを始めとするパーソナル・デバイスがあれば、「一人暮らし」の人にとって、必ずしもテレビという「デバイス」が必要ではなくなりました。しかし、家族やパートナー、友だちなど二人以上で暮らすとき、コミュニケーションの一つとして、「一緒に」テレビが視聴されるようになってきます。実際、統計データからも若者のテレビ離れよりも、一人暮らしのテレビ離れ、がより現象として読み取れています。
一方で、今までテレビ上では放送局の独壇場であった「プラットフォーム」は、OTTの台頭により、今までにない競争を強いられることになりました。テレビデバイスに映るコンテンツは、OTTの台頭により多様化し、数年前には既に7割がテレビ「デバイス」から視聴しているNetflix、アメリカでは3割以上はテレビによる視聴で、日本でもテレビによる視聴が昨年は前年比1.5倍まで増えたYouTubeなどを含め、アメリカでは既に、テレビという「デバイス」で視聴されているコンテンツの5割以上が「放送以外」のものとなっています。OTTを含め、様々な動画配信プレーヤーが台頭していますが、広告主が注目すべきなのは、広告収入で収益を上げているビデオオンデマンドサービス、AVOD(Ads video on demand)です。日本におけるAVODの代表例はYouTube、AbemaTV、TVerなど。中でもYouTubeの視聴量は圧倒的で、今までも日本の動画広告市場で重要な位置付けではもちろんありましたが、これからOTTの世界でも引き続き重要な位置づけになるでしょう。

一方、SVOD(Subscription video on demand)は月額課金のサブスクリプションモデルで展開する、会員制ストリーミングサービスです。最有力は言わずとしれたNetflixですが、アメリカではここ数年、Disney+やHBOmaxなどSVOD市場に新たなプレーヤーが急増。加入者数も右肩上がりで、競争が激化しています。競争が激しくなってくる中、テレビ視聴に向き合うことが、こうしたサービスの一つの成否ポイントにさえなっています。大物プロデューサーや元有名企業CEOを創業者に持ち、昨年鳴り物入りでローンチしながら、ほんの半年でサービス終了した「Quibi(クィビ)」というサービスがありますが、華々しいPRとは裏腹に、敗因の一つとして、スマホ×上質の動画という当初の狙いにこだわったあまりテレビ視聴をサポートしておらず、上質な動画なら大画面で見たい、というユーザーニーズを完全に読み違えたことが挙げられています。