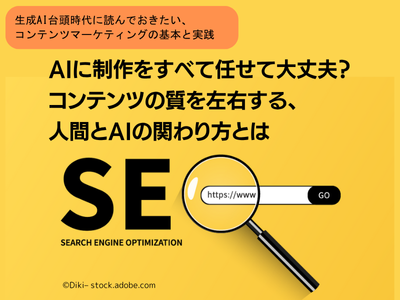楽しさと訴求メッセージのさじ加減
MZ:コラボレーションで気をつけていらっしゃるポイントを教えてください。
土岡:コンテンツサイドの方と、協力して企画を作ることです。私たちも、ファン心理を理解しようと努めていますが、「どうすればファンの方が喜んでくれるか」を一番理解されているのは、やはりコンテンツサイドの方々です。先方のご意見を伺いながら、どうやってブランドのメッセージを届けていくかを考えています。
例えばヒプノシスマイクさんの企画は、6人のディビジョンリーダー(作品内のキャラクター)がカレーメシを紹介するラップを毎日一人ずつ披露する内容にしました。
#ヒプノシスマイク #ヒプマイ pic.twitter.com/MQDNxoX0mD
— カレーメシくん (@currymeshikun) May 26, 2020
このときはカレーメシとして訴求したいメッセージをお伝えして、リリックを書いていただきました。私たちは、メッセージがきちんと含まれているかと、ブランドとして避けたい表現についてはチェックしますが、基本的にはコンテンツサイドの方にすべてお任せしています。
MZ:ファンが支持しているコンテンツの魅力と、ブランドの訴求メッセージをどのように組み合わせるかのさじ加減がポイントなんですね。
土岡:コラボは深さが大切です。テレビCMに比べると接触率は当然高くありませんが、接触後の商品購入率やブランド好意度はとても高い。反面、コラボ企画の内容によっては、ファンの方が面白くないと感じられてしまうこともあります。ですから、企画の立案にはファン心理をよく理解しているコンテンツサイドの方とのリレーションが欠かせません。
MZ:コラボ企画では、商品とオリジナルグッズをまとめた特別BOXセットも販売されています。このようなお買い物体験も、ファンにとっては嬉しい企画ですよね。

土岡:企画内容に応じて、BOXセットをご用意しています。ホロライブさんの企画では、コラボ限定ユニットによるオリジナルソングを制作したのですが、これをCD化したらファンの方々にもっと喜んでいただけるのではないか?と考え、BOXセットとして販売しました。
来店・購入を促した「デジタル実演販売」とは
MZ:ホロライブのコラボでは、「#ホロライブカレーメシWEEK」を展開されていました。ユーザーからカレーメシの味変えレシピを募集し、「カレーメシ味変え選手権」として動画配信を行うなど、大がかりな企画ですよね。
土岡:そうですね。Vtuberならではの企画を意識しました。また、店頭施策にもコラボ企画を連動させ、「デジタル実演販売」を行いました。
これは、一部の店舗の売り場に備え付けたPOPのQRコードを読み取っていただくと、ホロライブのメンバーの動画が再生され、カレーメシを実演販売してくれる内容です。コロナ禍でなかなか実演販売ができない中、新しいデジタルの取り組みになったと思います。
MZ:購入も、ファンにとってワクワクする行動に変わりますね。
土岡:そうなんです。また、ファンの方達がTwitter上で対応店舗の情報交換をされるなど、反響の大きさを感じました。
MZ:お話を伺っているとTwitterも、コラボに欠かせない存在ですね。ファンの反響もすぐに見えますし、リツイートによる拡散力も大きいです。
土岡:カレーメシではないのですが、同じカップライス商品の「カップヌードル 謎肉牛丼」を発売した際にTwitterのパワーを実感しました。この商品では牛丼好きを公言されているホロライブの白銀ノエルさんとコラボし、「デジタル牛丼食事会」を行いました。ノエルさんと一緒に謎肉牛丼をデジタル上で食べようという企画で、ライブ配信時には4万人のファンの方に集まっていただきました。

Twitterでも賑わいが起き、「#デジタル牛丼食事会」がトレンドに上がったんです。すると、ファン以外の方にも目にとまり、「謎肉牛丼ってなんだろう?」といったツイートが出てくるなど、多くの方に商品を知っていただく機会になりました。