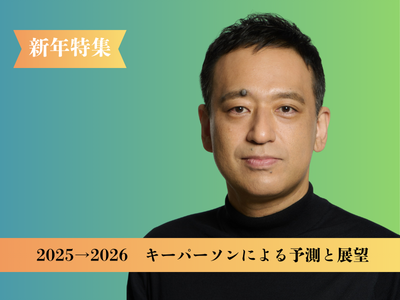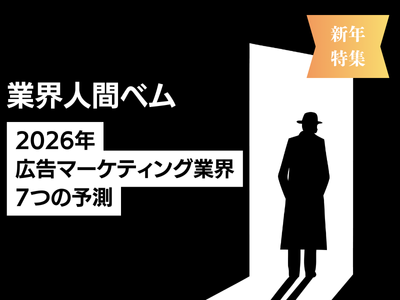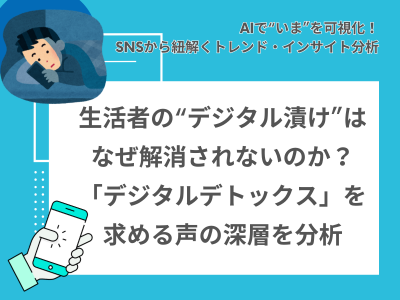※本記事は、2022年11月25日刊行の『MarkeZine』(雑誌)83号に掲載したものです。
今なぜCXなのか顧客と向き合う意味を考える
製品・サービス開発にはCXの観点が重要──このことに異を唱える人はいないだろう。
今業種・業界を問わずCXが注目されている。その背景として挙げられるのは事業環境の厳しさだ。新規顧客の獲得は人口減少トレンドによって難しくなる一方で、顧客のニーズは多様化・個別化かつ継続的に変化し、さらには新興企業が斬新な切り口で市場に参入してくる。こうした環境の変化への対応が遅れれば製品・サービスがコモディティ化し、顧客が離れかねない。モノもサービスもあふれかえる社会では、製品・サービスの機能的な側面だけで差別化を図ることは難しいため、CXを軸とした新しい価値の開発やエンゲージメントの形成に期待が寄せられているのである。
これまで製品・サービスの開発においては企業視点が優先されてきた。顧客体験は、度外視とは言わないが開発をドライブするほどのコンセプトではなかった。ブランドが顧客にどう思われているかを知ることは一部の部署の仕事であって、全社的な課題ではなかった。
しかし、今はすべての部署がCXについて考えなければならない時代になった。デジタル化の進展により企業と顧客との接点は多岐にわたり、チャネルも多様化した。顧客を含む生活者同士の情報交流も数年前には想像できなかったくらい盛んである。このような環境の変化において、企業は全面的かつ全社的に顧客との関わり方を見つめ直す必要に迫られているのである。
顧客の実態把握における問題
顧客の理解が十分でなければ、CXへの取り組みは表面的な活動に留まる。これを避けるために必要なのは、ターゲット顧客のインサイトを知ることだ。頻度や深度の差こそあれ、どのような企業も何かしらの取り組みをしてきたと思う。しかし、真の差別化につながるインサイトは簡単に得られるものではない。
一般的にインサイトを発掘する調査を行う場合、競合他社も似たような手法を採用するケースが多く、得られるインサイトに決定的な差が生まれにくい。その結果生み出される商品・サービス、ないしは顧客体験は同質化してしまうのである。
そこで、自社が独自の価値判断軸(後述)という“フィルター”を持ち、導き出すインサイト自体の差異化を図るとこの問題を解消することができる(図表1)。

他社と異なるインサイトを手にすることができれば、理想とする未来の顧客体験の創造につながる。