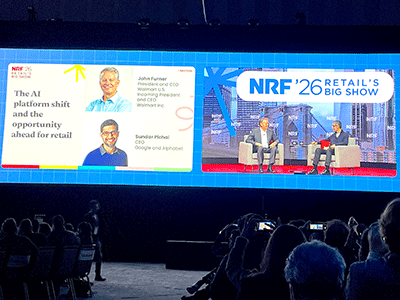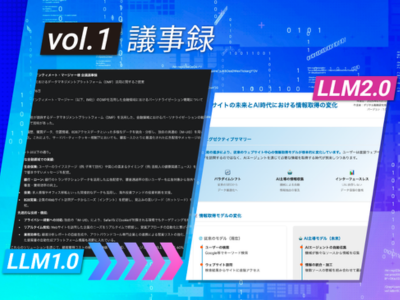営業部門がマーケティング手法に懐疑的?
今回紹介する書籍は『BtoBマーケティングの定石~なぜ営業とマーケは衝突するのか?』。著者はデジタルマーケティング支援ツールなどを提供しているWACUL(ワカル)の代表取締役・垣内勇威氏です。

垣内勇威(著) 日本実業出版社 2,420円(税込)
垣内氏は、2013年にWACULに入社。2019年に産学連携型の研究所「WACUL Technology&Marketing Lab.」を創設し、同所の所長および代表取締役として、マーケティングナレッジを世に広める活動をしています。
本書の第1章では、BtoBマーケティングの大半が失敗に終わる理由を解説し、第2章では具体的な組織作りの方法を紹介。第3章以降で、BtoBマーケティングを成功させるための戦略・戦術の立て方を、購買ファネルの段階ごとに整理・解説しています。
本書の冒頭、垣内氏は読者に対し次のように語っています。
日本に古くからあるBtoB企業の多くは、私の知る限りでも少なくとも20年前から「マーケティング」を導入しようとしては、失敗を繰り返しています。〈中略〉この原因は非常にシンプルで、「売上」を担ってきた営業部門の人たちが、「マーケティング」の手法に懐疑的であり、連携がスムーズにいかないという組織課題にあります。(p.20)
垣内氏によると、日本のBtoB企業の営業担当者には、マーケティング手法の多くが自分たちの仕事を“邪魔するもの”に見えているのだといいます。なぜ、このように営業部門とマーケティング部門には壁ができてしまっているのでしょうか?
社内の「世直し革命」を起こす心づもりで
両者の心理的距離の背景として「BtoB企業の周囲にはマーケティングという概念が育ちにくい環境があった」と指摘する垣内氏。日本は国土が狭い上、大手企業が都市部に集中していることからBtoB企業の営業担当者はマーケティングに頼らずとも足を使うことで成果を上げられていたのだといいます。しかし、売上の頭打ちや国内市場の飽和、優秀な人材の流出、さらには新型コロナウイルスの感染拡大によって、足で稼ぐ営業手法からの脱却を図る必要がでてきました。
しかし、いざマーケティングに注力しようとしても、会社全体が「結局は足を使った営業の方が売上につながる」という考え方を改めていないため、取り組みの多くが失敗に終わっているのだといいます。
よくある失敗例として挙がるのが、マーケティングを軸とした部門横断組織を作っても、その組織の権限が弱いゆえに部門間で摩擦が起きてしまうケースです。この場合、マーケティング部門が良かれと思って取ったアポイントも、営業部門からすれば「突然現れた部門から成約につながらなさそうなアポイントを入れられた」と感じ、反発したくなるのだそうです。
言うまでもありませんが、マーケティングが営業担当の邪魔をしてはなりません。マーケティングは「足を使った営業担当」を活かしつつ、彼ら彼女らを全力でサポートすることから取りかかるべきです。(p.24)
マーケティング担当者はトップセールスのスキルを他の営業担当者が再現できるような座組みを作ったり、単純業務の効率化を図ったりすることで、営業担当者をサポートするべきだと垣内氏は述べます。しかし、言うは易く案ずるは難し。営業とマーケティングが二人三脚の状態を目指すのであれば「世直し革命を起こす覚悟が必要だ」と垣内氏は強調します。
「革命」なのです。圧倒的な熱量を持った先導者が現れ、少しずつ社内の協力者を巻き込み、最終的にまったく違う会社になるくらいのゴールを目指さなければ、マーケティングが浸透したとは言えません。(p.37)
ボトムアップであらゆる企業で“革命”を起こせるように
“革命”を起こすにはトップダウンとボトムアップの2通りの方法があるといいます。1つ目の方法がトップダウンです。これは、各部門の権限を超越した、いわば「CMO」的なポジションを置き、大鉈を振るって前に進める方法です。ただ「日本の企業文化においてはCMOに権限を集中させることは難しい」と垣内氏。「CMOが柔と剛を使いこなして組織を動かすのであれば成功の可能性はあるが、そんな傑物を採用できる可能性は極めて低いだろう」と語ります。
もう1つの方法がボトムアップです。様々な事業部がある企業においては「まずは1つの事業部に絞って、顧客接点を担う専門チームを作るのが良い」と垣内氏は助言。ボトムアップの方法はトップダウンに比べて実現しやすく、推進担当者の熱意さえあればどのような企業であっても再現できる可能性が高いとのことです。
2章以降では、垣内氏がこれまでのコンサルティング案件で体験した成功・失敗例を基にボトムアップの推進方法を解説。「MAを導入しデータ統合も進めているのに、マーケティング手法の社内浸透が進まない」「マーケティング部門の社内におけるプレゼンスがいまだ低い」そんな悩みを抱えたマーケターの方は、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか?
本記事は日本実業出版社からの献本に基づいて記事作成しております