広告でモノが売れない時代、加えるべきPR的な考え方
──統合マーケティングにPRの視点が加わることで、どのようなよい変化が起こるでしょうか?
PRと広告が統合されることで、広告がより自然な形で消費者に受容されるようになります。「今評判のアレか」「友達の〇〇が言っていたのはコレか」というふうに、空気づくりができていれば、広告も情報として自然に受け取ってもらえるようになる。まず一つ、これは明らかによいことでしょう。
もう一つ、それによって、マーケティングの費用対効果が改善されます。「広告でモノが売れない」と言われるようになって久しく、明らかに広告の効果は以前より低減しています。広告予算を増やして投下量を2倍にしたところで、広告が効くようになる、モノが売れるようになるわけでもありません。かなり単純化してお話ししますが、100ある予算のうち90を広告に10をPRに回しているとしたら、その比率を変えることで、同じ全体予算でも費用対効果がよくなるケースは大いにあると思います。
ちなみに、誤解されやすいのですが、PRはタダでできるものではありません。広告枠を買わないので広告ほどお金はかかりませんが、世の中の流れにうまく乗っかる情報戦略を立てるための専門性が必要で、これはプロフェッショナル性が求められる領域だからです。
──なるほど。今、多くのキャンペーンは広告を中心に設計されているように思います。「広告でモノが売れない」という言葉もありましたが、昨今の業界の課題はどこにあると思われますか?
日本市場はロングセラーブランドが非常に増えており、もう認知度が限界値(Max)まで来てしまっています。「認知度100%ではないにしても、80〜90%の消費者に知られている」というような商品が多くなっているんですね。広告には複数の役割がありますが、中でもやはり認知獲得という役割は大きい。日本は歴史的にマス広告が主流でしたが、それは「全国民に認知されれば売れる」という状況があり、それが最も効果的なやり方だったからです。ですが、そうした広告活動には限界が訪れています。
そこで必要になってくるのが「パーセプション(認識)」の観点です。昨年出版した書籍『パーセプション 市場をつくる新発想』の中にも書きましたが、現代においては認知もさることながら、認識が重要になってきている。たとえば、先ほど触れたロングセラーブランドが昨今ぶつかっている課題を背景に、最近は商品やサービスの世代交代がよく起きています。認知度の高いロングセラーブランドでも、「この商品は親の世代が使うもので、私たちのものではない」と認識されていたら売れません。私も「若年層、Z世代の新規顧客を獲得したい」というご相談をよく受けますが、いずれもパーセプションに問題があるケースがほとんどです。
ただ、パーセプションはお客様が結果的に持つものですから、企業が一方的に「うちの商品は若い世代のものなんです」と発信したところで、パーセプション・チェンジは起こせませんし、しらけてしまいます。広告でパーセプションを変えられないということはありませんが、やはりPRを戦略的に組み込んで自然な形で情報を発信し、素地、環境を作ってから広告を展開するほうが成功すると思います。
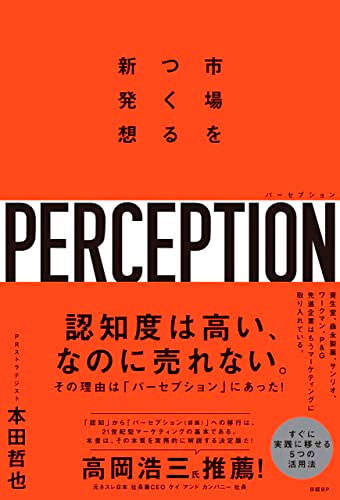
必要なのは「完璧なメディアプラン」ではない
──ここまで、統合マーケティングを設計するときにそもそも必要なPRの視点についてうかがってきました。メディアプランニングにおいて重要なことも教えていただけますか。
一つは、ナラティブ(共創的な物語)を起点に設計することです。我々はいつも、そのキャンペーンでどういうパーセプションチェンジを起こしたいのかということから逆算し、ナラティブを作るところから始めます。たとえば、「古臭いブランドだと思われているから、若返りを図りたい」という目的でキャンペーンを企画するとき、単純に「若者がよく見ている媒体を使おう」と、いきなりメディアから考えるべきではありません。「古臭いブランド」というパーセプションからの変容を起こせるようなナラティブをまず作る必要があります。
その後に、誰が・どこで・どのようにそのナラティブを話すかのスクリプト(脚本)を設計します。ここではかなり概略的にお話ししますが、たとえば、世の中の関心事を踏まえた硬派な話は、社会性のあるメディア(新聞や堅めのビジネスメディア)で、地方の中高年も含めて広く伝えるべき話はテレビで、この話の語り手はこのインフルエンサーが適任なのでは、といった感じで組み立てます。いわば映画やドラマのように、登場人物とセリフ、場面(メディア)を設定していくイメージです。もちろん、ここにはPRだけでなく、広告的なアプローチも含まれます。メディアでの話題化を受け、しかるべきタイミングでブランド発信のステートメントを出すときなどは広告が向いています。
もう一つ、メディアプランニングにおける絶対的な最適解は、もはや存在しないと思っています。メディアプランを決めきることより、重要なのはフレキシブルな対応力です。たしかに、昔はメディアプランの方程式のようなものがあって、「このメディア予算の配分で、このくらいのリーチが見込める」といったデータで判断することが多かった。ですが、昨今は不確実性が高く、多くの場合思いどおりにいきません。いったんはメディアプランも立てますが、メディアを用いて“発話”を促していく中で、状況を見て「やはりこう変えましょう」と判断できる能力や経験が、今求められていると思います。



































