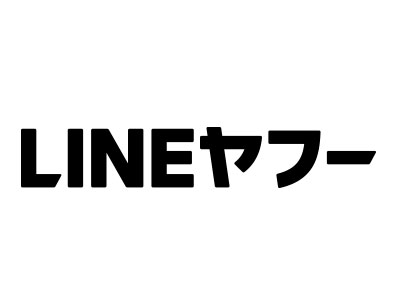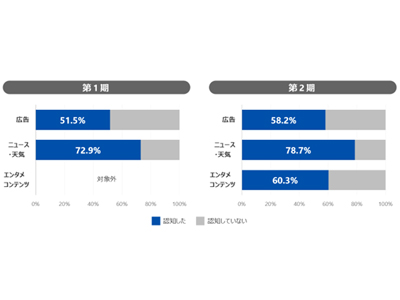成功体験を経たマーケターが陥りがちな思考
「人は知らない人からよりも、知っている人からのほうが商品を買いやすいのだと気づきました。今思えばあたり前のことなのですが、当時は近視眼的になりすぎていた自身を反省しました」(三浦)
モノを売るのではなくコトを売る──商売に携わる者であれば一度は聞いたことのある言葉かもしれないが、切羽詰まったり細かな作業やノルマに追われたりしていると、どうしても忘れてしまいがちだ。
マーケティングによって多少でも成果を上げられると「消費者の意思決定を操作できる」と勘違いすることがある。しかしそれは明らかに誤った解釈であり、危険で傲慢な姿勢だ。マーケティング担当者がどのような施策を講じようと、消費者は常に最終的な意思決定のレバーを自分自身で握っているからだ。我々はまだ買い物をするかどうかわからない消費者と何らかのつながりを確保し、意思決定時の最初の選択肢に入ることを目指すほかない。
消費者の最初の選択肢に入るためには、三浦さんのように特定のカテゴリーで悩み相談に乗るなど、様々なアプローチが考えられるだろう。そのアプローチにこそ各企業の独自性が表れると筆者は思う。
この一件以来、三浦さんは会員・非会員双方に対して商品を売り込むのではなく「積極的にコミュニケーションを取るにはどうすれば良いのか」を考え続けたという。会話の量が増えれば、売上も増加する手応えがあったからだ。その考えがLINEを通じた即レスのコミュニケーションにつながっていく。

三浦さんの返信は一般的なECサイトの問い合わせ対応と異なり、相手との距離が非常に近い。友人とやりとりしている際のトーンを思わせる。現代で最も普及しているコミュニケーションツールがLINEだとすると、この距離の近さとウェットさが自然に受け入れられるのかもしれない。
12のコミュニティを機能させる二つの掟
コミュニケーションの重要性を理解した三浦さんは、ダイエットにまつわる複数のLINEコミュニティを立ち上げ始めた。ダイエット時に飲めるお酒を相談するコミュニティや、食事制限に関するコミュニティ、ケトジェニックダイエットを頑張るためのコミュニティなど、様々な手法・思想・流派ごとにコミュニティを分けて運用しているのだ。取材時点で12のコミュニティが存在していた。

三浦さんはコミュニティを運営するにあたり、次の2点を徹底しているそうだ。
1. コミュニティ内では自社の商品ばかり投稿しない
2. ポジショントークをしない
これらは各トピックに関心のあるメンバーが集い、悩みを解決する場としてコミュニティを機能させるための掟と言える。三浦さんは管理人として日々パトロールを行い、科学的に誤った見解を示す投稿に補足をしたり、“荒らし”をBAN(追放)したりしながら、コミュニティの健全化・活性化を心がけている。
「コミュニティの運営を始めてから、人々がコミュニケーションを求めていることがわかりました。コミュニティ内で会員と非会員が相互に教え合ったり、会員が非会員に過去投稿のリンクを送ったり。適切なお節介が毎日のように発生しています」(三浦)
コミュニティを運営した結果、非会員の初回購入を促進できただけでなく、既存会員のLTVも大きく引き上がったそうだ。なお、現在ミラウタクヤ商店には年間購入額5万円以上の顧客が1,000人以上おり、商材平均単価は約3,000円。2022年の全顧客の年間LTVは2万円を超えているというから驚きである。