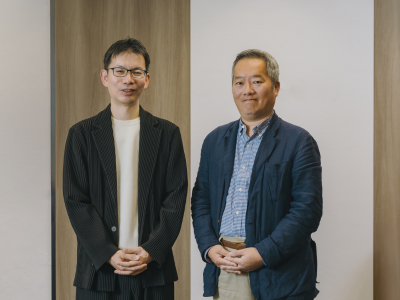Meta広告の新ルール、クリエイティブの「類似度」とは
MarkeZine:オプトのMetaパフォーマンス室については、前編で詳しく紹介いただきました。後編では、Meta広告のクリエイティブ運用について、Metaパフォーマンス室が導き出している現在の最適解を教えていただこうと思います。
さて、Metaパフォーマンス室は「クリエイティブ・ファーストな運用組織」を掲げています。そもそも、「クリエイティブ」にこだわる理由から教えていただけますか?
西森:ずばり、Meta広告の効果改善は、クリエイティブが最も大きなレバレッジとなっているからです。管理画面での設定調整も重要ですが、日々の細かな調整よりも、クリエイティブの差し替えのほうが効果に与えるインパクトが大きいと実感しています。

ただし、これは二者択一ではなく、両方を重視することが前提です。専門性を持った運用者が最適なクリエイティブのPDCAを回すことで、具体的な手応えを感じながら、継続的な運用を実現することができます。
MarkeZine:なるほど。最近、クリエイティブのPDCAが難しくなったという声をよく聞くのですが、これにはどういった背景があるのでしょうか?
西森:たしかに、クリエイティブ運用はますます複雑化しています。これには大きく2つの理由があると考えています。
まず、従来の方法では、ユーザーの興味を惹くコンテンツを継続的に提供することが難しくなっているというのが1つ目の理由です。
近年、SNSではショート動画など大量のコンテンツを短時間で消費する傾向が顕著になっています。特に、機械学習を活用したレコメンデーションの作用が強く、InstagramでもTikTokでも、ユーザーの興味に合致したコンテンツが次々に途切れることなく表示されますよね。結果、広告がユーザーの関心を獲得するためには、膨大なコンテンツの中でも際立つインパクトが必要不可欠となっています。
そのような中、MetaはAI技術を活用し、すべてのクリエイティブの類似度」を判定し、各クリエイティブの「ユーザー反応率」を予測していると言われています。その結果をもとに広告配信が行われており、AIに「類似している」と判定された広告クリエイティブは、その時点で配信量が制限されてしまうようです。これがクリエイティブ運用が難しくなっている2つ目の理由です。

MarkeZine:広告効果の高いクリエイティブに微調整を加え、鮮度を上げつつ、配信を続けるというのがクリエイティブ運用の一般的な手法でしたが、それも「類似度」の問題で通用しなくなっている可能性があるんですね。
西森:はい。どんなに多くのクリエイティブを制作しても、長時間かけてコンセプトを練り上げても、類似度次第で表示される機会すら失われてしまいます。