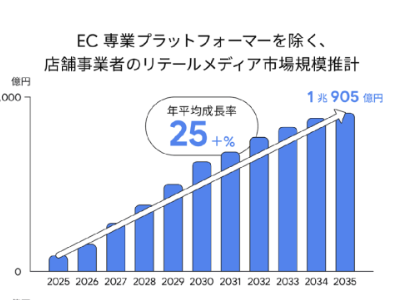サッポロビールのマーケティングにおけるテレビの役割とは?
━━広告やマーケティングの世界ではかなり前から「消費者のテレビ離れ」が叫ばれています。そうしたなか、サッポロビールのマーケティング戦略では、地上波やコネクテッドテレビなどを含めてテレビというメディアの役割をどう捉えているのでしょうか。

仰る通り、テレビ離れが叫ばれて久しいという事実はあるのですが、一方で「幅広い層のお客様とコミュニケーションが取れる大きな媒体」という点は変わらないと考えています。
とはいえ、テレビCMは「視聴したからといって、お客様がすぐトライアルする」媒体ではありません。特に当社の場合、即購買を促すようなテレビコミュニケーションを行っていないので、その傾向はより強いと思います。
「購買に直結させたい」というより、むしろ「お客様がビール売り場を訪れた時にブランドを思い出していただけるようにしたい」という思いを実現する媒体であり、継続的に情報を届けたりコミュニケーションしたりする手段として重要な存在と捉えています。
━━CMが「継続的なコミュニケーション手段」だとすると、トライアルや購買につながるような施策を他に展開しているのでしょうか。
当社のビールマーケティングでは「体験」と「広告」という2軸を重要視しています。体験とは、実際に美味しい生ビールを味わっていただくような取り組みのことです。その場でグッと味わっていただき、好きになって、そしてトライアルにつなげていく即時性のある施策です。
一方の広告、特にテレビCMの場合は「じわじわとお客様とつながり続けるもの」というイメージです。たとえば、当社のCM「大人エレベーター」シリーズの場合、「このビールがうまい」という表現は出てきません。サッポロ生ビール黒ラベル(以下、「黒ラベル」)の世界観や、CMに出演いただいている著名人の言葉や考え方に共感を促すものであり、ゆっくりとコミュニケーションを醸成していく役割だと考えています。
ゲストの価値観から共感を生む「大人エレベーター」
━━今お話しいただいた「大人エレベーター」シリーズは、黒ラベルのCMとして広く知られています。仰るように製品を直接訴求するCMとは一線を画しているシリーズだと思うのですが、このCM施策の概要も教えていただけますか。
「大人エレベーター」シリーズがスタートしたのは2010年、黒ラベルとして「大人の☆生」というテーマを掲げた時でした。スタート時から現在までずっと妻夫木聡さんにご出演いただき、エレベーターを上って年齢の“階”にいる素敵な大人の方と出会い、対談するというフォーマットを一貫しています。


妻夫木さんは毎回様々な問いかけを行うのですが、共通しているのは「大人とは?」という問いで、その回答を通してゲストの方の価値観や人となりに触れていくというコミュニケーションになっています。
━━なぜ「大人とは?」という問いが共通しているのですか?
黒ラベルは「ビールをたしなむ大人の方々に満足していただけるブランドでありたい」ということを目指しているので、「大人」というのがキーメッセージの中核となっています。「大人」という言葉を大事にして展開しているコミュニケーションなんですね。
つまり多種多様なものの考え方や自分なりの生き方、価値観を持った素敵な大人たちと出会い、そして最後に出てくる「丸くなるな、☆星になれ。」というブランドメッセージに落ちていくように設計しています。
━━CMを通じてゲストの価値観に触れることで、「大人という定義は様々だけど、こんな素敵な考え方があるな」と共感を呼ぶイメージでしょうか。
そうですね。「大人とは」と聞かれた時、見ている方が「自分だったらどう答えるかな」と、振り返って考えていただくようなことができたら良いなと思っています。
黒ラベルは大人エレベーターを通して「大人とは」と疑問を投げかけてはいるのですが、「こうである」というアンサーを実は出していないんです。「自分だったらどうだろう」「自分はどういうものの考え方をしているんだろう」というところまで感じていただければ一番嬉しいなと思います。
━━「大人エレベーター」は2010年からCMのフォーマットは変えずに続けているとのことですが、時代に合わせてチューニングしてきた部分はあるのでしょうか。
フォーマットは変わりませんが、変わっているとすると最も大きいのはキャスティングだと思います。