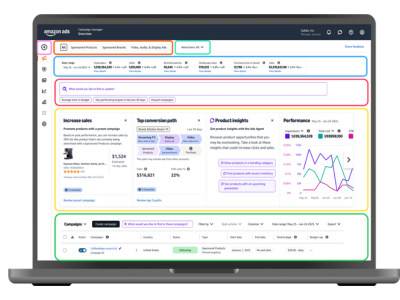BtoBマーケティングは「顧客理解の壁」が厚い
田岡:今日はよろしくお願いします。はじめに、BtoBマーケティング領域における関口さんのこれまでの取り組みについてお聞かせください。
関口:新卒で就職した日立製作所から前職の半導体メーカーまで、一貫してBtoBのデジタルマーケティングに携わってきました。

デジタルカスタマーエクスペリエンス エグゼクティブ/統括部長、
(兼)現場ソリューションカンパニー ヴァイスプレジデント(マーケティング戦略)、
(兼)回路形成プロセス事業部 事業部長付 関口昭如氏
キャリア初期は、完成したプロダクトのプロモーションが中心だったのですが、経験を積むうちに、顧客のニーズを起点に事業全体を構築したいと考えるようになりました。現在、パナソニック コネクトでは「誰に対し(Who)、何を(What)、なぜ(Why)訴求するのか」を軸に、マーケティング以外のチームも含め関係者で戦略を共有するプロセスの設計を推進しています。
田岡:関口さんとはMarkeZine Day Kansaiでお会いしまして、顧客理解を深めるインタビューで「新しいカテゴリーの種を探すこと」を意識されているとお聞きし、ぜひ詳細を伺いたいと今日の対談をオファーしました。たしかに、カテゴリー戦略でもまずはじめに「Who・What」を設計します。その第一歩として顧客理解が必要になりますが、結局ここが一番難しいところでもあります。

関口:そうですね。私も顧客理解の難しさは常に感じています。というのも、クライアントから営業担当に直接伝えられることは、真実の一端に過ぎないからです。
たとえば、仮に失注してしまったとしましょう。お客様から失注理由として「本当は契約したかったのですが、私はいいと思ったのですが予算の都合で他社製品に決めました。今回は見送ります」のように言われることがあります。ですが、実際には社内の利害関係が働いていたり、自治体からの補助金のタイミングを見計らっていたりと、表からは見えない事情が絡んでいることが少なくありません。
田岡:BtoBの場合、会社同士の関係もあって、本音を言いにくい部分がありますからね。
関口:おっしゃる通りです。加えて、顧客企業も一枚岩ではありません。現場部門は定常業務の効率化を重視する、経営層はもっと俯瞰の視点で費用対効果を計算する、といった具合に内部でもニーズが分かれているのが一般的です。つまり、窓口の担当者の言葉を受け身で聞くだけでは、顧客理解に限界があるんですよね。
田岡:伺ったような課題感も踏まえ、パナソニック コネクトのBtoBマーケティングでは、顧客インタビューに注力されているとお聞きしました。
関口:はい。2024年だけで80回ほどN1インタビューを実施しました。特定の顧客1人を深く分析するN1分析は、もともとBtoCでメジャーな手法ですが、私は「むしろBtoBでこそ有効なのでは?」と考えています。