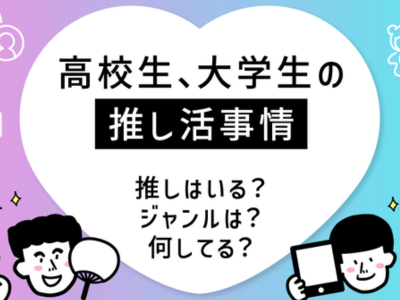この記事は、日本マーケティング学会発行の『マーケティングジャーナル』Vol.45, No.4の巻頭言を、加筆・修正したものです。
世の中に浸透し続ける生成AI
まず、2025年の「TED」でのGoogle元CEOエリック・シュミットとテクノロジストのビラワル・シドゥの対談をご覧ください。生成AIの急激な発展と普及、それから今日的な課題を知ることができます。
シュミット氏は、2016年にコンピューター囲碁プログラム「AlphaGo」がトップ囲碁棋士に勝利した時、これから何が起こるのかはよくわかっていなかったと述べています。言うまでもなく、AlphaGoからコロナ禍を挟み10年経たずして、生成AIが登場しました。
2022年、OpenAIのChatGPTが大きな話題になったことを覚えている方も多いはずです。ChatGPTは瞬く間に我々の日常に浸透し、今や多くの生成AIサービスが競合しています。それとともに、レポート作成で生成AIを使うことは当たり前になり、会話するように検索をするようになり、話し相手にもなってくれます。ビジネスの現場でも、アイデアを複数提案し、会議の議事録を一瞬でまとめ、コードを修正・作成して実行できるようになりました。「人間の仕事がなくなる」とさえ言われるようになっています。
重要な点として、現実には、新しい技術がどのように社会に浸透し、定着していくのかについては議論の余地があります。当初の期待がそのまま社会を形作るわけではありません。コンピューターも登場した当初は高級な計算機とされ、文章を清書するワープロの一つだと考えられていました。インターネットもまた、ビル・ゲイツやスティーブ・ジョブズですら、コンピューターにとっての付随的なサービスにすぎないと考えていたことがあります。生成AIも、ある時は単なる「強い棋士」だったかもしれません。生成AIがこれからどのような姿になるのかは、ひとえに私たちの社会の実践の中にあります。
ビジネス現場における生成AIの現在地とは
今回のマーケティングジャーナルの特集が示しているのは、こうした社会の実践の一つです。
ビジネスの現場において、生成AIはどのように捉えられ、またどのように用いられ始めているのでしょうか。さらに、どのような可能性を想定されているのでしょうか。一般の消費者はどうでしょうか。生成AIをどのように捉え、またどのように理解し、どのように対応しているのでしょうか。そして研究者は、生成AIをどのような研究対象として捉え、どのような可能性に注目しているのでしょうか。
本特集では、5つの論考を通じて、生成AIの可能性を考えています。次からは、それぞれの概要を紹介しましょう。