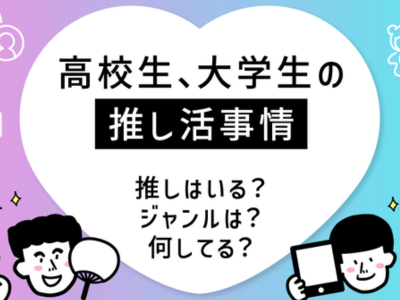会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
新規会員登録無料のご案内
- ・全ての過去記事が閲覧できます
※プレミアム記事(有料)は除く - ・会員限定メルマガを受信できます
- ・翔泳社の本が買える!500円分のポイントをプレゼント
この記事は参考になりましたか?
- 関連リンク
- COLUMN連載記事一覧
-
- Z世代とY世代、時代の変化を比較 「合理的すぎる若者像」と体験・効率・安心重視の消費行動を...
- 成果を出す「企業ブランディング」の実行戦略:KPI設定、広告効果、PDCAの「3つの壁」を...
- 企業に透明性が求められ「共感」が資産になる時代、企業はUGC(口コミ)とどう向き合うべきか...
- この記事の著者
-

河村 実咲(カワムラ ミサキ)
野村総合研究所 コンサルティング事業本部 マーケティング戦略コンサルティング部 コンサルタント
2023年に早稲田大学を卒業後、野村総合研究所へ入社。消費者データ分析を基盤とした民間企業のブランディング・プロモーション戦略策定から、官公庁の広報戦略・実行支援まで、官民を横断し多様なコンサルティングを手掛ける。<...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
-

中田 壮星(ナカタ マサトシ)
野村総合研究所 コンサルティング事業本部 マーケティング戦略コンサルティング部 エキスパートコンサルタント
2017年に東京工業大学大学院終了後、野村総合研究所に入社。マーケティング・プロモーション領域を中心に、官民で多数のコンサルティング経験を有する。生活者・消費者トレンドや、顧客社内外の消費者データをもとに...
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
この記事は参考になりましたか?
この記事をシェア