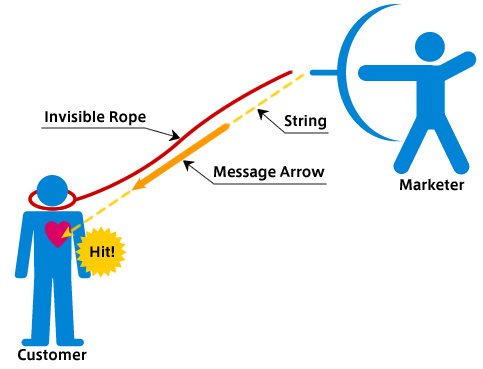DRM=「ヒモの付いた見えない矢」
では、DRMの世界においてこの二つを区分けしてみましょう。まず、前ページの3つの「ダイレクト」性から導かれる結論が2つあります。
[B]対象者からのレスポンスが「ダイレクト」
さて、今まではどちらかというと[A]の世界観で話をしていました。こちらはデータベース・マーケティングの範疇と重なる領域であり、対象者=「顧客(Customer)」を中心に据えた見方です。
この視点でのDRMでは、「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」という論理はあり得ません。例えて言えば映画の特殊撮影で的に向かって目に見えないロープを張り、それを伝ってヒモの付いた矢を飛ばすようなもの。当然対象者に刺さるわけです。実は、[A]側面でのDRMの神髄はこの「ヒモの付いた見えないロープ」なのです。
これに対して[B]は、機能と役割を中心に据えた見方です。こちらの世界におけるDRMは、フロー自体が受注(もしくは登録)する機能を備えているか、またはそこに直結させるシステムを持っていることが前提となります。つまり、直接レスポンスを得られるフローであることが重要なのです。
ですから、[B]の対象は必ずしも「顧客」とは限りません。新聞や雑誌、TVといったメディアで不特定多数に訴求してアクションを起こさせればいいのですから、対象者=「消費者(Consumer)」ということになります。
ここで疑問。「それは申し込み機能の付いたマス広告とどこが違うの?」「市場からのレスポンスを期待するという意味では、SP広告と同じじゃないか?」…、正直なところ、そのボーダーは非常に漠然とした領域です。次ページでは、この点について考えてみましょう。