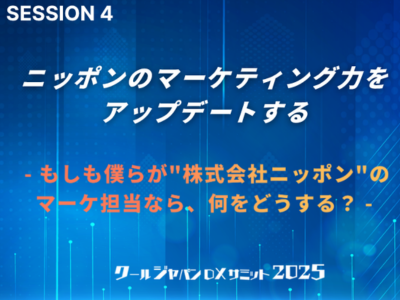ブランドもまた、Facebook上でのソーシャルグラフの中に存在している
実名登録を前提としているFacebookでは、そのつながりも「会社の部署の先輩の山根さん」「高校の同級生だった工藤さん」「地域のボランティア活動で知り合った神原さん」といったように、ネットだけの関係性ではなく、リアルな社会でのつながりがネット上でも再現されています。
実際に顔を合わせ、人となりを知っている間柄でのネットワークの中で情報がやりとりされていること。しかもそれが、世界で10億人、日本でも1500万人が毎月訪問するというスケールで具現化されているということ。これこそが、従来のネット上のコミュニティでは存在しなかった、Facebookだけが提供している価値なのです。
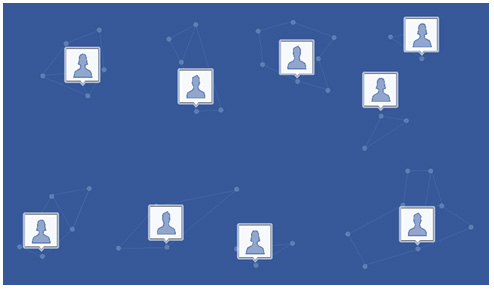
Facebookのような、リアルな間柄に基づいて形成されるつながりをソーシャルグラフと呼びます。ソーシャル、つまり社会の中での人としてのつながりをインターネット上でも再現している、というわけです。
実生活で知っている人とインターネットでもつながり、自分にとって居心地のいい範囲内でのみ情報をやりとりすることが可能になったことで、より多くの人が日常のパーソナルなできごとや自分の感情を共有するようになっています。これは、日本だけでなく、北米やヨーロッパ諸国でも同じです。アメリカでも、Facebook以前は、大勢の普通のインターネットユーザーにとって、自分の日常生活をネット上で公開することには大きな心理的なハードルが存在していたのです。それが、Facebookの出現によって変化したのです。
この事実がマーケッターにとって意味することはというと、生活者が自分たちの行為を、自分を核としたグループに向かって共有をしていて、その共有された情報は知っている人から知っている人へ、実名制のネットワーク上で拡散する可能性を持っているということです。そこで共有される行為には当然、彼らの「何を購入した」「このお店に出かけた」「食べてみてどんな味だった」といった消費行為も含まれます。
Facebook上で再現される人と人のソーシャルグラフの中には、その個人にとって関係性のあるブランドやお店などのビジネスも存在しています。こうした時に、ビジネスが主体的にそのネットワークの中でコミュニケーション活動を行うことの重要性は、あらためて言うまでもないでしょう。
企業が、ブランドが、Facebook上で情報を発信していく上での核となる場所が、Facebookページです。個人と個人がつながるのと同じように、企業のFacebookページは「いいね!」をしてくれた人と、つながることができるのです。そうした「ファン」とブランドの交流、つまりコメントであったり、情報のシェアであったり、店舗へのチェックインなどのアクションは、Facebook上でつながっているファンの友だちへ、そしてその先の友だちへと伝播していくのです。