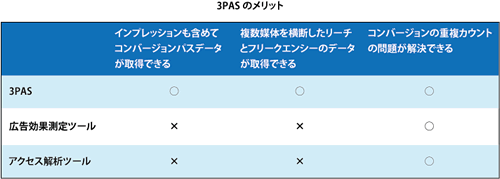アトリビューションと3PASの関係
このコンバージョンパスデータは、アトリビューションの初期のころはクリックだけの経路を扱っていました。広告をクリックした履歴のデータをコンバージョンに至るまでクッキーでトラックし分析していたのです。
その後しばらくして、クリックだけではなくインプレッションも対象に分析したいというニーズが高まっていきます。ここで第三者配信アドサーバー(Third Party Ad Serving:3PAS=スリーパス)が脚光を浴びることになります。この3PASについてはこの「アドテクノロジー基礎講座」の第1回でも説明されていますので、そちらも参照してください。

3PASを使ってバナー広告を配信すると、クリックだけではなくインプレッションも含めてコンバージョンパスデータを取得することができます。複数の媒体への広告配信をひとつのシステムでおこなうため、複数媒体を横断したフリークエンシー(接触回数)の把握も可能になります。フリークエンシーとは、一人のユーザーに広告が何回接触しているか、あるいは、何回露出しているかのことです。
バナー広告の場合、フリークエンシーはユーザー単位でのインプレッション回数になります。複数媒体を横断したフリークエンシーが分かるので、その結果として、複数媒体の重複リーチについてもデータが取得できるようになります。
たとえば、媒体社側のレポートでインプレッションが100回の場合、それだけでは100人に1回ずつ表示されているのか、1人に100回表示されているのか分かりません。さらに、ひとつの媒体ではなく複数の媒体を使って広告配信していると、それらが1人のユーザーに重複してリーチしているのかどうかも媒体社側のレポートでは分からないのです。これは、アクセス解析ツールや広告効果測定ツールでも同様です。
アトリビューションの普及に伴い、3PASが業界のトレンドに
3PASは、実は10年以上前から存在していましたが、アトリビューションの普及に伴って業界トレンドになってきました。アトリビューション視点でみたときの3PASのメリットは、(1)インプレッションも含めてコンバージョンパスデータが取得できる、(2)複数媒体を横断したリーチとフリークエンシーのデータが取得できる、(3)コンバージョンの重複カウントの問題が解決できる、3つが挙げられます。
インターネット広告のアトリビューションという観点では、3PASがアクセス解析ツールや広告効果測定ツールよりも優れているということになります。しかし、もちろん、サイトの解析をする場合などは、アクセス解析ツールの方が優れています。用途によって使い分けなければなりません。また、最近は、3PASとアクセス解析ツールなどを連携することによって、広告配信のインプレッションから広告のクリック、そして広告主企業サイトへのアクセス後のユーザーの動きも一気通貫でトラッキングできるようになってきています。
また3PASでの配信ができない広告メニューもあります。いわゆる、純広告やリスティング広告などです。これらも、クリックトラッキングやインプレッショントラッキングをおこなうことによって、オンライン広告の配信についてはほぼすべて3PASでデータを集約することが可能になります。
そしてオンライン広告以外の、たとえば、自然検索経由やSNS経由、コンテンツサイト経由などもリファラー情報から判別することができます。そのため、ほぼすべての流入に3PASは対応することができるのです(具体的には個々のツールによって異なります)。

オンライン上のほぼすべての流入が捕捉できるため、いわゆる、カスタマー・ジャーニーといわれるユーザーの動線が可視化されるのです。カスタマー・ジャーニーとは、ユーザーがコンバージョンに至るまでの経路のことです。コンバージョンパスデータのなかに、カスタマー・ジャーニーの情報が含まれています。コンバージョンの直前のラストクリックだけではなく、そこに至る一連のユーザーの動きを把握・分析することによって、より効率的に広告投下をおこなっていくことができるようになります。
つまり、Attention(注意)→ Interest(興味・関心)を引き起こしている広告を把握し、Search(検索)→ Action(行動)→ Share(共有)の流れをマケーターの意図で、ある程度、作り出すことができるようになるのです。これによって、ラストクリックだけの評価で陥りがちな縮小最適化の課題解決にもつなげることができるのです。
今回は広告効果測定ツールの役割から、ラストクリック偏重問題、アトリビューションの概念の登場、3PASが注目されるようになった背景、そしてカスタマージャーニーまで、一連の流れで解説しました。順を追って説明したので、それぞれの概念のつながりが理解できたかと思います。次回は、オンラインアトリビューションのについて、具体的事例を取り上げながら説明していきます。