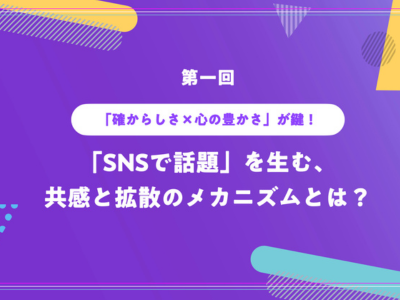アートとイラストレーションの違いとは何でしょうか? 「いま」を象徴するイラストレーター150人が共演した『ILLUSTRATION 2016』に作品が掲載されている作家のお一人、大槻香奈さんはそれを自己表現か人に向けたものかという違いだとおっしゃいます。
翔泳社では本書の刊行を記念し、大槻さんにインタビューをお願いしました。前編は11月18日(水)に公開。今回は、その後編をお送りします。
イラストレーターはみずから仕事を作り出せるか?
大槻:個人的にも、イラストレーターは受け身の人が多い気がします。本来はそれが正しいのかもしれませんが、もっとこういうことをしたら面白いんじゃないか、という議論をしたり自分から行動したりする人が増えれば、すごく面白いことになりそうですよね。
――自分で仕事を作るということですね。
大槻:それはけっこう大事になると思います。みんな普通にうまく絵が描けるんですよ。でも、うまさはある程度に達するとそれ以上にはいかないんですよ。私は絵がうまいことに対して面白さは感じません。「うわぁ、すごいなぁ」という感動ではなく、「この人、ほんとに勉強頑張ったんだなぁ」という努力を評価する感じになってしまいます。もちろん上手であることは重要なのですが、イラストレーションは、描いた人が自分の絵を使っていったい何をしたいのか、というところに魅力を感じます。
なので、イラストレーションの本来の意味を確認し直す作業が必要だと思っています。道路の標識も情報を伝達するために使われている絵という意味ではイラストレーションと言えるかもしれない。そういうところから考えて、では自分の作品だったらどういう効果をもたらすことができるか、と考えていくと、何かいいアイデアを思いつくかもしれません。
私はどうしてもアート色が強くて、美術作品として作ったら面白いんじゃないかという発想は出るんですが、イラストレーションとして面白かったり新しかったりする発想とは考え方がちょっと違うんです。
美術作家でありイラストレーターでもあるという見方をされることが多いんですが、実際そうだとしても、私はどちらの世界にもどっぷり浸かれないタイプなんです。イラストレーションとアートは、私の中ではまったく別物で、イラストレーションにはイラストレーションとしてのあり方があり、アートにはアートであります。イラストレーションの表現を安易にアートに持ってきただけで評価されるみたいなのはなんだか違う気もしますし、そういうのは好きではありません。その線引きははっきり区別しているつもりですが、なかなか伝わらないですよね。
見る側の人がそういう感想を抱くのは、可能性を感じてくれていると思うので嬉しいんですが、同じ業界の人に言われると不安になってきます。「いちおう使い分けてんねんけどな……」と。
イラストレーションは一瞬のインパクトが勝負
――ほかにもイラストレーションとアートでは届き方、流通がまったく異なりますよね。イラストレーションは基本的に大量生産でお店に並んでいて、アートは一点もので展覧会で飾られます。大槻さんとしては、流通という面で何か意識していることはありますか?
大槻:例えば本では書店に並びますよね。そこではほかの商品もたくさんあって、その中に自分の絵があることになります。そういう場面では、見かけた人に「あれ、これはちょっと違うぞ」と思われるような絵を描くように意識しています。
特に色と構図は考えます。本だとミステリー小説の表紙の仕事が多くて、ちょっと暗くて怖い感じでと依頼されます。けど、書店のミステリーのコーナーに置かれると、ほかの本も暗いから埋もれちゃうんですよね(笑)。そこで埋もれないためにあえてピンクなどの明るい色を使うんです。小林泰三さんの『幸せスイッチ』(2015年、光文社)や降田天さんの『女王はかえらない』(2015年、宝島社)がそれです。明るいピンクなんですが、よく見ると気持ち悪いという感じです。なるべく埋もれないようにするのは大事にしていて、なおかつ世界観を崩さないように気をつけています。


『S.N.S』のジャケットも青色にこだわって、青空ほど爽やかではないけど暗い印象を与えず、けれどあったかみはそれほどなくて冷たいわけでもない、という繊細なバランスの青色を選びました。その青色が印象に残るように人物の色を変えました。

美術作品はその前で長時間考えるものだと思うんですよ。もしかしたら何時間、何日、何年も。でも、イラストレーションは一瞬のインパクトが勝負です。お店で流し見しているときに、「あれ」と立ち止まってもらわないといけないので、ある程度はあざとくていいのかなと。ちょっとした違和感を植えつけることを考えています。
なので、イラストレーションに関しては、買った人がなぜその商品を買ったのか自分でもよく分からないという作り方をしようと意識しています。思わず買ってしまったというのを狙いたいんです。表紙買いですね。好きだからとか、私のことを知っているからとかではなくて、「よく分からんけど買ってしまった」となればいいですね。
――そうなったらすごすぎます(笑)。
大槻:洗脳みたいに(笑)。それは狙ってできることはではないかもしれませんが、そういうことを考えて作っているのは事実ですね。
――本だと書店で表紙が見えるように平積みされるのは新刊のときか、売れているときだけですから、一瞬のインパクトは本当に重要ですよね。見ただけで買われるようになったらもはや神業です。
大槻:あと、イラストレーターとしてやりたいのはデザイナーとのコラボレーションです。今年に入ってから、デザイナーさんが堂々と絵をいじってくれるようになりました。顔の上に文字が載ったり、アップされたり、色を変えられたり、原画をそのまま使うのではない工夫が楽しみになってきました。いい意味で、自分の作品を大事にされていないところがいいですね。
デザイナーさんの手によって、もっと絵の原型がなくなっても面白いかもしれないです。今後長く仕事を続けるなら、原画に忠実である必要はなくてもいいんじゃないかと思います。
いい形でお金を稼ぎ、作品を手放すまでが作家の仕事
――作品を売ることについてはどうお考えですか? 昔は作品を売りたくないと書かれていましたが、いまでは「いい形でお金を稼いで回すこと」を強調されているように思います。
大槻:それも震災がきっかけですね。震災を機に、自分がどれだけ人の役に立ってきたのかと考えたんです。さっきも話しましたが、自分のために絵を描いてきて、人のためには描いてきませんでした。だから、作品を売ることで誰かに恩返しをするといったことまで頭が回っていなかったんです。
お金を回すというのは大事なことです。いまはもうあまりないんですが、絵描きはお金のことを考えるなという空気がほんの数年前までありました。「売るぞ!」という感じだと反感を受けたという状況です。
――村上隆さんが業界のそういう風潮を嘆いていらしたのを覚えています。
大槻:その流れもあったかもしれません。お金を稼ぐことが悪いというのは違うだろうと思います。自分で作ったものでちゃんとお金をいただかないと、結局は埋もれていって描かなくなるんですよね。現実に今回の個展でも馬鹿みたいにお金を使っているんですよ。そのお金をどこから出すんだという話ですね。それはやっぱり、いままでの個展で買ってくださった方のおかげで、会場の演出にお金を使うことができたんです。いいものを作れば喜ばれるので、そういったいい循環を維持したいんです。
いいものを作ってほしいと思う人がいる、自分も作りたい、いいものを見たいから作品を買う、そのお金を次の制作費に充てる。この流れができてきて、「これが作家活動なのか」とやっと分かってきたところがあります(笑)。いまはそれがぎりぎりの状態で回っていて余裕がないんですが、この輪を大きくしていきたいんです。自分の個展だけでなく、企画したい展覧会がいっぱいあるんですよ。そういうところにお金を回せるようになったら、もっとハッピーになる人が増えるんじゃないかと思います。
自分が活動していて実感するのは、日本はまだまだアートが元気ではないし、受け入れられてもいないということです。ただ、数年前と比べると自分自身の状況はよくなっているので、ここで諦めないで、頑張って押し広げていこうと考えています。続けていくしかないんですけどね。
だから、次に繋げるために、作るだけでなくてちゃんと売りたいんです。作品を作っているときに、手放すことの意味をすごく考えます。作って終わりではなくて、手放すところまでが仕事です。今回の個展で売れなかったら、けっこう引きずると思います(笑)。手放すつもりで描いていたので、それが自分の家に舞い戻ってくるのはすごく心苦しいというか、先の夢が絶たれてしまうので……。
作品をお手に取っていただくというのは、作品を生きたものにすることだと思います。仮に私の制作意思を忘れてしまっても、作品が手元に残っていればその人の中で別の意味を持って生き続けるものになります。そうなってこそ、作品は役割を果たすことになると思うんです。会場を飛び出して、その人の日常の思い出になることがとても大事だと思います。「個展に来ていろいろ感じることがあってよかった」というのも一つの見方ではありますが、自分の作品に関しては、それがゴールではないんですよね。違う意味を持ち始めるのは大事なことです。
今回個展に久々に来られた人がいたんですが、その人は数年前に買った私の絵を部屋に飾っていたら、ある日、一部が鳥の羽に見えてきて、それが女の子の背中から生えているように見えたと言うんです。で、それがすごい大発見だったからとわざわざ教えに来てくださったんです(笑)。そういうのはとても嬉しいですね。
そういったところに絵を売ること、手放すことに意味を感じます。自分がやりたかったことに近い感じがしています。
――やはりお金を出して買ってもらわないとそうはならないですよね。買った人もお金を出したことで意味を見出そうとするはずです。
大槻:お金を出すっていうのは体験なんですよね。コレクターの中では、作品が安いと体験にならないから買わない人がいるんです。「買ってください」とは思うんですが(笑)、いまの価格の2倍以上になったら買うという人もいます。作品の価格を価値に合わせて上げていくのも大事なんです。
――価格の判断は非常に難しそうです。
大槻:それをすごい緊張感の中でやっています(笑)。美術作家として、自分の作品の価値を上げていくのも仕事としてあるんですよ。
――イラストレーションと違って、アートは自分で価値をつけないといけませんからね。本書『ILLUSTRATION 2016』の価格も、需要や競合商品との比較、部数などある意味で外部要素を核にして決められ、それが価値になります。掲載されているイラストレーターの誰かが決めるものではないんですよね。
大槻:本当にそうなんです。いま大学で教えているんですが、若い人はおおよそ受け身姿勢で「評価されたい」と思っていますから、あまり自分からアピールしないんですよ。でも、評価してくれる人なんていません。自分の価値を自分で上げていける人でないと、先には行けないというのは事実としてあるんですよね。
どうしようもなくなったらたこ焼き屋をやる
――自分でつけた価格と価値の理由がきちんと伝わらなくて、見向きもされなくなるかもしれないという怖さはありませんか?
大槻:そうなんですけど、こないだ思ったんですよ。やっぱり、いつでも売れるわけではないですし、いつ貧乏になってもおかしくありません。いまでも、ちょっとでもこけたら大打撃です。だから、本当にやばいと思ったら、絵をすっぱりやめてたこ焼き屋をやろうと。
たこ焼きとか餃子ってみんな買うじゃないですか。人が欲しているものを作るべきっていう考えがいつもどこかにあるので、たこ焼き屋をやって売る。で、パッケージか何かに絵を描くっていう(笑)。ギリギリ絵描きとしての活動から離れてないみたいな……。
本当に無理になったら全然違うことをして、お金がなくて展覧会ができなくなったという事実さえも何か作品にして乗り越えていこうと思っています。最終手段として絵にこだわる必要はあまりなく、社会のために何かをしようとは考えているので、作品を作って評価されないんだったら絵でなくてもいいのかなと考えることはあります。
――アートから食というのは180度違いますから、その発想にいってしまうのは面白いですね。
大槻:知り合いがアートフェア東京に参加して、お客さんが入らなかったり売れなかったりしたという話を聞いたら、もうアートフェアで野菜を売ったらいいんじゃないかと考えたこともありました(笑)。アーティストが野菜を作って売ればいいやと。半分は冗談ですが(笑)。
私も売れていない時代が長かったので、生きていくことが一番大事だと思っています。あんまり作品を作ることにこだわりすぎると、生きていくのが困難になりますよね。精神的に辛くなるとゴッホの手紙を読んだりするんですが、弟のテオに「お金を貸してくれ」と書いてあって、それを読むたびに悲しくて、絶対こうならないように頑張らないと……って思うんです(笑)。死なない生き方をしようといつも考えています。
――そこで最終手段がたこ焼き屋なんですね。おいしいものを食べるのが生きがいの人もいますよね。
大槻:たしかに。私もそうなんですよ、最近は仕方なくカップラーメンを食べるのが嫌なんです。自分の好きなものとか、そのとき食べたいものしか口に入れたくない。それってけっこう大事だと思います。食べたいものを食べるというのが生きていく力になるというのは、けっこう実感しています。
――「空虚」という問いかけに対して「食」というのは、答えの一つではないかと感じます。大槻さん、予定を大幅に超えてしまいましたが、長時間のインタビューありがとうございました!
今回、大槻さんのアートやイラストレーションに対するお考えがたいへんよく分かるインタビューとなりました。イラストレーションを仕事にしている方や学んでいる方は、それを踏まえて『ILLUSTRATION 2016』を読んでいただくと、たいへん勉強になるのではないでしょうか。