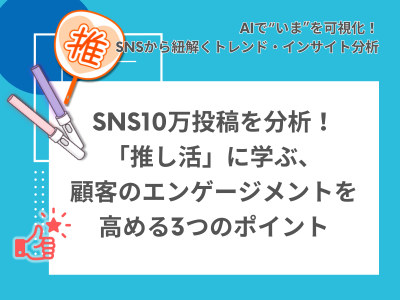コア事業の枠を超えて生活者の変化に寄り添う
――外食や中食も含め、楽しく自分の食事をコーディネートできるのが現代的であり、そんなふうに主導権を持てるよう促しているのですね。そのために、レシピに留まらず、食にまつわるより広いサービスを展開しているのでしょうか。
そうですね。疲れてイチから料理ができない日でも、スーパーのから揚げをちょっとアレンジすると充足感が得られたりします。生活の一部である料理に向き合う以上、私たちは外的環境や生活者のライフスタイルの変化に合わせて提案を変えたり増やしたりして然るべきです。
たとえば最近、お肉の消費量がすごく伸びているんです。理由は、お肉はただ焼いて塩を振れば一品になる、時短食材だから。その選択肢を選ぶ人は必ずしもお肉が食べたいわけではないので、私たちは「生姜焼きならすぐ作れますよ」という提案に加えて、「時短ならお刺身もいいですよ」とか「旬の野菜をゆでるだけでも」という提案をしたいし、その食材の情報や食材自体を届けたりもしたい。そんな幅広さのために、生鮮EC「クックパッドマート」をはじめ、サービスの拡充や新規立ち上げを続けています。
機能的価値と熱量顧客との関係構築の二大要素
――御社の顧客層は、とても広いですよね。一人暮らしを始めた学生でも単身者でも、子育て中の働く親でも「私向けのサービスだ」と思える便利な要素があるように感じています。ともするとターゲットを絞り切れないと思いますが、顧客像をどう捉えて対応しているのですか?
おっしゃるとおり、属性などでのターゲットは設定していません。その上でのユーザーとの関係構築に、不可欠な要素が2つあると思っています。
1つは、機能的価値です。どんなサービスも、何らかの機能的価値がないと使われません。当社では多様なユーザー層を踏まえ、また同じ人でもその日の状況や気分によって様々なニーズがあることも加味して、1つではなく複数の答えを用意しています。忙しいお母さんならレシピの人気順検索で迷う時間を省けますし、別の検索方法はまた別のシーンで役立つ、といった形ですね。
もう1つは、熱量です。私は、サービスには必ず熱量が宿ると思っています。レシピ投稿なら、料理のプロではなく一般の方による自分や家族のためのレシピが「他の誰かにも知ってほしい」という思いとともに投稿されている。そこには少なからず、熱量が加わっています。
――熱量というのは納得です。それがクックパッドというプラットフォームの強みであり、他社が取って代われない要因になっているのですね。
そうであるように、いつも意識していますね。食関連のサービスを訪れる人には、皆さん一定のこだわりがあります。それぞれのこだわりの中で、誰かの「こうするといいよ」という意見が拠り所になって新しいチャレンジが生まれ、熱量が伝播していく。
私たちは、レシピを投稿する皆さんも、「クックパッドマート」の生産者さんも、あるいは「おりょうりえほん」の絵本作家さんもすべて「つくり手」と呼んでいます。つくり手の方々が熱量を持って、新しい楽しみや価値を提供するとき、その一つひとつが唯一無二のコンテンツになります。それらを私たちが勝手に判断したり制約したりすることなく、広い器で受け止めることが、プラットフォームとしてとても大切なことだと思っています。
モノに込められた思いは爆発的に広がっていく
――では、Japan CEOとして特に注力していく事業や領域について教えてください。海外でも既に74ヵ国で事業を展開されていますが、収益の9割近くは日本拠点だそうですね。
はい。日本市場は引き続き重要な拠点です。ただ、注力する事業というお答えは難しいですね。私たちは縦割りで事業を捉えていないので。
あくまでミッションに基づき、その実現に必要なパーツに関して、あらゆることを事業化していきます。レシピや食材、キッチン環境など複数のパーツと、前述のたくさんのつくり手を、よりよい形でマッチングすることが私たちの事業なので、つくり手の方々を刺激できるインフラ作りに包括的に取り組みます。
世の中で成功しているインフラを見ると、たとえばYouTubeは多くの人に映像の楽しみを広げましたし、Uberは利用者に利便性を提供しながら、ドライバーの仕事も増やしています。私たちに置き換えると、それは日々の食を担う人や食に関係するつくり手にとって、本当に価値があり刺激になるインフラを作ることになると思います。
あらゆることを、とお話ししましたが、大きくは3つのテーマを見据えています。1つ目はレシピサービスを中心に長く蓄積しているコンテンツプラットフォームです。料理の楽しみやHow to情報の流通は、引き続き重点項目です。
2つ目に掲げているのは、モノの流通です。「クックパッドマート」を皮切りに模索している新しい領域ですね。情報の流通に比べてモノの流通は圧倒的に難しいですが、それだけマーケットの規模も大きい。それに、たとえば魚の食べ方を教えてもらうより、「僕らが作ったこのしょうゆでぜひお刺身を食べてください」としょうゆ自体を差し出されるほうがぐっときませんか?
思いはモノに乗りやすく、爆発的に普及していきます。そんな思いとともに、モノの流通に向き合っています。
3つ目は、地域や人同士のコミュニティというテーマです。各地の生産者さんと生活者をつなげることもその一環です。また、コロナ禍によって人同士の交流が分断される中で、新しいつながり方や楽しみも生まれているので、その後押しや創出に取り組みます。
――おっしゃるように、2つ目の「モノの流通」は情報流通に比べて関係者も多く、とてもハードルが高いと思います。そこにあえて挑戦されるのですね。
はい。もちろん、コンテンツプラットフォームという基盤の強化が前提ですが、冒頭で申し上げたように、それは土台です。次のフェーズが、料理の領域のインフラの確立であり、そこにモノの流通は不可欠です。
チャレンジングですが、料理の領域で一定のプレゼンスを獲得した私たちだからこそ、モノの流通を含めたインフラ作りに責任があるとも捉えています。同時に、情報の流通に留まっていては、GAFAをはじめ世界的に定着しているプラットフォーマーに肩を並べることはできません。料理という特定領域に特化している分、目線は同じくらい高くしながら料理の領域でできることをやり抜くことが、世界中の人に当たり前に使ってもらえるサービスになるために必要だと思っています。