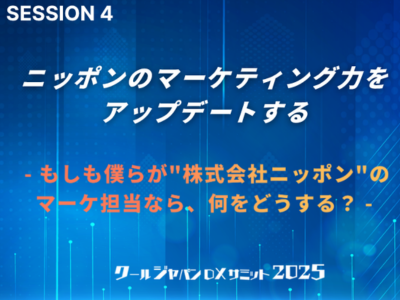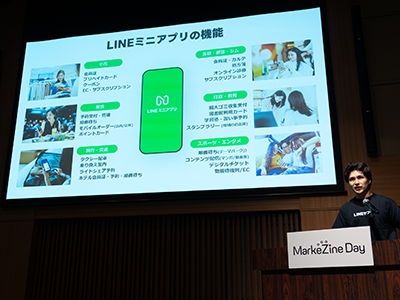価値を作るのは「いかがでしょう」を差し出す姿勢
Bコーポレーションの「B」の語源は、「Benefit(ベネフィット)」の略であるとされている。ここで、日本では使い慣れないこの「ベネフィット」という言葉の意味合いを再定義する。
日本語での「ベネフィット」の単語がもたらす意味合いは、(自分の、自社の)経済活動における「利益」や「得をすること」「恩恵があること」という理解で止まっていた。あるいは、「このベネフィットを提供する代わりに、この商品を購買していただきたい」というような交換条件としての使われ方も見受ける。少し進化した解釈として、「福利厚生」の項目を「ベネフィット」とする用法もあるが、これも従業員から見た「得をすること」の意味の延長だ。
対して、B-Lab社が「Benefit」の概念の理想として掲げている世界は、日本から見れば未開の“新”価値基準を提案している。
「Compete in the World」(世界と比較して、自分が頂点に立とうとするのではなく)
↓
「Best for the World」(世界のために、尽くす頂点への一人で在ろうよ)
「Best for the World(世界に尽くす頂点へ)」の座標がゴールとしてあり、世界の「コミュニティ」に対し、「顧客」「環境」「従業員」に向けて、自らを「ガバナンス(統治)」する姿勢だ。
SDGsと似て非なるのは、「サステナブル」や「エクセレント」な企業となることを国連や国家に向けて証明することが目的でなく、社会に対して「新しい気づき」を提供する姿勢や、最初のきっかけを自社(民間)の基準で差し出すことに価値を置いている点だ。良い会社の証を示す動機で「社会的価値を目指す」と含めてしまうのは、ベネフィットの意味合いとしては小さい枠組みだ。同様に、「ステークホルダーからの理解のため」というサード・パーティーへのリターンの動機や、「自社が儲かるため」というファースト・パーティーな動機も、ベネフィットの意味合いとしては片側で限定的だ。ましてや「Bコーポレーション」の称号を取得するメリット・デメリットは、と論じてしまうと本末転倒になる。
ベネフィットの意味するところは、決して交換を前提とした条件の道具ではなく、「いかがでしょう」という相手への無償の投げかけによる、いわばゼロパーティーの関係者に向けた「姿勢」にある。単なる「お利口さんになりたいから」「品行方正になりたいから」などの回避型の防御ではなく、常に向かう「あり続ける」「能動姿勢」が起点だ。
日本において、多くの企業が採用するスタンダードな認証の例として、「プライバシーマーク制度」や「有機食品の検査認証制度」などの呼応的なガイドラインが存在する。これらに「とりあえずの免罪符」や「やむなき納税」の側面が存在していないだろうか。認証される以前の「いかがでしょう」の起点姿勢こそが、これらのマークを掲げるよりも大きな価値を作る。「ベネフィット」の新概念は、自社の基準を考えるに際し、大きな牽制球を投げてくれる話題としてキャッチしたい。