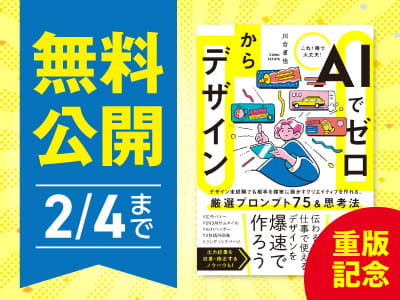35年以上続く販促支援の道のり 現在に見る課題
━━スコープは創業が1989年と歴史があり、広告宣伝・販促に関する企画調査や施策を手掛けていると伺いました。企業の販促戦略、特に販売の現場を基点にした販促戦略の企画・実行に強みがあると思います。そうした販促活動において、特にマーケティング視点から見てどのような課題があるのか教えてください。

新卒で入社後、大手流通企業のチラシ販促や店頭販促、ネットスーパー事業を担当。その後外資系消費財メーカーの担当になり、キャッシュバック施策に携わる。郵便為替や現金郵送などアナログ業務の工数が多いキャッシュバックの課題に気づき、デジタルで送金できるサービス「ウォレッチョ」を立ち上げ。現在はデジタルテクノロジー事業本部ウォレッチョ事業部に所属し、サービス開発からマーケティング領域・営業領域に至るすべてを担当
草刈:販促施策の一つに、私がこれまで携わってきた「キャッシュバック」があります。文字通り、商品を購入いただくと現金が戻ってくるという施策で、注目度も成果も高い施策です。そのため売り場担当の方からも人気の高い施策なのですが、「キャッシュバック施策をやりたいけれど、社内でこの施策を了承してもらうためのプランニングを手伝って欲しい」とのご依頼が非常に多い。なぜなら、経営層やブランドマーケティングの方のなかには、「キャッシュバック」という直截的な表現を避けたい、使いたくないという方が多いんです。
━━それはなぜなのでしょう?
草刈:「あからさますぎる(品がない)」という意見もありますが、それ以上にマーケターの方は「お客様にそれ以上のコミュニケーションやブランド価値を提供しにくい」というネガティブな印象をもっているように思います。とはいえ、実際に購入するお客様にとっては「これを買うと現金が戻るのか」と単純明快な言葉であり、成果を見てもそれほど悪い印象はないというのが本音です。
解消すべきはブランドコミュニケーションとの相違
多田:私が過去に関わったプレゼントキャンペーンにおいても、「現金・商品券プレゼント」と「品物プレゼント」の2択だとすると、前者のほうが圧倒的に応募が多いんです。企業の方も、販促キャンペーンの施策としてキャッシュバックは外せない施策であることを理解しています。

新卒で入社し、流通小売業のオムニチャネル事業のほか、店頭販促の業務に従事。その後、現在所属しているデータドリブンプロモーション事業本部の前身である企画部門に異動し、データやトレンド分析に基づいた販促企画を立案する業務を担当。1年間を52週に分け、1週間ごとの販促を企画する「52週販促」などのスキームを用いて多角的な施策展開をサポートする
多田:ただ、コミュニケーションとして「購入した、現金をキャッシュバックした」だけではブランドの価値やストーリーを伝えられません。たとえばアイスクリームのキャンペーンで、「暑い夏に、このアイスを購入した方に携帯扇風機をプレゼント!」という施策であれば、「お客様には暑い夏を快適に過ごしていただきたい、暑いなかで涼む楽しみを体験していただきたい」という思いを伝えられます。こうしてライフスタイルに合わせたもの、体験価値を向上させるものをプレゼントするほうが、ブランドストーリーとしてはきれいにまとまりますし、価値提案しやすくなります。
キャッシュバックは非常に高い販促効果が見込めますし、メーカーであれば、キャッシュバック施策のなかで購入者のファーストパーティーデータを取得するというメリットもあります。ただ、あからさまに「キャッシュバック」と訴求するとそれだけで終わってしまいますし、これからも購入し続けるという動機付けにつながりません。そのサポートとして、当社にご相談いただくケースが増えているんです。
━━ブランドコミュニケーションの課題を克服し、効果的にキャッシュバック施策を展開するにはどういう戦略が必要なのでしょうか。
多田:ポイントは「キャッシュバックありき」ではなく、その後ろにあるバリューをいかにストーリー性をもって伝えていくかです。言い換えれば、インセンティブがキャッシュバックであっても、応募条件に採用されるアクションによってそれ以上の動機を提供でき、ブランドの価値を感じてもらえるということです。そこがコミュニケーションの肝になります。
この戦略のもと、私たちは三つの手法を提案しています。