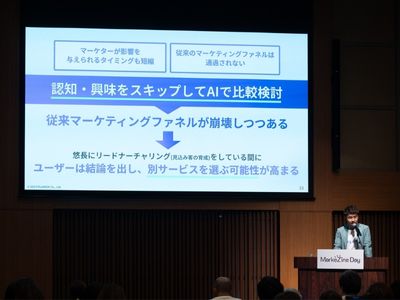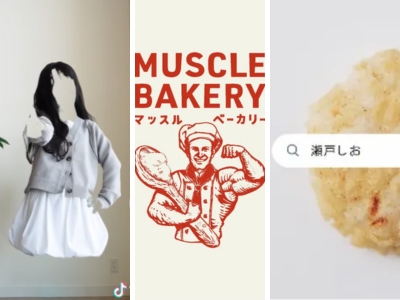初期段階に必要な「期待値のコントロール」「不本意なFBの抑制」
上西氏によると、Marubeni Chatbotの開発は当初2名の若手社員が主導した。2022年にGPT-3.5が発表された段階から技術動向を追い、GPT-4の登場後はすぐにチーム内へ開発を上申して開発に着手していたという。これ以降も一貫し、Marubeni Chatbotが内製で開発されてきたことは、普及を加速させた大きなポイントの一つだ。

内製による開発を決定したことにより、全社へ普及していく際の安心と信頼を獲得できた。社内の組織が作り、承認を経ているということで、業務への使用において信頼がある状態で使い始められたのだ。また、これによって社内の他の組織との連携もスムーズにでき、全社システムへの搭載やアナウンスなども行うことが可能になった。
また、コスト面も外部委託より安価に抑えられている。上西氏は「事業ごとの機能追加やトレンドに合わせた新たな機能追加をするときに、コストを最小化しながら行えることも普及に大きく影響していると思っています」と話す。
内製の強みはこれだけにとどまらない。2024年5月14日にOpenAIが「GPT-4o」を発表したときには、わずか半日で全ユーザーがこの最新技術を利用できる環境を整えた。上西氏は内製化の強みを活かしたこのスピード感も、社内で生成AI普及を加速させる一因となったと述べた。
ではこの初期段階で、普及にともなう社内へのコミュニケーションはどのように行ったのか。丸紅では特定ユーザーによる検証と全社向けウェビナーの開催を並行させており、これが効果的だったと話す。
ビジネス活用の検証については、テクノロジーに対するリテラシーが高い社内人材に限定して実施。そもそもデジタル・イノベーション部では「デジタル人財認定制度」を通じ、社内人材のデジタルに関するスキル/経験の可視化を行っている。AIのビジネス活用の検証にはこの制度で上位レベルと判断されたイノベーター層~アーリーアダプター層の人材を起用した。これには、初期段階における期待値のコントロールや、質の高いフィードバックを得る目的があったという。

一方、生成AIに対する社内の関心が高まる中で、「業務利用はできないのか?」という問い合わせが増加し、それに応える形で全社向けのウェビナーを開催。このウェビナーではデジタルの専門組織として正しい情報を伝えることに努めた。このときの参加者は500名を超え、生成AIへの注目度の高さから上西氏は「早期に全社公開へ向けたステップを踏んでいく必要性を感じました」と語った。
生成AI活用レベルをどう測る?全社での推進に必要な定義付け
続いて伊延氏が登壇し、生成AIを活用する環境づくりと普及へのアプローチについてMarubeni Chatbotが全社に公開されて以降の経緯を基に解説した。

Marubeni Chatbotは2023年6月に正式なローンチ版へアップデートされ、全社公開に踏み切った。現在では先述の通り、9,000ユーザーを超える規模に成長している。内製化によるクオリティの高いアプリケーション開発が、普及の重要な役割を果たしたことは間違いない。しかし、全社での活用を推進するには、アプリケーションの質だけが重要なわけではない。そもそもDA課が担うのは、「全社変革」と「DX推進」であり、まだゴールではないのだ。伊延氏は社内における生成AI活用レベルの定義付けと目標設定、そしてアプローチの指針について触れた。
生成AIの活用といっても、イメージするものは人によって異なる。機能開発や普及施策を進めていくにあたって、自分たちの生成AI活用がどのレベルにあるのか、目線を合わせる必要もあった。伊延氏は「そのため我々は、生成AIの活用推進を複数のレベルに分けて取り組むことにしました」と語る。同組織では、生成AIの活用レベルを4段階に分類。下から順に「Chatbotの導入」「コーポレートスタッフ業務の効率化」「営業業務効率化/高度化」となり、最終的には「経営判断」といった高度な領域で、生成AIを活用できるように検証を進めていく計画だ。

では、普及に向けた本格的な社内アプローチはどのように進めたのか。伊延氏はターゲットの規模とレベルで分ける戦略を説明する。